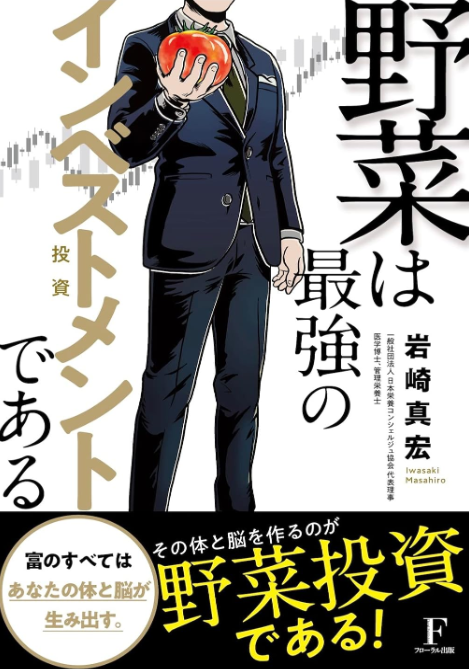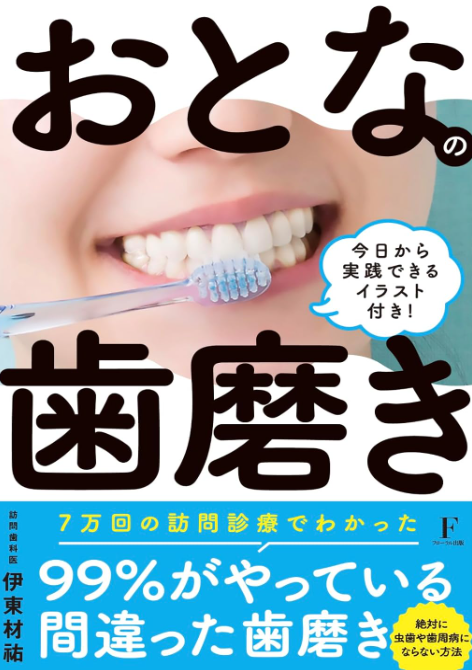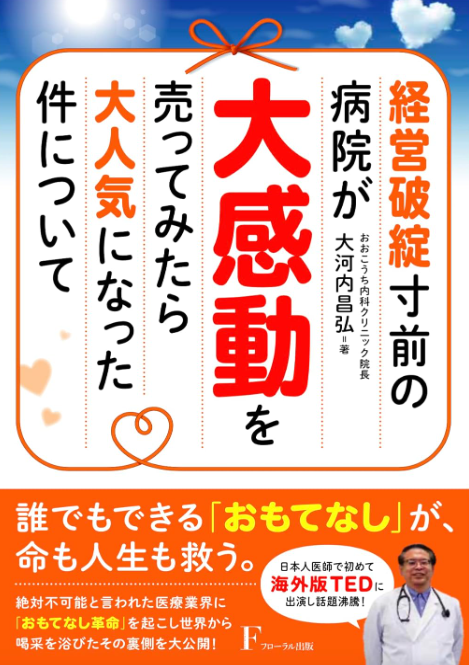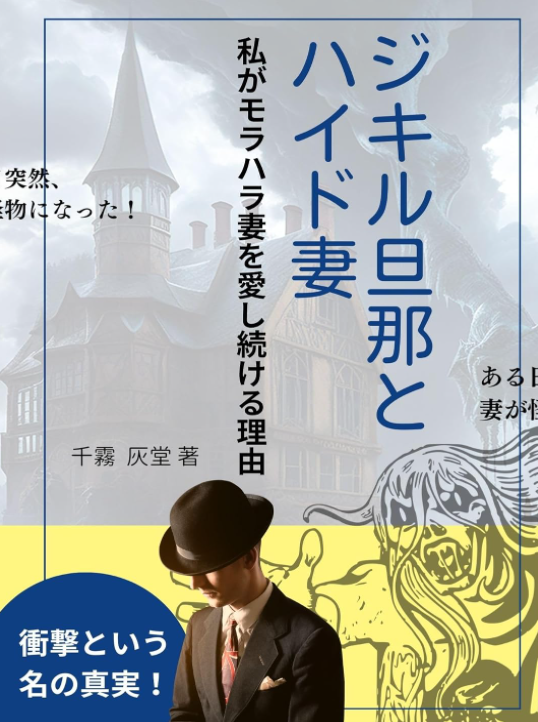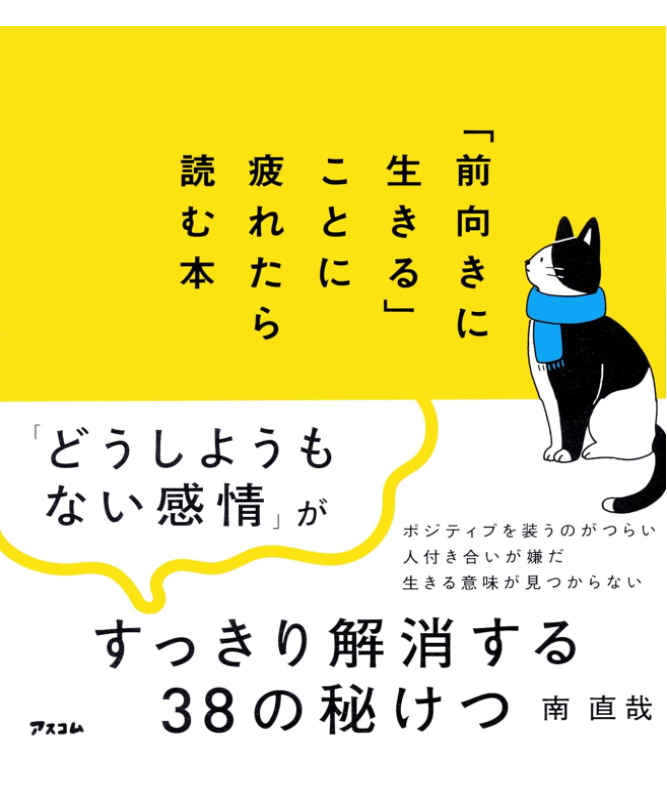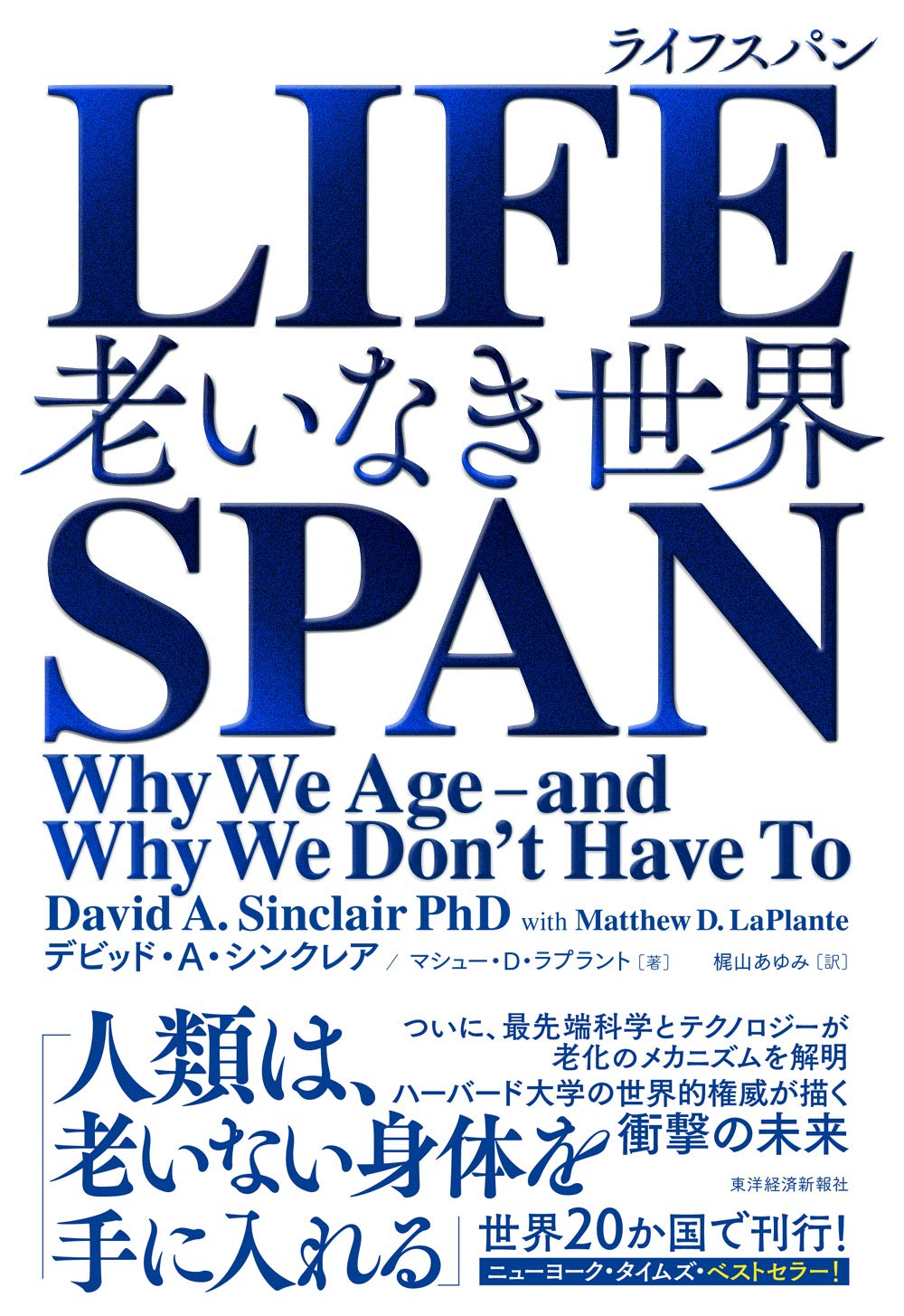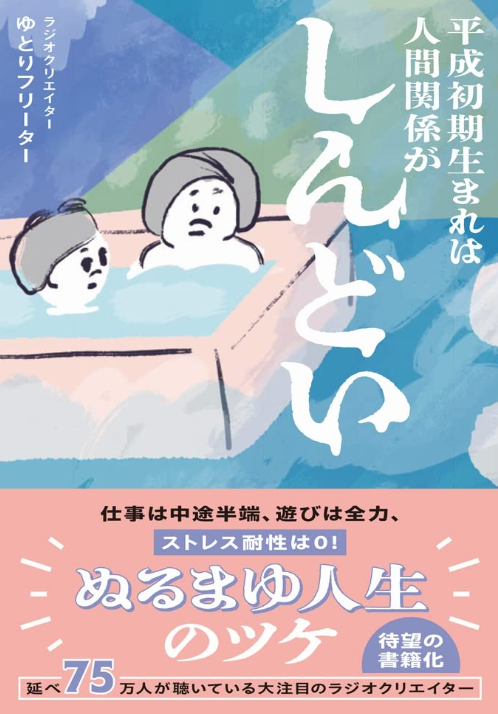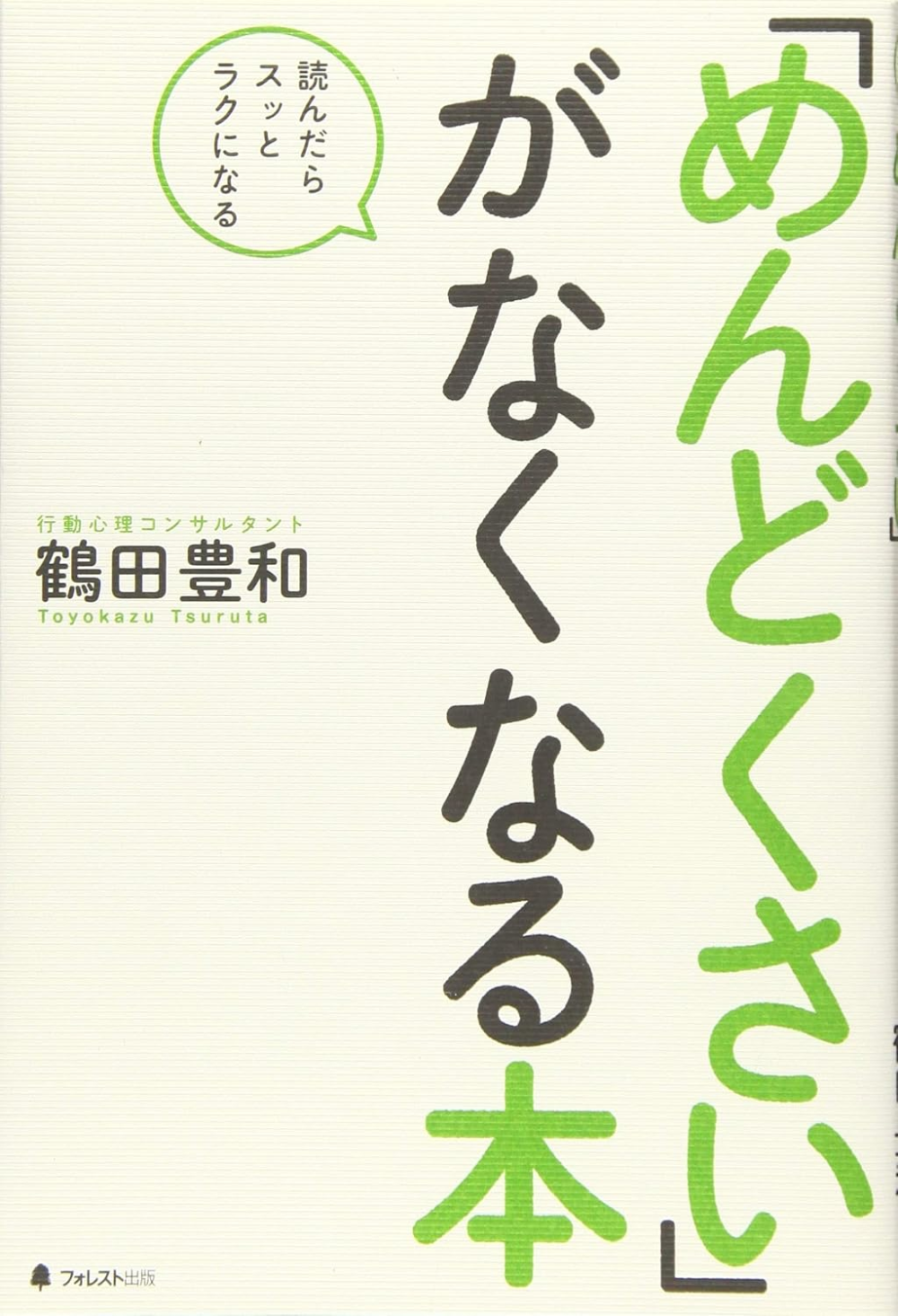【認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること】
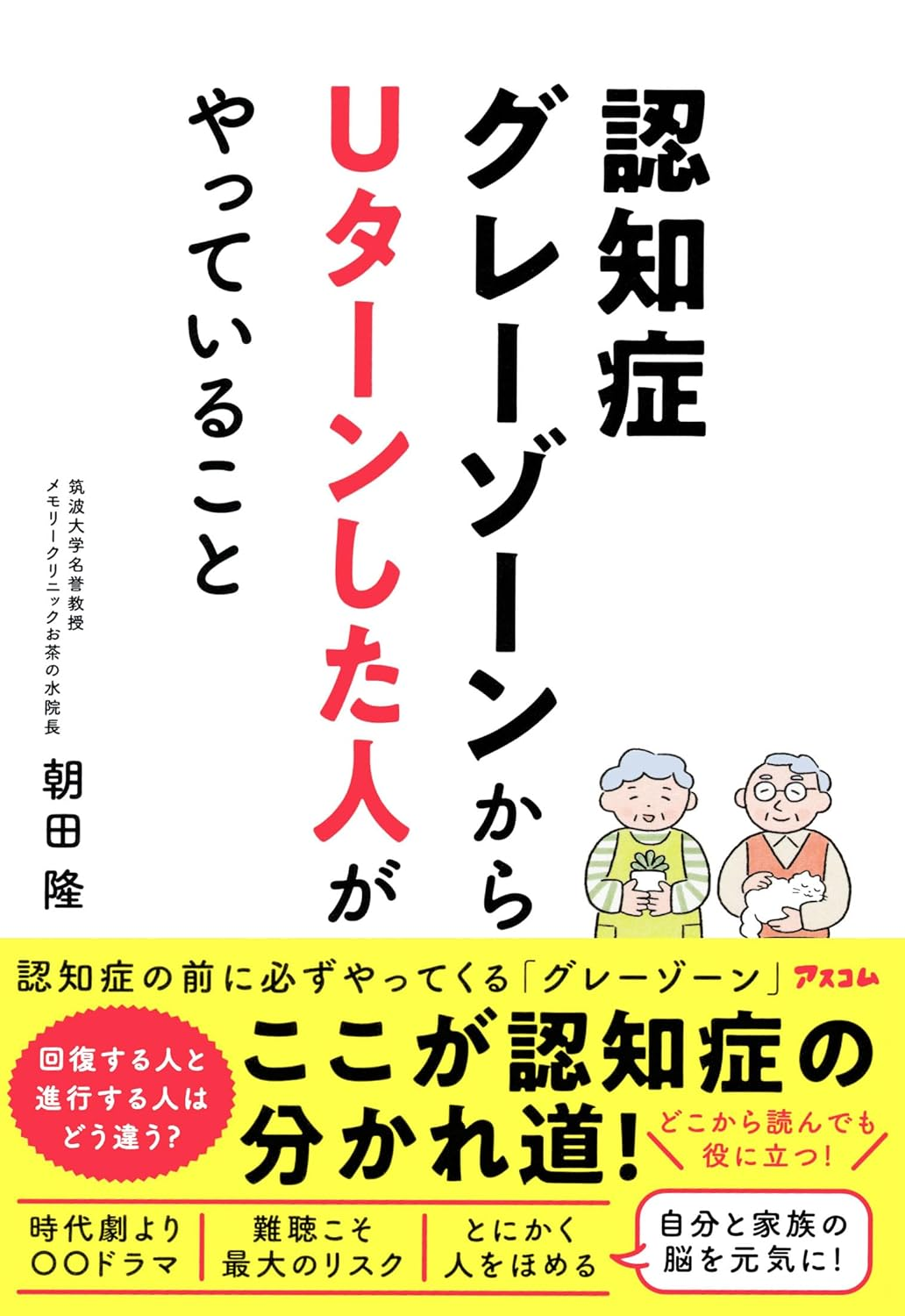
インフォメーション
| 題名 | 認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること |
| 著者 | 朝田 隆 |
| 出版社 | アスコム |
| 出版日 | 2023年9月 |
| 価格 | 1,540円(税込) |
ある60代の女性が、著者の認知症専門クリニックを訪れました。
なんでも、10個入りパックの卵を3日連続で買ってしまい、ついに4日目になった時、不安にかられて訪ねたのだそうです。
診断の結果、女性は認知症ではありませんでした。
かといって、正常な状態の脳の状態でもありません。
「認知症グレーゾーン」だったのです。
認知症グレーゾーンの正式名称は、MCI(軽度認知障害)。
MCIとは、日常生活に大きな支障はないものの、本人やご家族にとっては「最近ちょっとおかしいなあ」と感じるさまざまな警告サインを発する状態。
いわば、正常な脳と認知症の間の状態です。
認知症に認知症になる人はその段階として、必ずこのグレーゾーンを通るのですが、全ての人がグレーゾーンから認知症に移行するとは限りません。
現状維持する人もいれば、適切な対応することで認知症への移行を遅らせることもできます。
さらには、4人に一人は健常な脳の状態にÜターン(回復)できることがわかっているのです。
一方でそのまま認知症へ進行してしまう人もいます。
つまり、ここが「認知症の分かれ道」。
では、回復する人と進行してしまう人の違いは、いったいどこにあるのか?
それがこの本のテーマです。
まずは、あなたの認知機能を簡単にテストしてみましょう。
<キツネ回転テスト>
①左右の手でキツネの形をつくります。
②キツネの形をキープしたまま、左手の人差し指と右手の小指、左手の小指と右手の人差し指をつけます。
このとき、どちらかのキツネが自分の方を向き、もう片方のキツネは外を向いている「逆さギツネ」になっているはずです。
しかし、頭頂葉の機能が衰えてくると、手を回転できずに、キツネが両方とも外を向いてしまうことが非常に多いのです。
他にも、チューリップ、ハトの回転テストや、10時10分の時計を描くテストなど、グレーゾーンのセルフチェックをこの本ではたくさん用意しました。
では、具体的にUターンするためには、どうするの?
その答えも、すべて本書の中にあります。
・恋愛ドラマを観るだけで脳内にある物質があふれ出す
・瞑想よりも塗り絵が脳にいい理由
・思い出を話すだけで脳が元気になる「回想法」
・脳にいい「ほめ方」
・認知機能が平均34%アップした「すごい歩き方」
・脳を意図的に混乱させる方法
・2つ以上の作業を同時に行う「デュアルタスク」で脳を活性化するワケ
・認知症リスクが最大23%下がった脳によい食事
・脳のごみを洗い流すよい睡眠
などなど、日常の習慣をちょっと変えるだけで、Uターンへの道はひらけます。
そのための方法を、この本ではたくさん書きました。
日本の認知症治療の第一人者と知られる著者が、40年にわたり、2万人以上の患者と向き合いたどりついた答えです。
難しく考えず、「これならできそう」「楽しそう」と思うものから試してください。
じつは認知症は、長い年月をかけて認知機能が低下し、発症する生活習慣病のひとつ。
認知症を発症する20年も前から、脳の変化は始まっています。
まだグレーゾーンにまでは至らない方や、40代、50代の方にとっても、この本がいつまでも若々しい脳を保つために役立ちます!
引用:アスコム
ポイント
- 認知症になる人は、その前段階として“認知症グレーゾーン”を通る。4人に1人は、そこから健常な脳の状態にUターン(回復)できることがわかっている。
- 認知症の入り口は意欲の低下である。その最初のサインが「めんどうくさい」。「めんどうくさい」が始まった段階で発見し対応することで、Uターンの可能性が高まる。
- 認知症グレーゾーンから健康な脳にUターンするためには、生活習慣の見直しが必要だ。ポイントは、挑戦、変化、生きがい、孤独の回避、利他である。
サマリー
はじめに
認知症になる人は、その前段階として“認知症グレーゾーン”を通る。
これは日常生活に大きな支障はないものの、本人やご家族が「ちょっとおかしいなあ」と感じるさまざまな警告サインを発する状態で、「軽度認知障害(MCI)」と呼ばれる。
しかし、4人に1人は、そこから健常な脳の状態にUターン(回復)できることがわかっている。
本書では、単なる老化現象とグレーゾーンの見分け方、Uターンするための対処法を、具体的な事例をあげながらお話ししていく。
「認知症グレーゾーンのサイン」と単なる老化の違い
最初のサインは「めんどうくさい」
認知症の入り口は、意欲の低下である。
その最初のサインが「めんどうくさい」だ。
モノを考えたりがんばろうと思ったり、仕事をテキパキこなしたりできるのは、「前頭葉」と呼ばれる脳の活発な働きによる。
「めんどうくさい」は、この前頭葉の働きが大幅に低下するために起こる。
趣味、仕事・家事・育児、さらには「歯みがき」のような長年の習慣さえもめんどうになり、先送りするようになる。
このサインを見過ごして放っておくと、やがて脳の中で記憶を管理している「海馬」と呼ばれる部位が縮み始める。
こうなると「記憶の低下」が急速に進み、対策をしなければ、本格的な認知症へ。
「めんどうくさい」が始まった段階で発見し、対応することで、Uターンの可能性が高まる。
単なる老化との違い
どんなに社交的な人でも、年をとって足腰が弱ってくると外出は減る。
それでも、馴染みの店へ出かけたり、行きつけの美容院に行ったりして日常を楽しめているなら、単なる老化の範囲内である。
もともとは社交家だったのに急に出不精になったというような、大きく性格が変わってしまうようなケースは危険サイン。
ポイントは、「もともとはどうだったのか」という点である。
芸能人などの名前がなかなか出てこないのも、年をとるとよくあることだ。
しかし自分の子どもや孫など、ごく身近な親族の名前をなかなか思い出せないとなると、認知症グレーゾーンの可能性が高い。
パタリと料理をしなくなるのも、グレーゾーンの代表的なサインだ。
料理は、脳がフル稼働していないとできないものなのである。
認知症グレーゾーンからUターンするための生活習慣
生活習慣5つのポイント
認知症グレーゾーンから健康な脳にUターンするためには、生活習慣の見直しが必要である。
キーワードは「わくわく」。
わくわくすると、ドーパミン、オキシトシン、セロトニンという神経伝達物質の分泌が活発になる。
三大ホルモンと呼ばれるこれらの脳内ホルモンは、認知症の予防、ひいては認知症グレーゾーンからのUターンにも大きく寄与する。
次の5つがポイントになる。
①挑戦
「もう年だから」と、やりたいことを我慢したり、楽しいことをあきらめたりすると、脳への刺激が減って認知症対策には大きなマイナスになる。
「年甲斐もない」挑戦が、脳と体の若さを保つ最大の秘訣だ。
②変化
変化のない毎日を送っていると、脳はどんどん縮んでしまう。
「いつも」と違う新しいことを少しずつ始めてみると、脳の刺激になる。
③生きがい
楽しいこと、夢中になれることを見つける。
植物や動物を育て成長を見守るのは、癒しにもなる。
④孤独の回避
孤独になると脳が縮み、メンタル面のリスクも高める。
認知症予防には、人と積極的に交流することが重要である。
⑤利他
ボランティアのような他者のために力を尽くす活動をすると、自分の幸福感が高まることが知られている。
恋愛ドラマを観ると脳内ホルモンが分泌
恋をすると、3つの脳内ホルモンがあふれるほど分泌される。
本気で恋愛感情を抱かなくても、ドラマや映画などを見て、「この人ステキ」とあこがれるだけでもいい。
このような感情も十分にときめきであり、脳内ホルモンは分泌される。