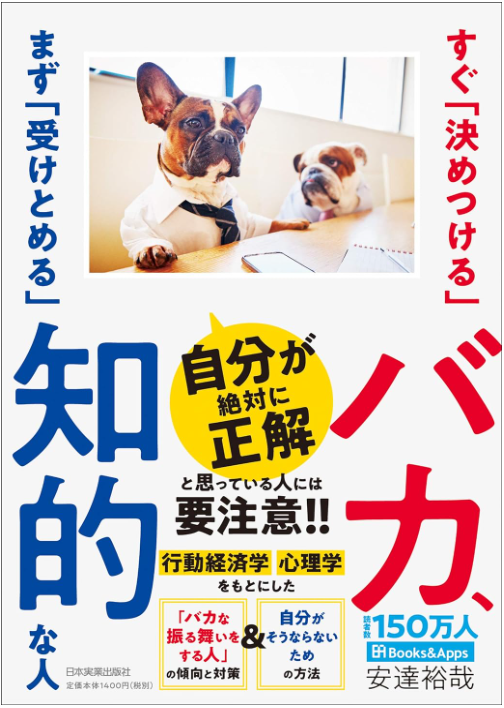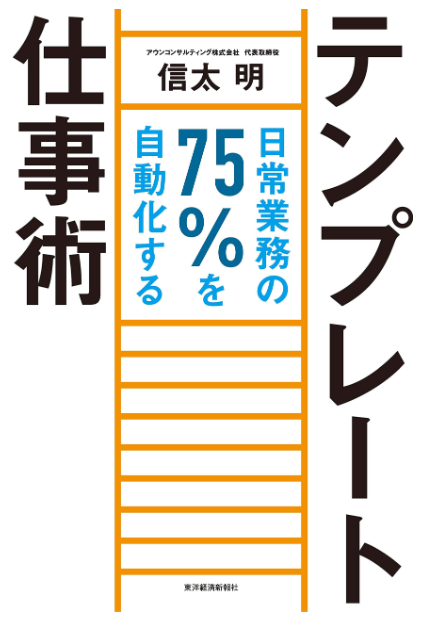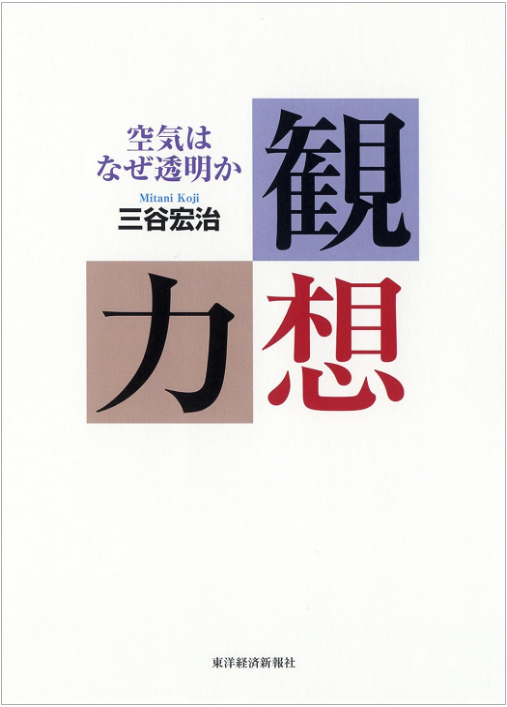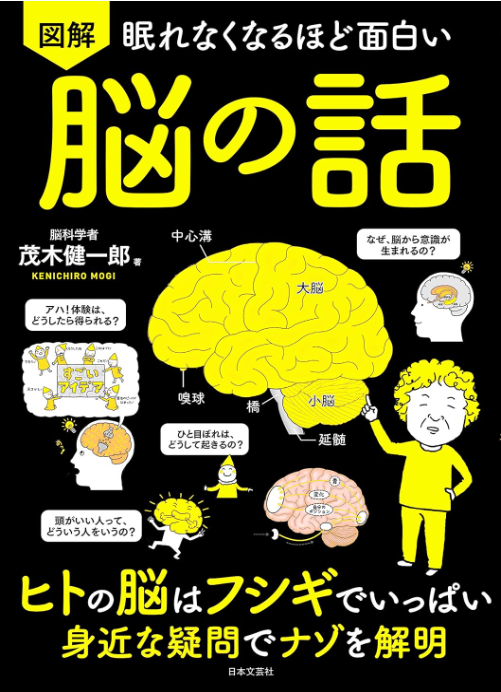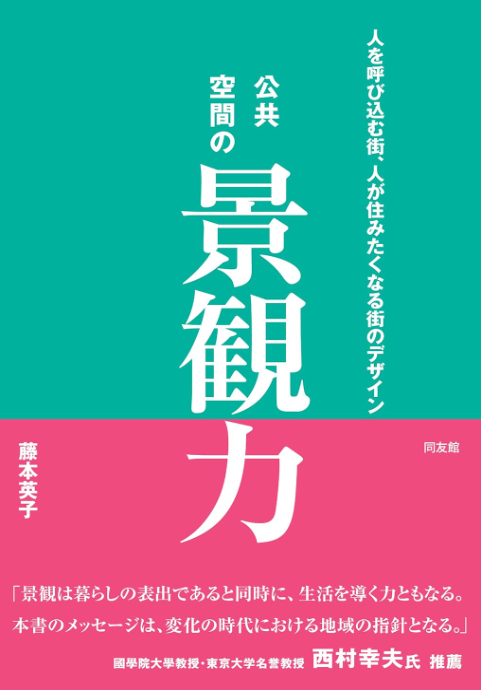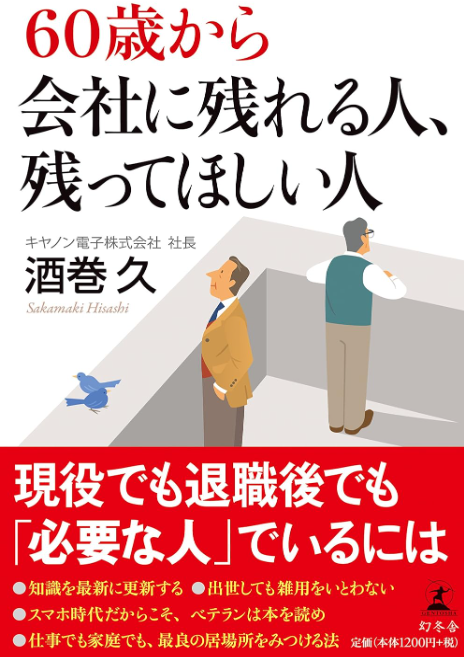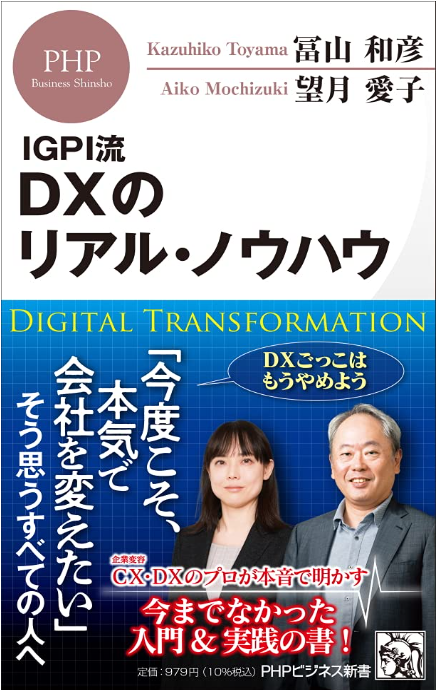【今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」】
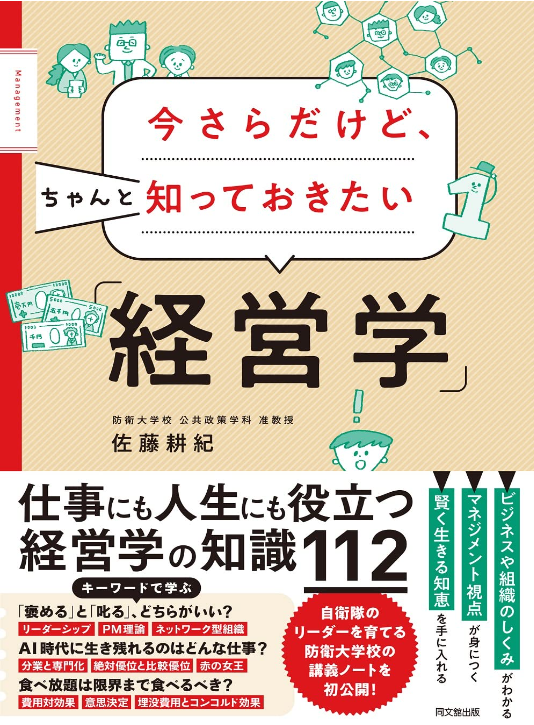
インフォメーション
| 題名 | 今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」 |
| 著者 | 佐藤 耕紀 |
| 出版社 | 同文館出版 |
| 出版日 | 2021年6月24日 |
| 価格 | 1,870円(税込) |
ポイント
- 経営学の基本は「費用対効果」(効率、生産性)という考え方だ。これを理解して実践すれば、短い時間で多くのことをこなして、自由に好きなことができる人生に近づくことができる。
- 経営は確率のマネジメントである。成功の可能性を高くすることに注力し、「概ね良好」でいいのである。
サマリー
はじめに
本書を書くにあたり、最初に考えたのはどういう性格の本にするかということだ。
著者は、かねてから、経営学の文章はともすれば難解で、実際に何の役に立つのか分かりにくい面があると思っていた。
一方、実務家やコンサルタントの解説は、ときとして論理性や根拠に乏しいとも感じていた。
そこで、科学的な理論に裏打ちされつつも、「わかりやすい」「役に立つ」にこだわった本をつくりたいと考えた。
まさに、読者にとって、コストパフォーマンス(費用対効果)のよい本をつくろうと思ったのだ。
経営学の基本は「費用対効果」(効率、生産性)という考え方だ。
これを理解して実践すれば、短い時間で多くのことをこなして、「お金」や「時間」や「知識」を得られ、自由に好きなことができる人生に近づけるのである。
もう少し具体的にいえば、経営学を学ぶことで、
「要領よく仕事をする」(1章)
「賢い判断をする」(2章)
「売上や利益を増やす」(3章)
「小さな費用で大きな成果をあげる」(4章)
「ライバルとの競争に勝つ」(5章)
「組織の仕組みを理解する」(6章)
「やる気を活かす」(7章)
「マネジメントの仕組みを理解する」(8章)
「自分の価値を活かす」(9章)
「豊かな人生を切り拓く」(10章)
「生産性の高い働き方をする」(11章)
といったことのヒントが見つかるはずだ。
ビジネスで費用と効果を金額で表す
何をするにしても得られるものと失うもの、プラス面とマイナス面がある。
プラス面は活動から得られる「効果」、マイナス面はその「費用」(活動のために消費した資源)だ。
企業会計では、ある時点の「資産」や「負債」の状態を金額で表す「賃借対照表」、一定期間の収益や費用の状況を金額で表す「損益計算書」といった「財務諸表」を作成する。
資産から負債を引いた純粋な資産のことを「純資産」というが、企業の「純資産」とは、ダムに溜まった水のようなものである。
上流から流れ込む水が「収益」、下流へ流れ出る水が「費用」にあたる。
流入の方が多い時(純利益)、その分だけダムの水(純資産)が増える。
流出の方が多い時(純損失)、その分だけダムの水(純資産)が減る。
純損失(赤字)が続いてダムの水が底をつくと「債務超過」に陥り、倒産の危機にさらされるのだ。