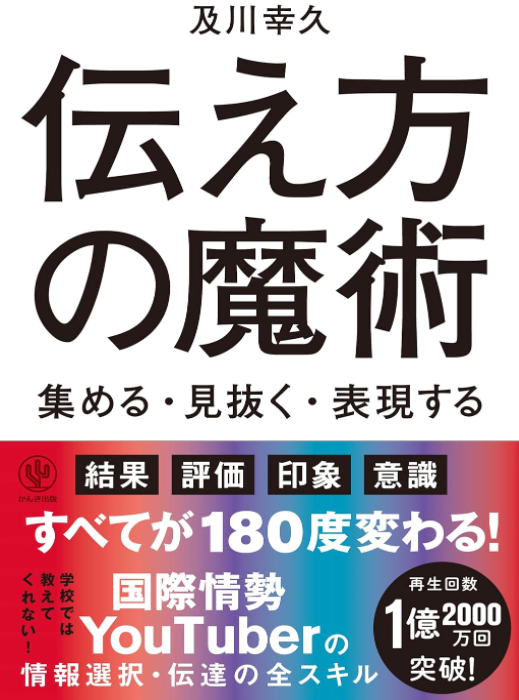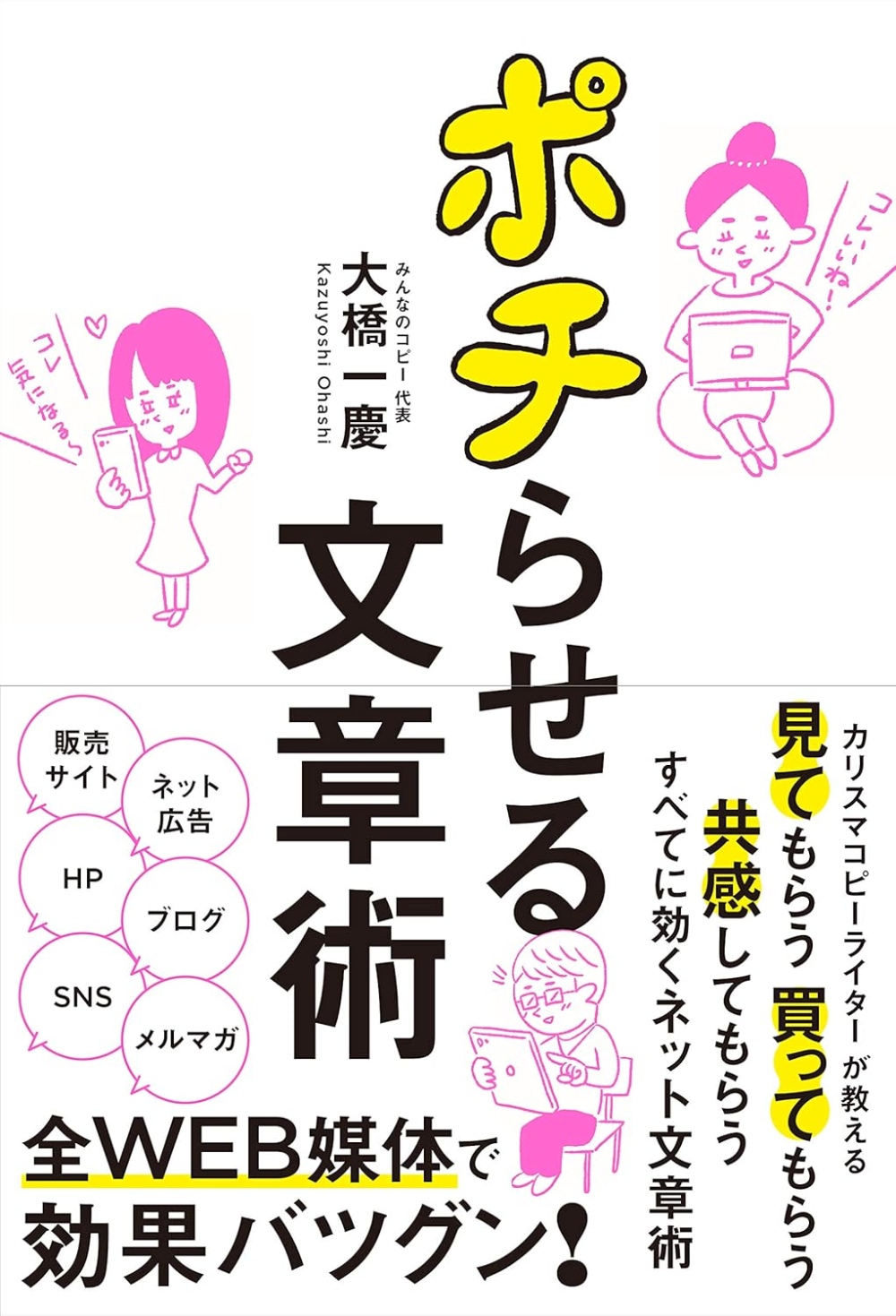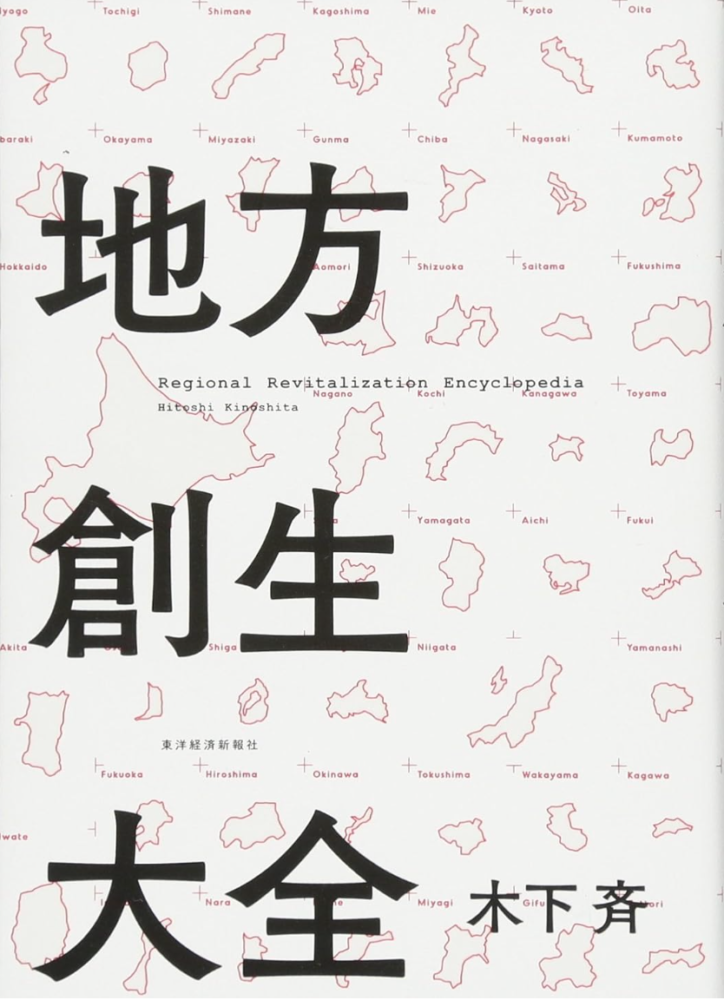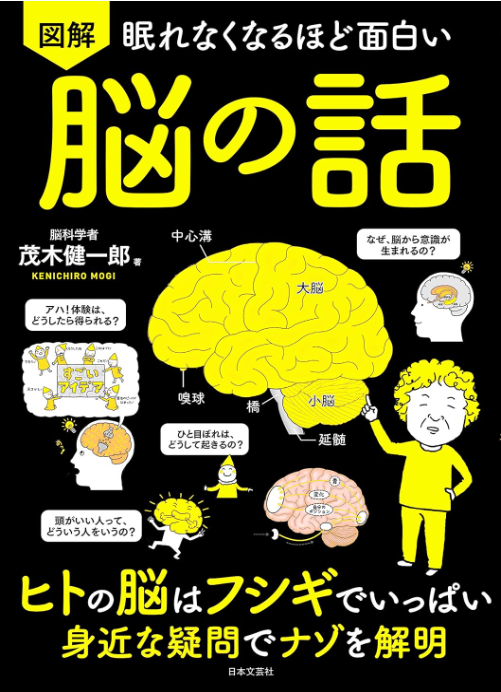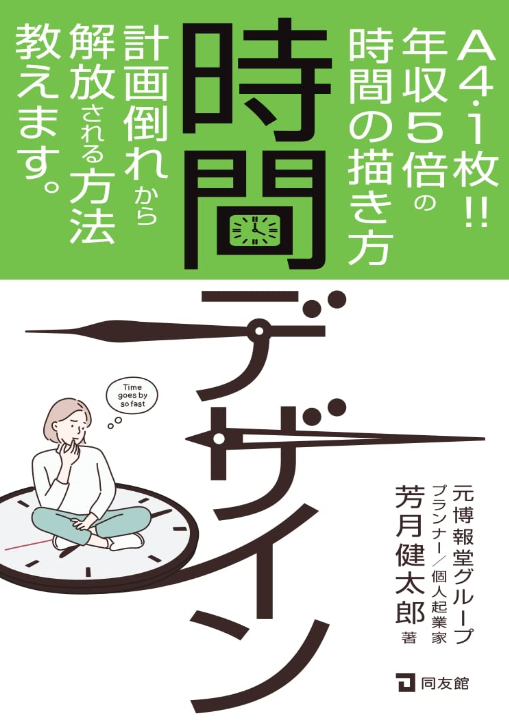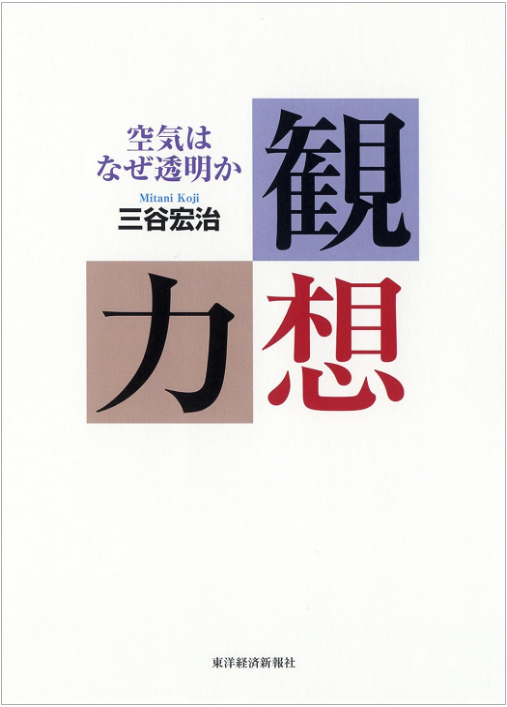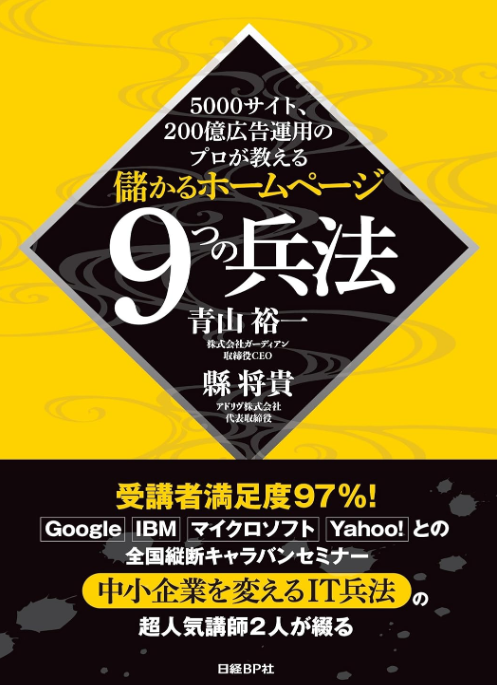【広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。】
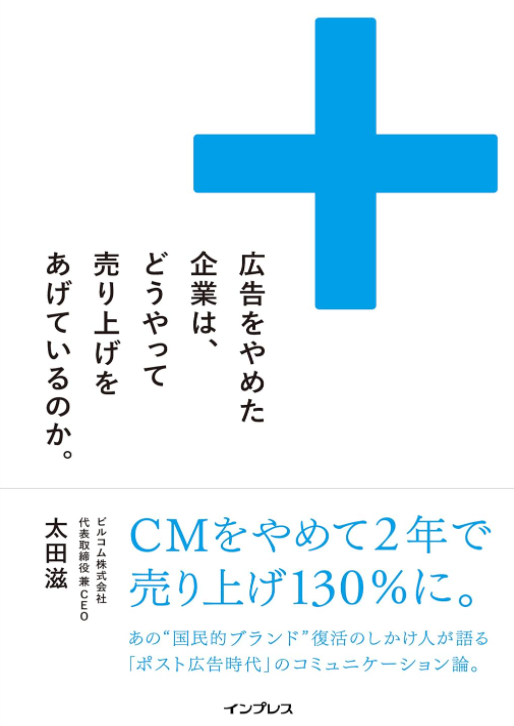
インフォメーション
| 題名 | 広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。 |
| 著者 | 太田滋(おおたしげる) |
| 出版社 | インプレス |
| 出版日 | 2018年1月31日 |
| 価格 | 1760円(税込) |
広告がかつてのようには効かなくなった。かけた費用に見合うだけの効果が得られなくなった。広告の炎上がおそろしい──。企業の担当者が広告にアタマを抱えるいまの状況は、なぜ起こっているのか。そんななかで企業は、どのように生活者に働きかけていけばいいのか。歴史ある国民的食品ブランドを復活に導いたり、高い技術に支えられてはいたものの知名度ゼロだったホーロー鍋を短期間のうちに「15ヶ月待ち」の予約状態にもちこんだりと、広告をつかわずに数々の企業の売り上げをあげてきた筆者が、その知見をまとめた1冊です。
はじめに──どうして「ちがい」が生まれたのか
第1章 なぜ「広告をやめたい企業」が増えているのか
第2章 広告は本当に効かなくなったのか
第3章 広告に代わる「つぎのコミュニケーション」
第4章 広告をやめた企業はこうやって売り上げをあげる
第5章 科学を武器にしたPR的コミュニケーションの可能性
おわりに──「信頼」が競争軸になる時代
引用:インプレス
ポイント
- いまの時代に適した企業のコミュニケーションのあり方を考えるには、まずその時代の社会のコミュニケーション作法を把握する必要があるのだ。
- パブリックレーションズ(PR)とは、組織とそれを取り巻く生活者とのあいだに、社会善を意識した交互に理想的な関係を築くべく、メディアや個人などの第三者の媒介を交えつつ、信頼にもとづいておこなうコミュニケーション活動である。
- ソーシャルメディア時代の消費心理プロセスとして、筆者が提唱しているのが「PLSA」というモデルだ。「Perseption(認知・認識)」「Listing(登録・リスト化)」「Simulation(評価)」「Action(消費・体験)」である。
サマリー
どうして「ちがい」が生まれたのか
この数年、企業の事業担当役員や広報宣伝部門の責任者は、広告がかつてのようには効かなくなったと異口同音に語る。
本書は、そんな悩みに答えるべく、筆者が代表をつとめるビルコム株式会社がもつ、広告に代わって売り上げをあげることができるコミュニケーション手法に関する知見をまとめたものだ。
私たちの手法は広告とは異なるものだが、世界的な広告賞を獲得した仕事もいくつかある。
それほどに「広告に近いところ」で活動してきたのだ。
だが、近くはあっても、「広告が効かなくなった」という声が高まる中で、私たちの「広告ではないコミュニケーション」の効果は高まっている。
どうして「ちがい」が生まれたのか。
それは、どこからくるのか。
本書では、それを読み解くため、広告的アプローチが効かなくなったという客観的事実に着目し、今起こっている事柄を冷静に読み解くところから、変化の根っこにあるものの分析に取り組んだ。
さらに「つぎの時代のコミュニケーション」に必要な用件を導き出し、広告に代わり売り上げに貢献できるコミュニケーションについての解説を試みている。