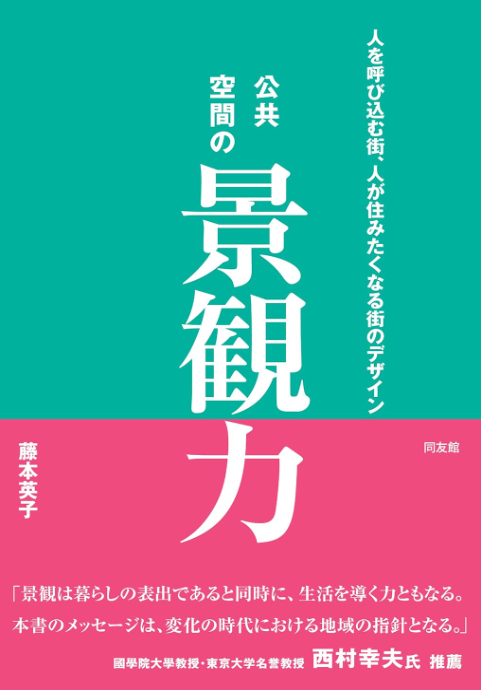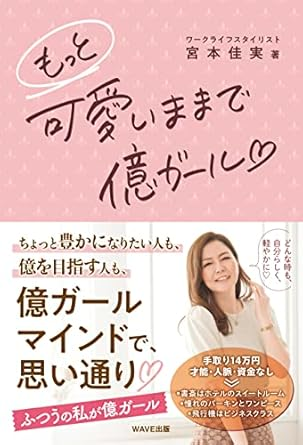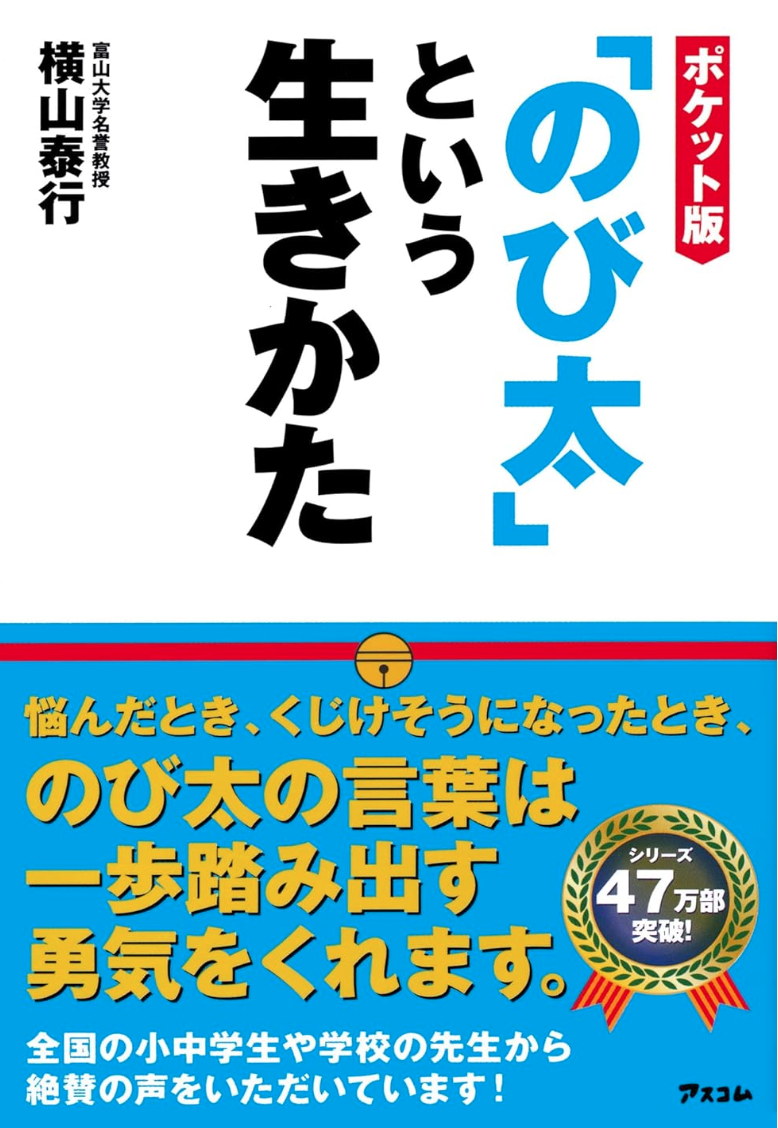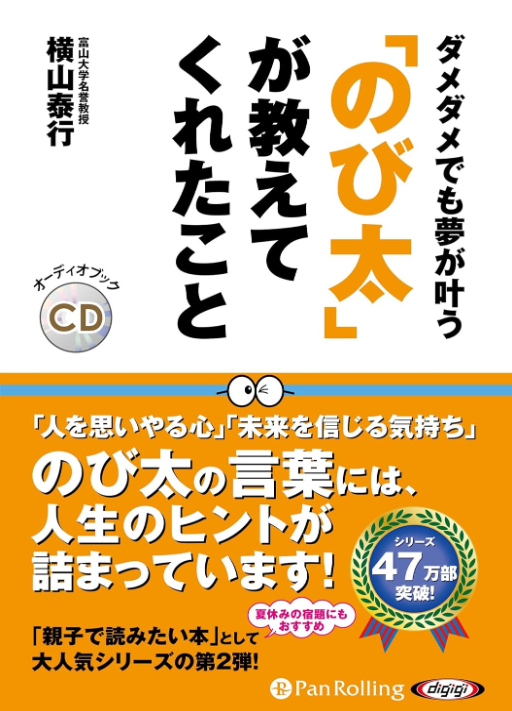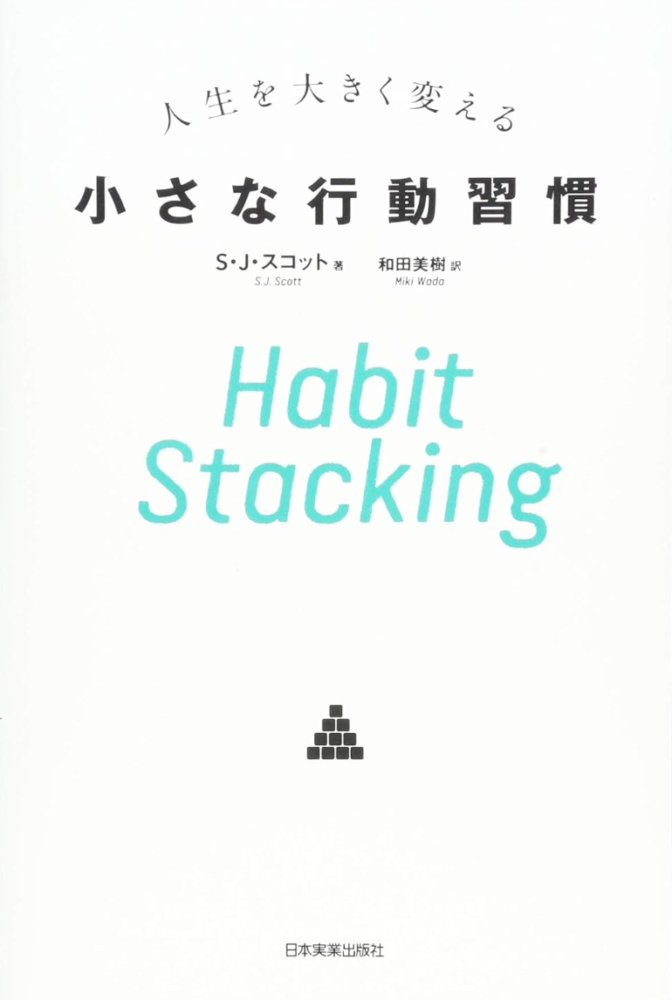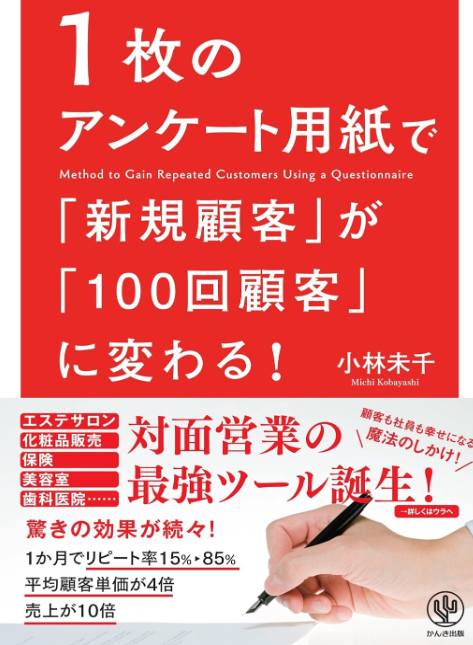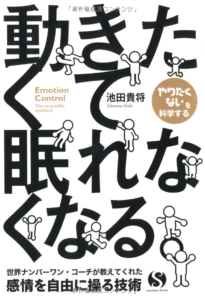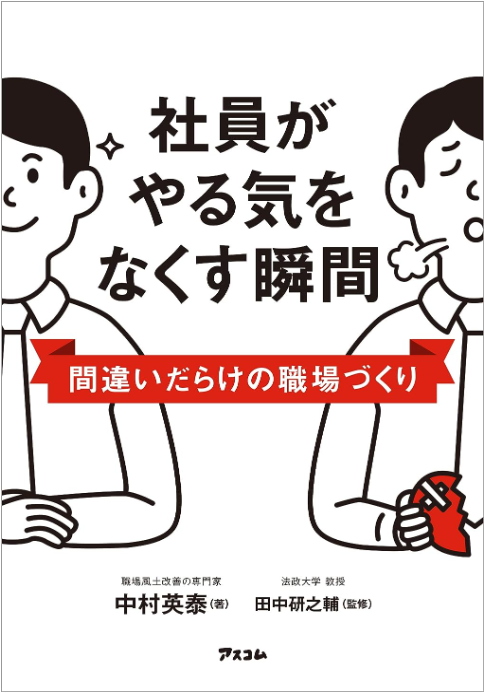【「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた】
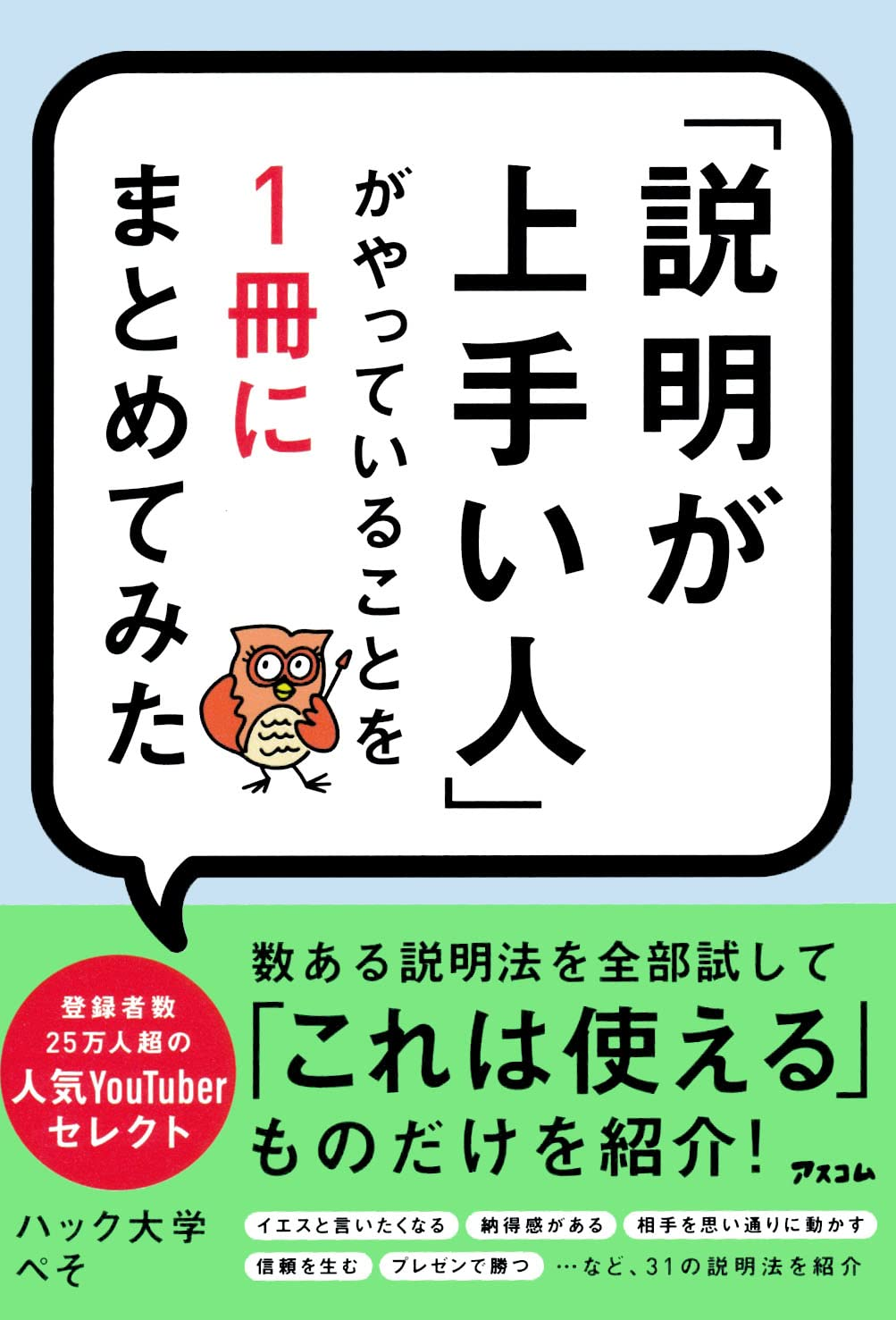
インフォメーション
| 題名 | 「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた |
| 著者 | ハック大学 ぺそ |
| 出版社 | アスコム |
| 出版日 | 2022年2月 |
| 価格 | 1,540円(税込) |
以下、著者の「ハック大学 ぺそ」が実際に試して
「使えなかった説明法」です。
●ロジカルトーキングで理路整然と伝える
●相手に思いが伝わるように熱意を込める
●必ず結論から端的に話す
●相手の話を遮らないように相槌を打ち続ける
●相手が理解しやすいようにまずは詳しい状況説明をする
●上司が判断しやすいように起きたことを時系列で話す
●モレがないように知っていることは全て話す
●ビジネス用語や横文字を駆使してカッコよく説明する
●指示する場合は「やること」だけを端的に伝える
●有名経営者のような華麗なプレゼンで魅了する
この10個の「使えなかった説明法」、みなさんはどんな感想をお持ちでしょうか?
「確かに、それダメそう」という項目もあれば
「何で、それがダメなの? 私もよくやってるよ」と思う内容もあるかもしれません。
なぜ、ダメなのか?
詳細はこの本の中でご説明しますが、一例を挙げてみます。
「ロジカルトーキング」は一見、マストな説明法のように思えるかもしれません。
もちろん、短い時間で端的に「報告」する場合は、それでいいケースもあります。
でも多くの場合、「論理だけ」だと、分かりにくい説明になりがちです。
例えば、いま流行りの「サブスク」について、あまり詳しくない人に説明する場合
「サブスクというのは、一定期間、定額料金を払うことで、
継続的に商品やサービスを利用し続けられるビジネスモデルです」
とロジカルに説明されたらどうでしょうか。
確かに正しい説明ではあるのですが、わかるような、わからないような、
相手はそんな受け取り方をするかもしれません。
一方で
「サブスクというのは、要は、1カ月単位の焼き肉食べ放題のようなもので、
飲食以外にも、ファッションや音楽配信などいろんなモノがある感じですよ」
と説明したらどうでしょうか。イメージしやすいですよね。
ポイントは左脳と右脳を両方働かせること。
自分たちの生活に身近なものに例えることで、「なるほど」と相手も納得してくれます。
このように、上手な説明には「コツ」があります。
ご心配なく、そんなに難しい話ではありません。
この本に載っている、いくつかのテクニックを覚えればいいのです。
「ちょっとしたテクニック」を身につけて、
上手に使い分けられるようになれば、誰だって説明力はぐっと上がります。
ぜひ、ご一読ください。
引用:アスコム
ポイント
- 説明が下手な人は、みな同じような思考回路をしている。相手を無視して自分ファーストになっていたり、相手の期待に応えるための「戦術」を考えていない。
- 説明はまず「結論」から話すことを心がけよう。また、「事実」と「自分の解釈」を区別しよう。
- ビジネスでは「短く話す」は鉄則。説明が長くなってしまう人は「知っている内容全てを話そう」とするが、その必要はない。
サマリー
はじめに
上手な説明には「コツ」がある。
いくつかのテクニックを覚えて、上手に使い分けられるようになれば、誰でも説明力はぐっと上がる。
説明が上手くなると、話がスムーズに進むだけでなく、相手に「すごい」と思われ、「大事な仕事を任せても上手くやってくれるだろう」と、評価が上がる。
つまりあなた自身の「価値」を周囲に認めさせることができる。
逆に説明が下手だと、「この人とは仕事をしたくない」と判断されても仕方がない。
説明が上手くなることは、最高のブランディングなのである。
説明下手な人にありがちな特徴
説明力のテクニックを使いこなすには、まず「考え方」を押さえるのが早道だ。
説明が下手な人は、みな同じような思考回路をしている。
その特徴には、次のようなものがある。
「自分ファースト」になっている
説明がうまくいかない最大の理由は「相手を無視している」から。
「説明しよう」という気持ちばかりが先走ってしまい、「相手のことを考える」という大原則が、消し飛んでしまうのである。
いい説明とは、相手の得につながるものだ。
「この商品をお使いになりますと、年間で最大10万円もお得になります」と、「私どもは、この商品を開発するために2年の歳月を費やしました」では、多くの人が前者に興味を示すだろう。
それは「相手ファースト」の立場で、相手にとってのメリットを具体的に示しているからである。
後者は「私はこんなに大変だったんです。聞いてください」と一方的に話している印象を持たれかねない。
説明がうまく伝わらない場合は、「自分ファースト」になっている可能性が高い。