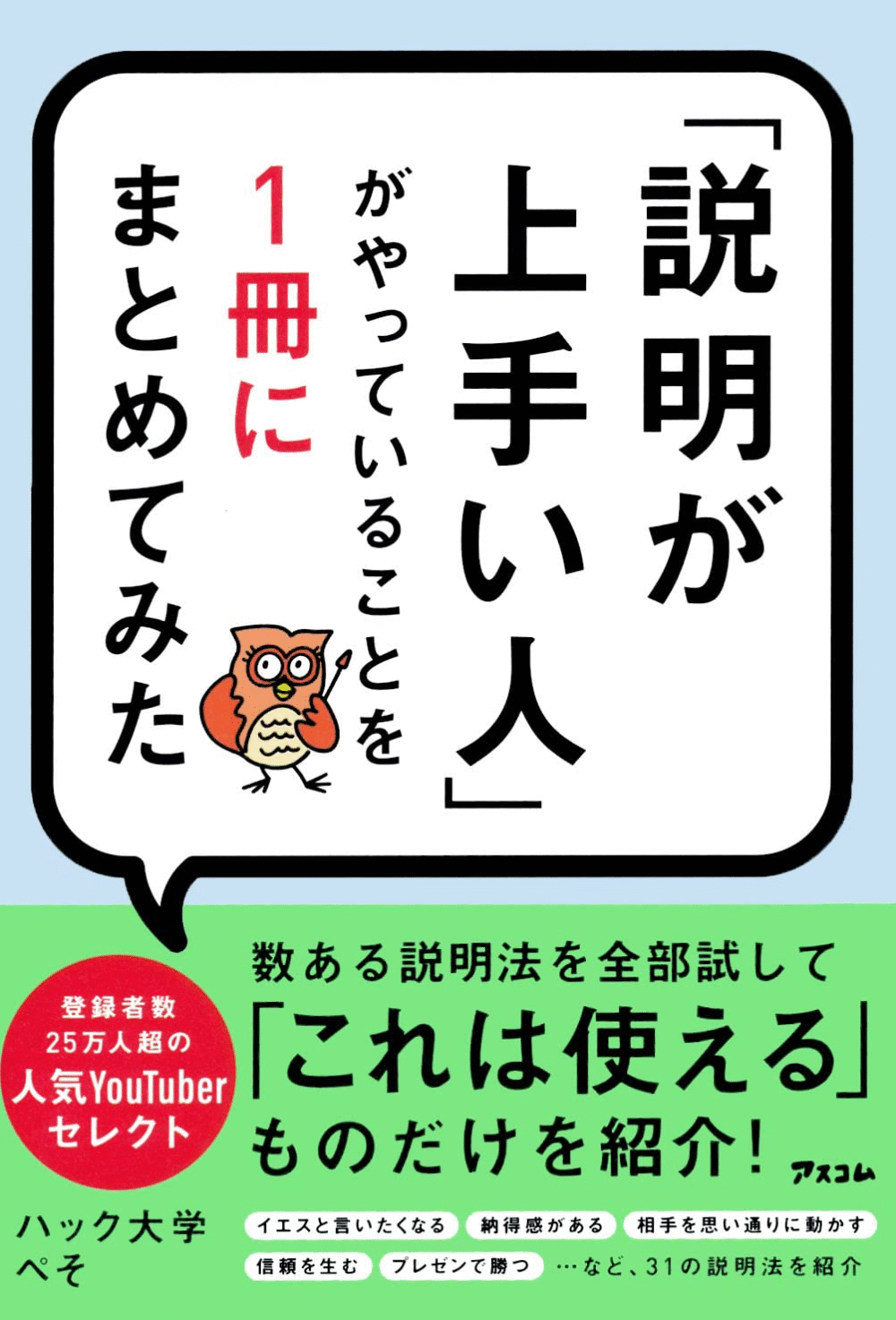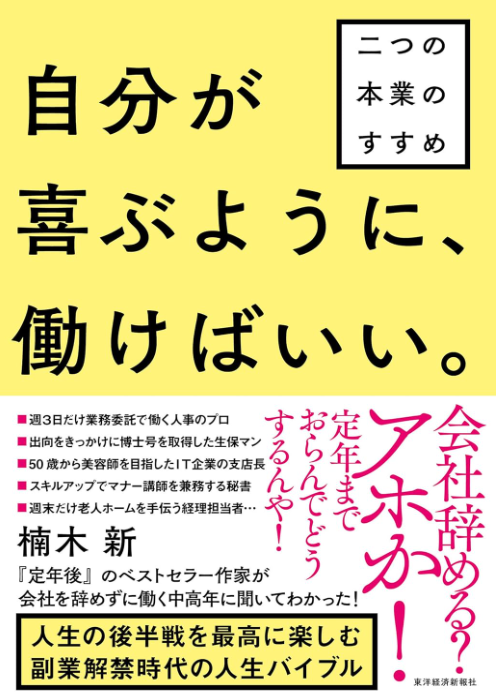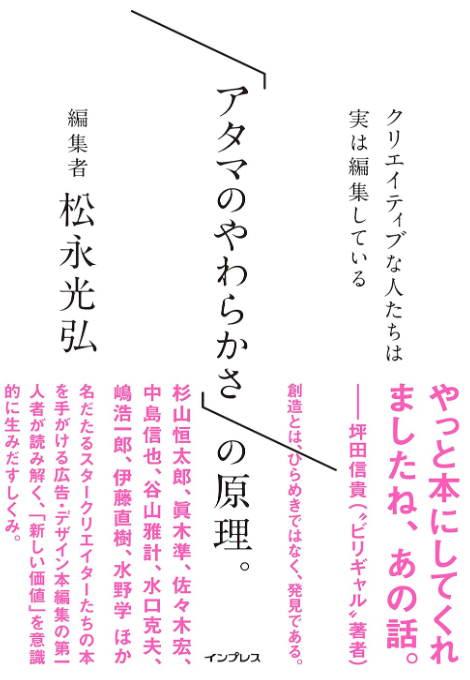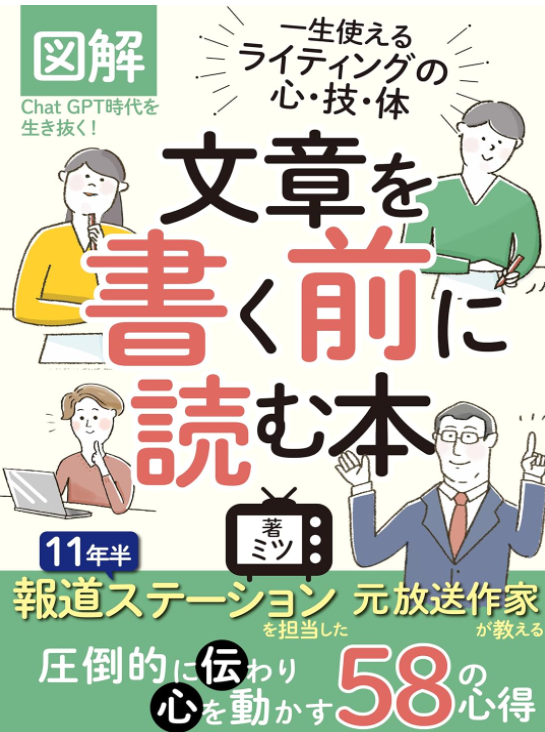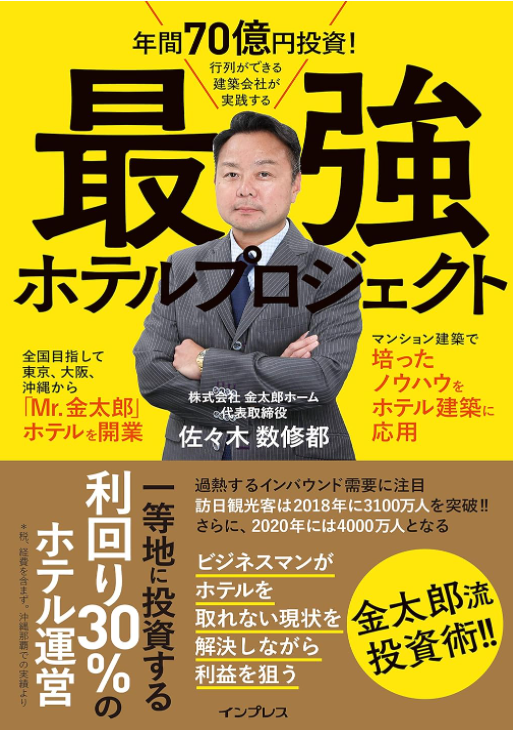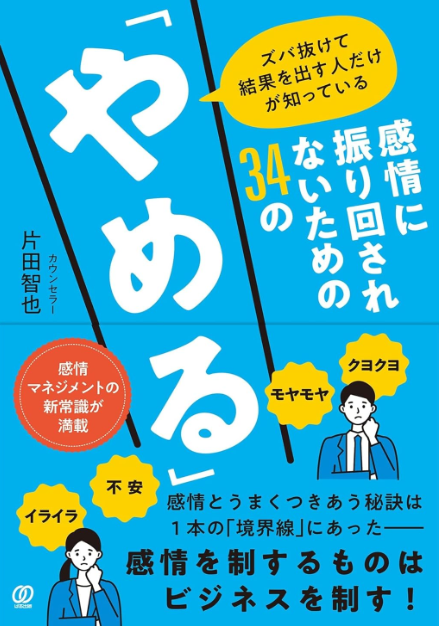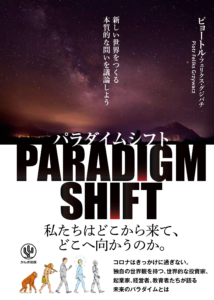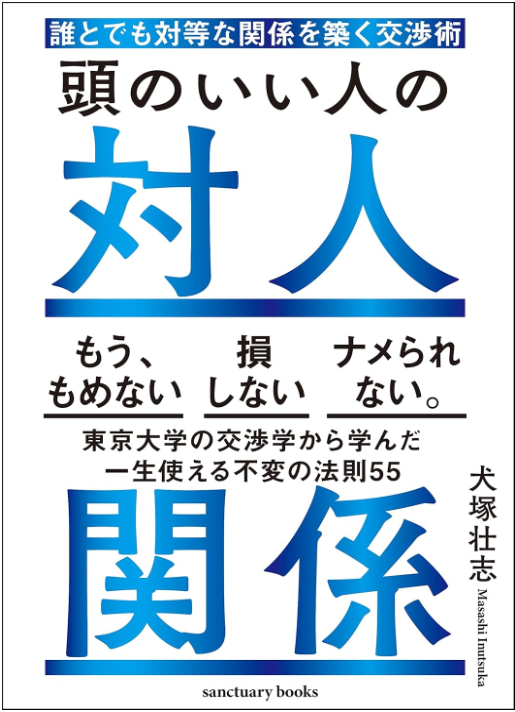【ファシリテーションの教科書 組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップ】
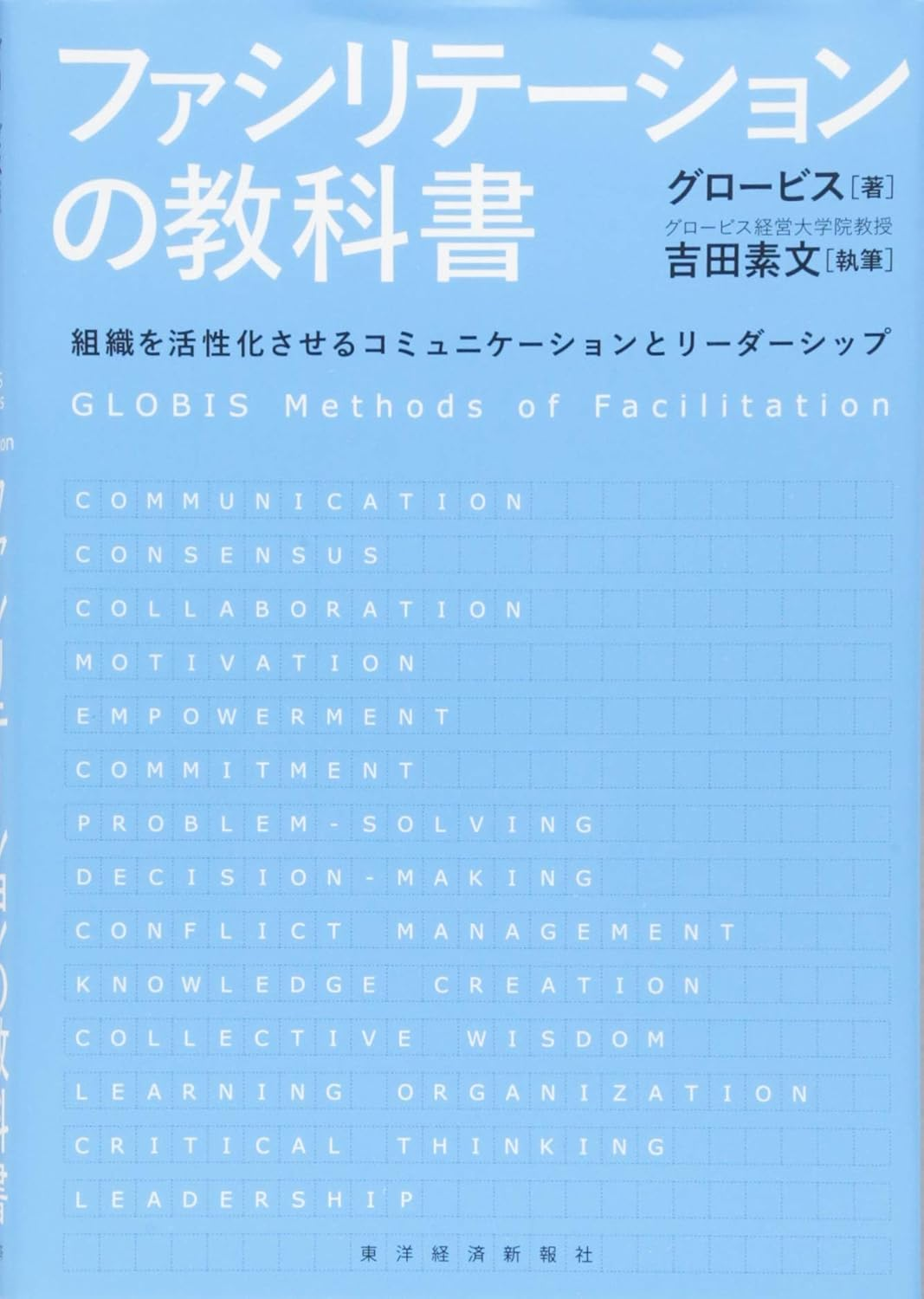
インフォメーション
| 題名 | ファシリテーションの教科書 組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップ |
| 著者 | グロービス 【著】 吉田 素文 【執筆】 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 出版日 | 2014年10月 |
| 価格 | 2,640円(税込) |
会議を円滑に進め、最大限の成果を上げるマネジメントスキルの腕を磨くための考え方・方法論を解説します。
◆知恵と意欲を最大限に引き出す技術
これからの組織で求められるのは、議論の場で参加者の知恵と意欲を最大限に引き出せる「ファシリテーター型リーダー」です。この、変革の時代をリードする理想のファシリテーターになるためのコミュニケーション技術、それを支える思考について詳述したのが本書です。
◆優れたファシリテーターになるための2大要素を詳述
本書は、優れたファシリテーターになるための2大要素である「仕込み」「さばき」の方法を2部で構成されています。第Ⅰ部「仕込み─あるべき議論の姿
を設計する」では「仕込み」の基本的な考え方と流れを押さえ、具体的な実践のイメージのつかみ方を解説します。
第Ⅱ部「さばき─議論を活性化し、思考を導く」では「さばき」の基本動作(発言を引き出す、議論を方向づけ結論づけるなど)を解説。また議論の場で直面する「対立」や「感情」にどのように対応すべきかを詳述しています。
コミュニケーションスタイルを「伝え、説得し、動かす」から「引き出し、決めさせ、 自ら動くことを助ける、に転換する」など具体的な処方箋を示しつつリーダシップ発揮のためのノウハウを伝えます。
組織力を高めるための“ファシリテーション”が本格的に学べるリーダー必読の書です。
引用:東洋経済新報社
ポイント
- 「どうしたら『考える組織』をつくることができるのか?」この問いこそ、多くの日本企業・組織が直面する課題であると断言する。
- 執筆者はファシリテーションのスキルを次のように説明する。「メンバーや関係者の知恵とやる気を引き出し、深い納得に裏づけられた合意を実現する強力な武器であり、同時に人の能力を育成するうえで肝となるコミュニケーションスキル 」
- ファシリテーションの究極の目的は、ファシリテーターのリードやコントロールがなくても、参加者自らが生産的な議論の場を想像し、実りある議論ができること。すなわち「考える組織」づくりなのだ。
サマリー
「考える組織」をつくるために
本書の著者は、1992年に設立された株式会社グロービス。
執筆者は、グロービス経営大学院教授である吉田氏である。
執筆者は、本書の冒頭に綴っている。
「どうしたら『考える組織』をつくることができるのか?」
この問いこそ、多くの日本企業・組織が直面する課題であると断言する。
多くの経営者は「自分で考えない指示待ち社員が多い」と嘆く一方、社員は「上が何を考えているかわからない」等と不満を募らせるというような断絶は、多くの組織で起こっている。
執筆者は、「考える組織」を次のように定義する。
「トップから現場最前線のメンバーまで、組織の1人ひとりがそれぞれの持ち場で何を解決すべきか、なぜそうなっているのか、どうすべきかを自ら考え行動すること。
さらに1人ひとりが自らの考えを積極的に発言し、知恵を出し合い、組織として最適な結論を素早く導く。
立場や利害の違いを越えて相互理解を図り、合意を形成し、納得のうえで一気呵成に動く。
このように強い個が掛け算のように力を増幅させながら協働する組織が『考える組織』です。」
そして、そのために不可欠なのが「議論の場を活性化し、議論の質を上げる」ことだと伝える。
では、どうしたら議論の場を活性化したり、議論そのものの質を上げることができるのだろうか。
そこで、必要なのが、メンバーが考えるべき重要な「問い」を提示し、1人ひとりの思考投入量を最大化し、知恵と意欲を引き出すことができる「ファシリテーター型リーダー」だというのだ。
本書は、これからの組織で求められる「ファシリテーター型リーダー」のコミュニケーションの技術、それを支える思考、さらに持つべき基本姿勢について記された一書である。
リーダーシップを具現化するファシリテーション
ビジネスパーソンにとって、「リーダーシップ」は、身につけていくべきスキルだと捉えている人は多いだろう。
一方「ファシリテーション」を自分が身につけるべきスキルと捉えている人は少ない。