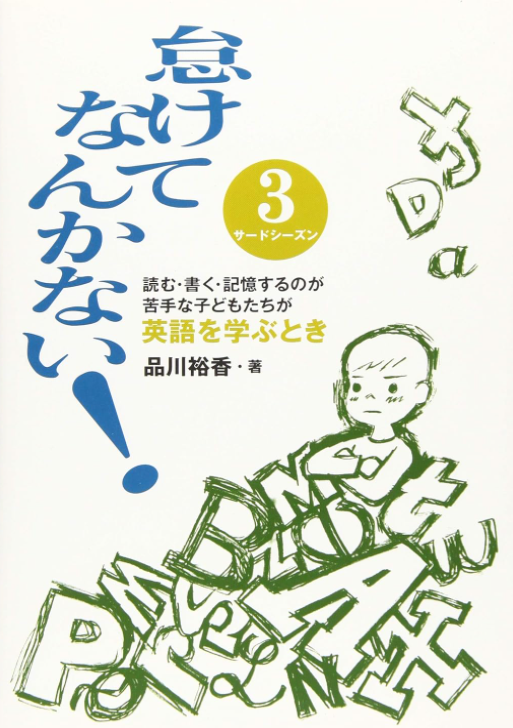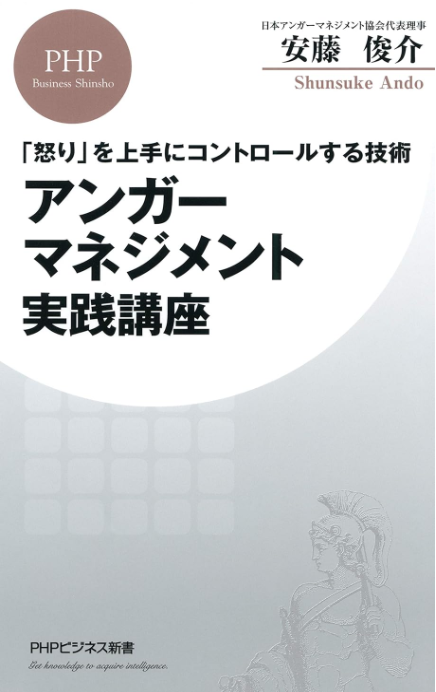【うらやましい孤独死】

インフォメーション
| 題名 | うらやましい孤独死 |
| 著者 | 森田 洋之 |
| 出版社 | 発行:三五館シンシャ 発売:フォレスト出版 |
| 出版日 | 2021年3月 |
| 価格 | 1,430円(税込) |
ボケても、家族がいなくても、「理想の死」は迎えられる
コロナ禍の時代にこそ考えたい、「理想の死」の見つけ方
「万一、何かあったら心配」「1日でも長生きしてほしい」……本人に良かれと思って誰もがとる行動が、じつは高齢者を孤独に追いやっている。
「好きなものを食べたい」「自由に外出したい」「死ぬ前にもう一度、自宅に帰りたい」、そんな人間として当たり前の希望を、願っても仕方ないと口に出すこともできない。私はそうした高齢者の方々をたくさん見てきた。
どんなに安全を求めても、安心を願っても、人間は必ず死ぬ。いま本当に求められているのは中途半端な“安全・安心”ではなく、その“安全・安心”の呪縛から高齢者の生活を解放することなのだ。「うらやましい孤独死」は、そのもっともわかりやすい例だろう。
引用:フォレスト出版
ポイント
- 著者は、本書の趣旨を次のように伝える。「それまでの人生が孤独ではなく、いきいきとした人間の交流がある中での死であれば、たとえ最期の瞬間がいわゆる孤独死であったとしても、それはうらやましいとも言えるのではないか?」
- 孤独死の問題の本質は、死そのものではなく、高齢者がそれまで孤独に生活していたことではないだろうか。
- 著者は、孤独死を回避しようとするがゆえに、独居高齢者を地域から引き剥がし、施設や病院へ送り込むことは、じつは孤独を生じさせる連鎖になることを指摘する。
サマリー
人間がかかるもっとも重い病気
「うらやましい孤独死」というタイトルから、孤独を美化するような内容を想像する人も多いかもしれないが、本書のテーマはそれとは異なる。
著者は、本書の趣旨を次のように伝える。
「それまでの人生が孤独ではなく、いきいきとした人間の交流がある中での死であれば、たとえ最期の瞬間がいわゆる孤独死であったとしても、それはうらやましいとも言えるのではないか?」
さらに、孤独死を過度に恐れるあまり独居高齢者が容易に施設に収容されている風潮にも警鐘を鳴らす。
著者は言い切る。
「人間がかかるもっとも重い病気は『孤独』である」
いくつもの科学的調査で、「孤独」は確実に健康を害することが証明されているという。
たしかに、高齢の家族の独居には多くの心配がある。
持病があったり、認知症などの症状があれば、なおさら「1人にはしておけない」と思うのは当然だ。
しかし、著者は、本人に良かれと思って誰もがとる行動が、じつは高齢者を孤独に追いやっていると厳しく指摘する。
著者は医師として、次のような高齢者を山ほど見てきたからだ。
「好きなものを食べたい」「自由に外出したい」「死ぬ前にもう一度自宅に帰りたい」、そんな人間として当たり前の希望を、願っても仕方がないと口に出すこともできない。
だからこそ、安全・安心の呪縛から高齢者の生活を解放すべきだと主張しているのだ。
本書には「うらやましい孤独死」ともいえる事例と、その理論的背景が集められている。
「ほんとうにうらやましいよ」
著者が「うらやましい孤独死」という言葉をはじめて耳にしたのは、北海道・夕張の診療所で医師をしていたときだ。
ある高齢女性が、独居の実姉が自宅のソファーで横になって亡くなっているのを発見した。
発見時には死後数日経っていたようで、世間一般でいわれる「孤独死」の状態だった。
しかし、その高齢の女性は著者に言った。
「本当にうらやましいよ。コロッと逝けたんだもの。あの歳までずっと元気に畑もやっててね。夕張のみんなに囲まれてさ。…都会に行ってアパートだの、施設だのに入りなさいって言われてもね。夕張で最期までみんなと元気にしててコロッと逝けたらいいよね。本当にうらやましい…」
著者は、それまで抱いていた孤独死のイメージとかけ離れた「うらやましい」という言葉に驚愕した。
痛ましいはずの孤独死を「うらやましい」というのだろうかと疑問に思ったのだ。
この問いに対して、著者は『破綻からの奇蹟~いま夕張市民から学ぶこと』(南日本ヘルスリサーチラボ)で次のような趣旨のことを記している。
孤独死の問題の本質は、死そのものではなく、高齢者がそれまで孤独に生活していたことではないだろうか。
夕張の例は死に至るまでの生活が孤独ではなかったのだ。
誰もが迎える死に至るまでの生活が、地域の絆という人間関係の中でのいきいきとしたものであれば、それはある意味人間としての本来の姿であり、それこそ「うらやましい」と言えるのかもしれない。
日本の病院で起こる「バカげたこと」
日本の病院は、世界一多い病床数を誇るがゆえに、ふだんから空床になりがちだ。
著者は、自院の収益確保のために患者を集める「集患」が当然のように行われていることを目にしてきた。
そして、このバカげたことである「集患」の対象となるのが高齢者であり、特に、病院グループ内の高齢者住宅や介護施設に入所している高齢者は、常に「入院予備軍」として確保されているというのだ。
個々の医師にそのような意識がない場合でも、多額の借金を抱えて病院を建てた経営側にしてみれば、借金を滞りなく返済するためには、常に「集患」し、「満床」を維持することが最大の命題となる。
このように努力して、満床を維持していかなければ、日本の病院は経営が維持できないシステムであるという驚くべき事実を伝える。
著者は、日本の医療の大部分が「高齢者ビジネス」になっていることを指摘し、医療の現場で接する高齢者の多くに笑顔がないことに心を痛めている。
日本の医療現場の複雑な現実や矛盾に、なんとか一石を投じるためにも本書を著したのだ。