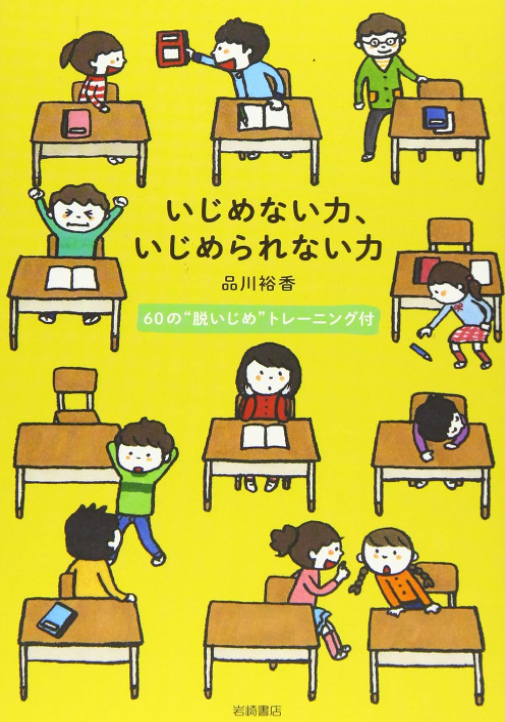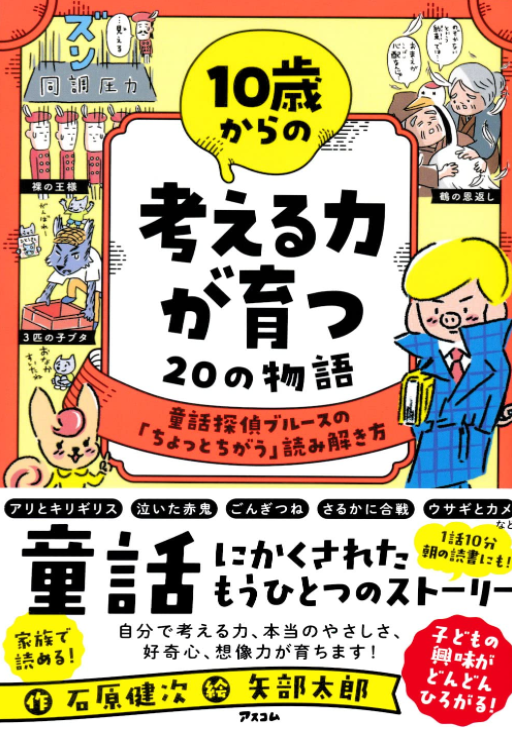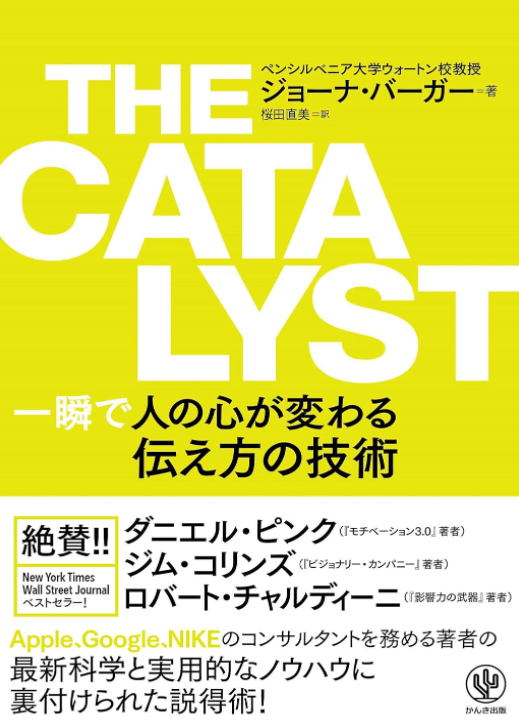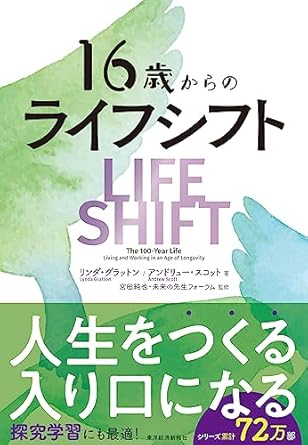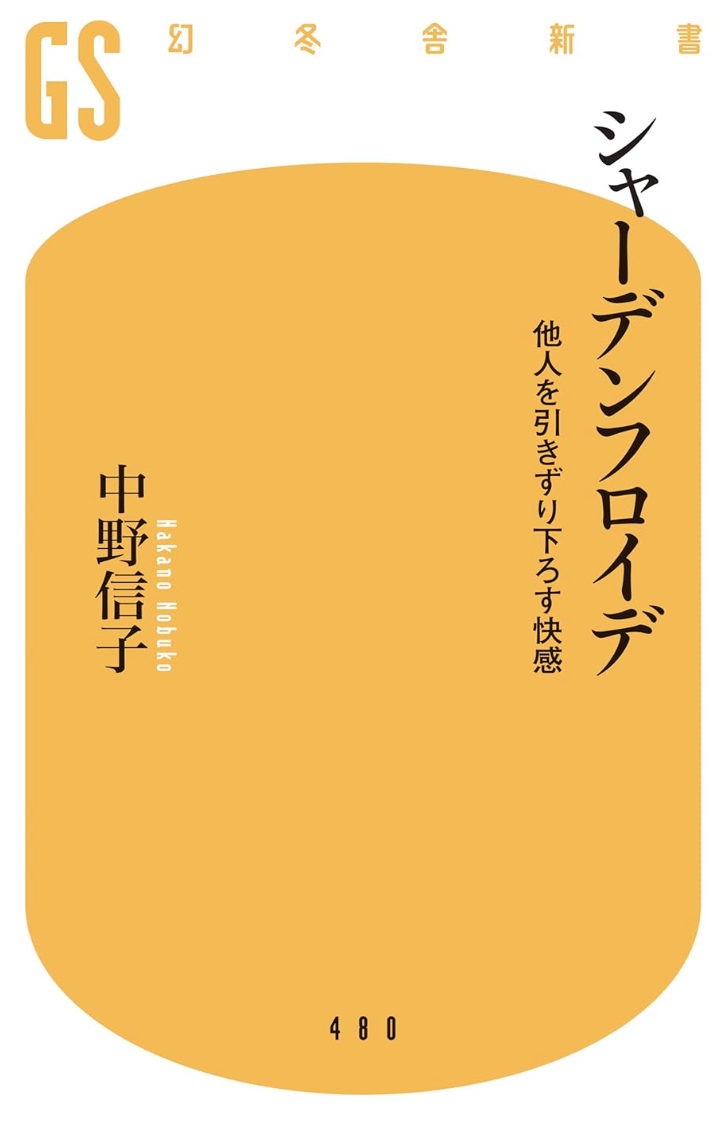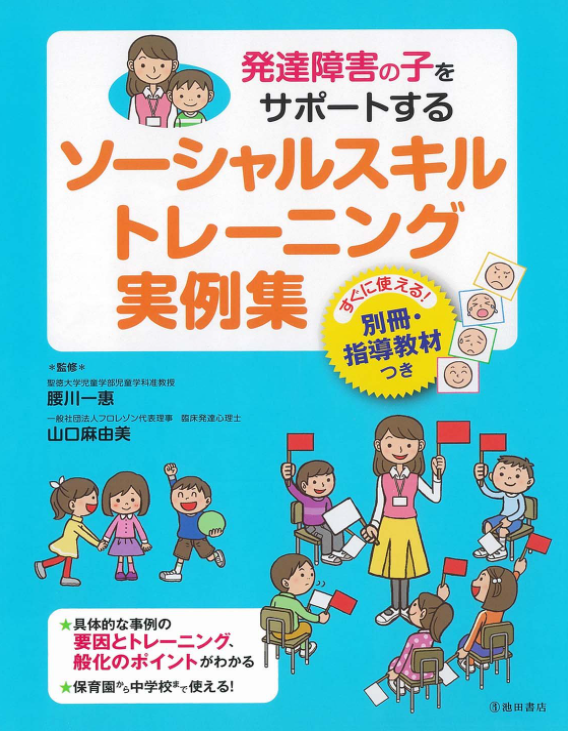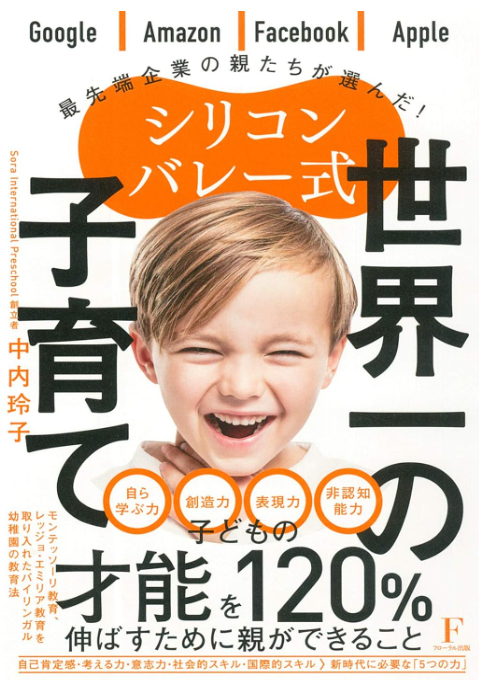【ひとりっ子の育て方】
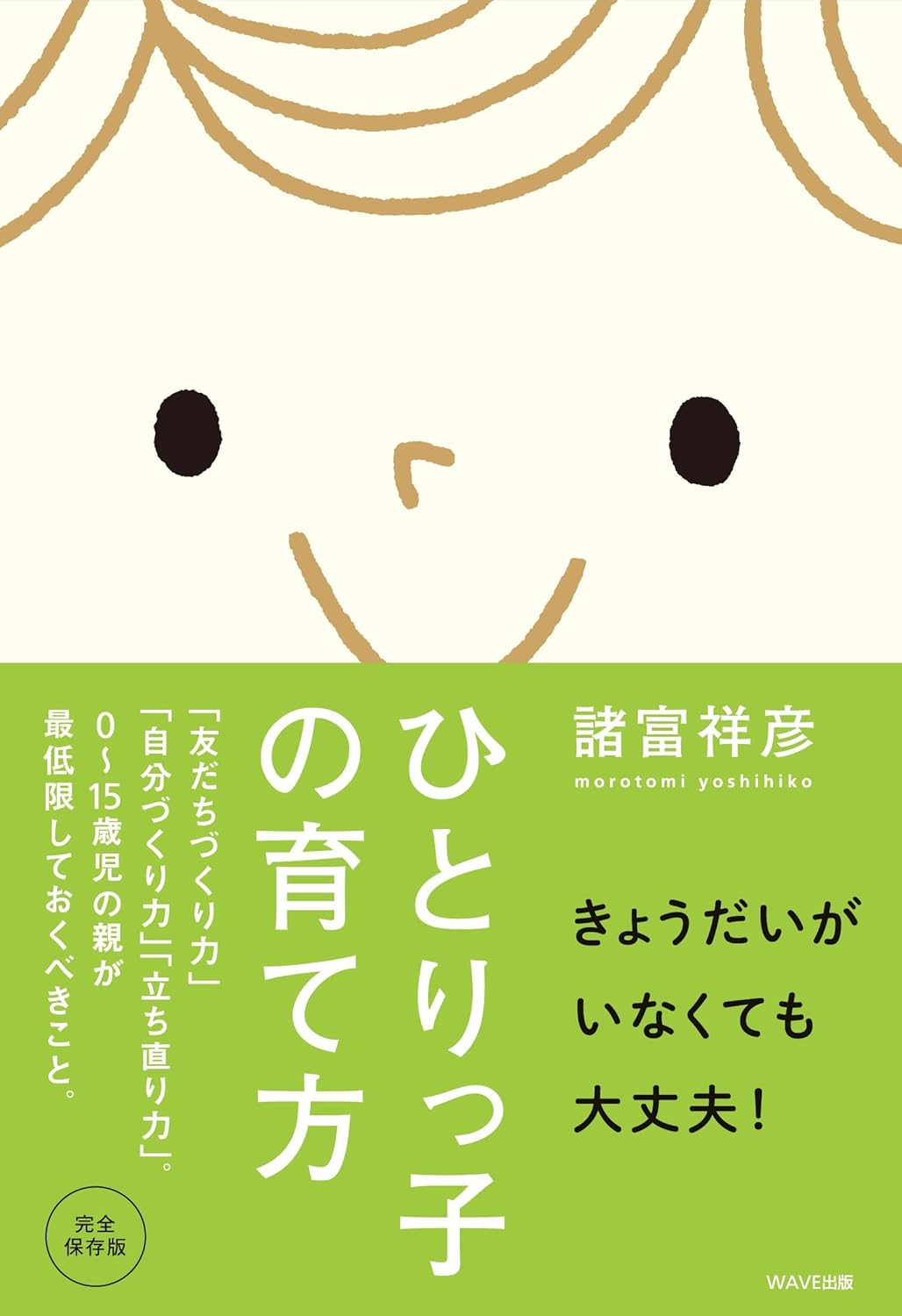
インフォメーション
| 題名 | ひとりっ子の育て方 |
| 著者 | 諸富 祥彦 |
| 出版社 | WAVE出版 |
| 出版日 | 2013年10月 |
| 価格 | 1,430円(税込) |
きょうだいがいなくても大丈夫!
乳幼児+小学校時代の親の態度が将来につながる!
親の「不安と願望」にきっちり答える本
●打たれ弱いところがある
●競争意識が低すぎる
●社会性が身につくかどうか心配
●大人と接することが多く、子ども社会で浮かないか
●兄弟を作ってあげられない罪悪感を抱えている
●親子密着度が高いので、思春期うまく子離れ親離れできるか不安・・・・
ひとりっ子はメリットがいっぱい!
・兄弟間の葛藤(シブリング・ライバリティ)がなく、変な劣等感を感じず育つ
・穏やかで優しい子が多い
・「一人時間=孤独」が充実していることの特典
・ワガママというよりマイペース
・「親のブレーキ」のかけ方を学べば関係良好
引用:Amazon
ポイント
- 本書は、ひとりっ子であることのマイナス点を補い、ひとりっ子であるがゆえに得られるプラスの点を伸ばしていくことができる子育ての仕方について書かれている。
- ひとりっ子の最大のメリットは、「親の愛情を独占できること」だと伝える。子どもはみんな母の愛をひとり占めしたいと思っているので、愛情を独占できるひとりっ子は、心が安定しやすいというのだ。
- 著者は、ひとりっ子の親に「やりすぎない」「頑張りすぎない」「上手にブレーキをかけましょう」とアドバイスしている。なぜなら、ひとりっ子は親からの惜しみない愛情を注いでもらえると同時に、親からの期待や関心も一身に受けてしまうからだ。
サマリー
ひとりっ子のネガティブイメージは根拠なし
著者は、30年近く子育てカウンセラーとして、多くの子育ての相談にのってきた。
また、明治大学の教授として、子育てや教育などに関わる心理学を教えている。
ひとりっ子の子育てをしている親には、きょうだいがいる子の子育てをしている親にはない、特有の悩みがあるという。
「やっぱり、きょうだいがいないと、さみしいですよね。うちの子に悪くて」
「ひとりっ子なので、ワガママにならないか心配です」
「兄弟がいないから、いつか私たち親が死んだら、その後孤独でつらい人生を歩むことになりますよね」
など、さまざまな心配をしている。
しかし、「ひとりっ子がワガママである」といった事実を実証した研究はなく、ひとりっ子のネガティブなイメージはまったく根拠がないものだと伝えている。
本書は、ひとりっ子であることのマイナス点を補い、ひとりっ子であるがゆえに得られるプラスの点を伸ばしていくことができる子育ての仕方について書かれている。
具体的には次の3つの力をもつ子どもに育てることだ。
①「友だちづくりの力」(仲間づくりの力)
②「自分づくりの力」(自分らしい人生を自分で切り開いていく力)
③「つらいことがあっても、立ち直る力」(困難に満ちた苦しいことがあっても、心折れてしまうことなく、そこから立ち直っていく心の強さ)
著者が長年子育てカウンセリングをする中で培った「子育ての知恵」がたくさん示されている。
ひとりっ子のメリット・デメリット
ひとりっ子の最大のメリットは、「親の愛情を独占できること」だと伝える。
子どもはみんな母の愛をひとり占めしたいと思っているので、愛情を独占できるひとりっ子は、心が安定しやすいというのだ。
著者がカウンセラーとして活動するなかで、気づいた「人生最大の不幸のリスク」がある。
それは、子どものころ、「ほかのきょうだいと比べて、私は両親から愛されていない」という思いを抱いているということだ。
ひとりっ子はこの最大のリスクを回避できるのだ。
そして、ネガティブにとらえられることの多い「ひとりで過ごす時間の多さ」については、実は、「クリエイティビティ」の育ちにつながるというメリットになると指摘する。
ひとりで過ごす時間は、思考や空想を自由にめぐらせ、内面の世界で豊かに遊んでいるので、「想像力や創造性が育っている」時間になるからだ。
一方、ひとりっ子に不足しがちな経験を補うこととして、早い時期から保育園に通うことをすすめている。
保育園は、0歳〜1歳という早い時期から、同年齢の子どもたちに加えて異年齢の子どもとも集団生活を送ることで「疑似きょうだい」ができる。
また、保育園だけでなくボーイスカウトやガールスカウト、夏休み中のキャンプなど、異年齢の子どもたちとふれあう機会を活用することもできると提案する。
人間関係の力は、基本的には他人とふれあうことでしか身につかないので、早い時期から子ども同士で関わる機会を意識的に増やすことが必要だと伝えているのだ。
ひとりっ子親のブレーキのかけ方
著者は、ひとりっ子の親に「やりすぎない」「頑張りすぎない」「上手にブレーキをかけましょう」とアドバイスしている。
なぜなら、ひとりっ子は親からの惜しみない愛情を注いでもらえると同時に、親からの期待や関心も一身に受けてしまうからだ。
具体的には、次の4つのブレーキを心がけてほしいと伝える。
①「しつけ」のやりすぎへのブレーキ
ひとりっ子を親が「厳しくしつけよう」としすぎると、「お母さんは私のことが好きじゃないんだ」「お母さんは私のことをダメだと思っているんだ」という自己否定的な気持ちばかり残ってしまう。
学校や社会で否応なく厳しい体験をするようになるので、むしろ、親の役割は家の外でつらい体験をする子どもの「心の基地」になり、何度でも受け入れて支えることのほうが大切なのだ。
②「習い事」にハマりすぎることへのブレーキ
3つ以上の塾や習い事に通っていたり、子どもがやめたいと言っても、簡単にはやめさせないという関わりにはブレーキが必要だ。
大切なのは、子どもが「本当に勘弁してくれ」というサインを出しているときは、無理に続けさせてはいけない。
一方、子どもが「やってみたい」という習い事をさせる時は、「すぐに辞めず1ヶ月は続ける」とか「きちんと家で練習する」という「約束事」を決めておくことが必要だ。
③「友達関係」に口出しすることへのブレーキ
親自身が、遊ぶ友だちや、誕生日会に呼ぶお友だちを勝手に決めるのはNG。
大切なことは「友達づくりの機会はつくるけれど、口出ししすぎない」ことだ。
④「勉強」させようとしすぎてしまうことへのブレーキ
子どもの成績について「喜びすぎない」「落ち込みすぎない」こと、特に「ほかの子と比較してほめたり叱ったりしないこと」が大切である。
この4つのブレーキを意識することが、ひとりっ子のマイナス点を補い、プラスの点を伸ばす工夫につながると教えている。