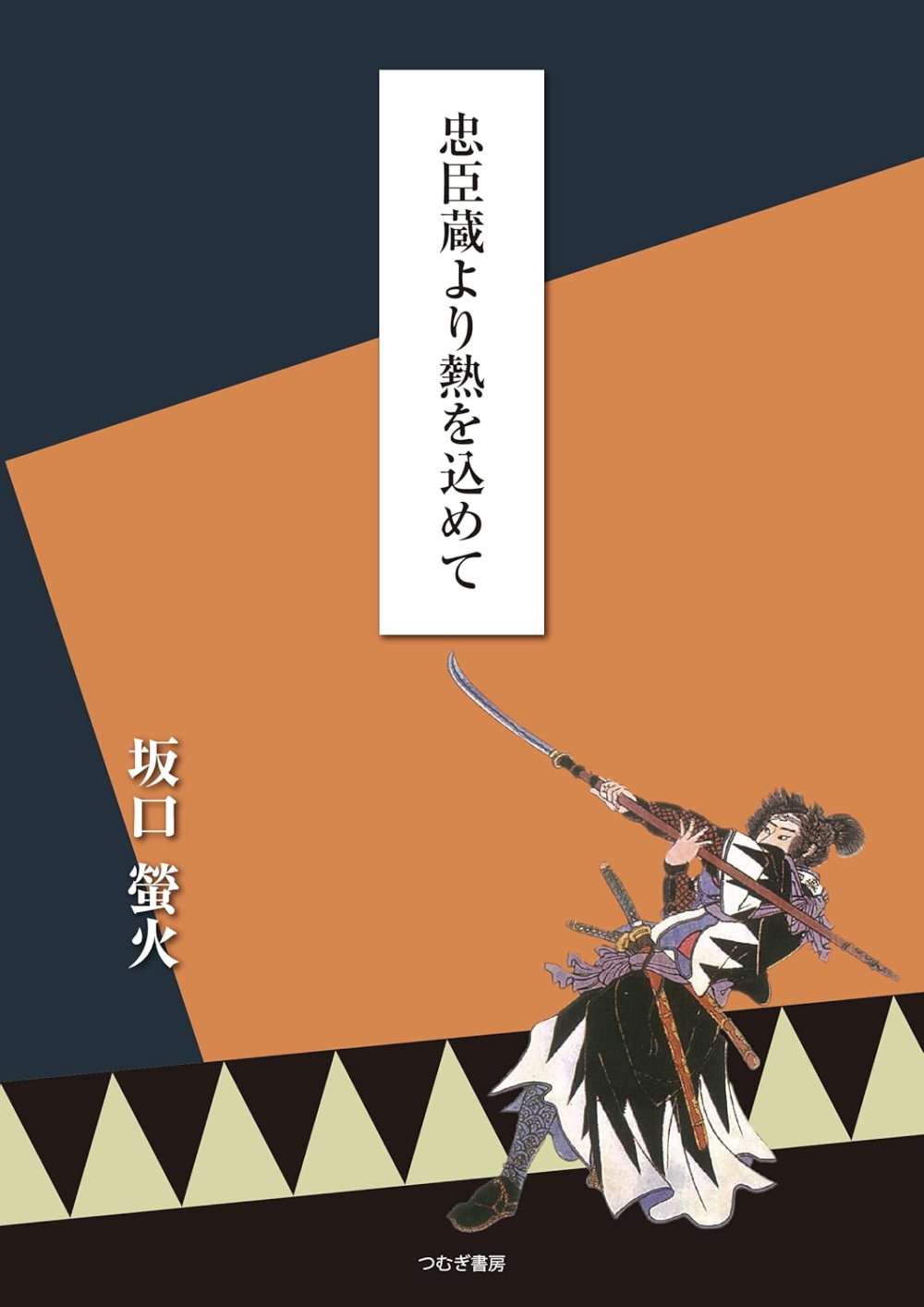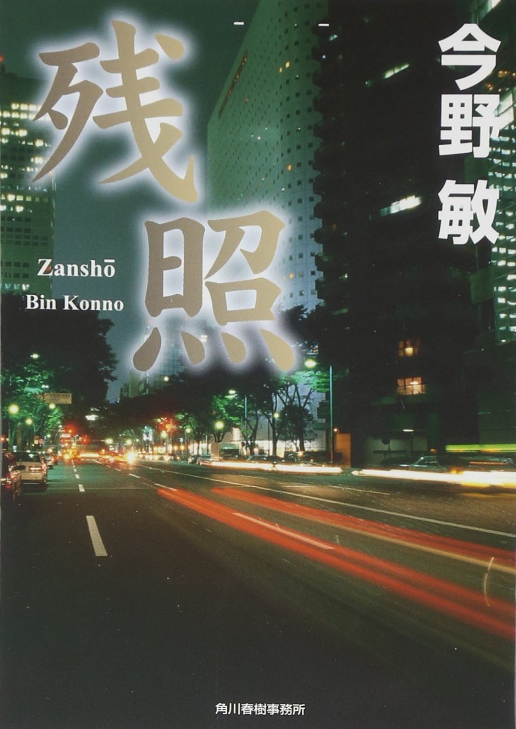【そして、バトンは渡された】

インフォメーション
| 題名 | そして、バトンは渡された |
| 著者 | 瀬尾まいこ |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 出版日 | 2018年2月22日 |
| 価格 | 1,400円(税込) |
登場人物
・優子
主人公
・森宮壮介
三人目の父
・田中梨花
二人目の母
・泉ヶ原茂雄
二人目の父
あらすじ
父が三人、母が二人
生まれた時、優子は水戸優子だった。
その後、田中優子となり、泉ヶ原優子を経て、現在は森宮優子。
優子には父が三人、母親が二人いる。
家族の形態は、十七年間で七回も変わった。
実の母親は、優子が三歳になる前に事故で亡くなった。
幼かった優子は、母の顔も覚えていない。
優子の家族は何度か変わり、父親や母親でいた人とも別れてきた。
けれど、亡くなっているのは実の母親だけだ。
一緒に暮らさなくなった人と、会うことはない。
でも、どこかにいてくれるのと、どこにもいないのとでは、まるで違う。
血が繋がっていようがいまいが、自分の家族を、そばにいてくれた人を、亡くすのは何より悲しいことだ。
二人目の母
優子が小学校二年生の夏休み。
最初に現れたのは、梨花だった。
整った顔立ちというわけではないけれど、くりっとした目に大きな口は華やかで、化粧や髪型をもっとも似合うように施している、自分を見せるのがうまい人だった。
優子はすぐに梨花が好きになった。
三年生になる前の春休みに、梨花は優子の母親になった。
毎朝学校に行く前には髪の毛をかわいく結び、友達が遊びに来るときはたくさんお菓子を用意してくれた。
優子は梨花が自慢でしかたがなかった。
梨花と暮らし始めてから、いいことばかりだった。
小学校五年生になる前の春休み。
梨花と父はあまりうまくいっていなかった。
夜に二人が言い合いになってる声が聞こえることもあった。
父が転勤でブラジルへ行くことになったのだ。
しかし、梨花は日本に残ると言う。
優子に与えられた選択肢は二つ。
父とブラジルへ行って向こうで暮らすか、梨花と日本に残って今までと同じ暮らしをするか。
父と梨花は離婚する。
優子は、梨花と日本に残る決断をする。