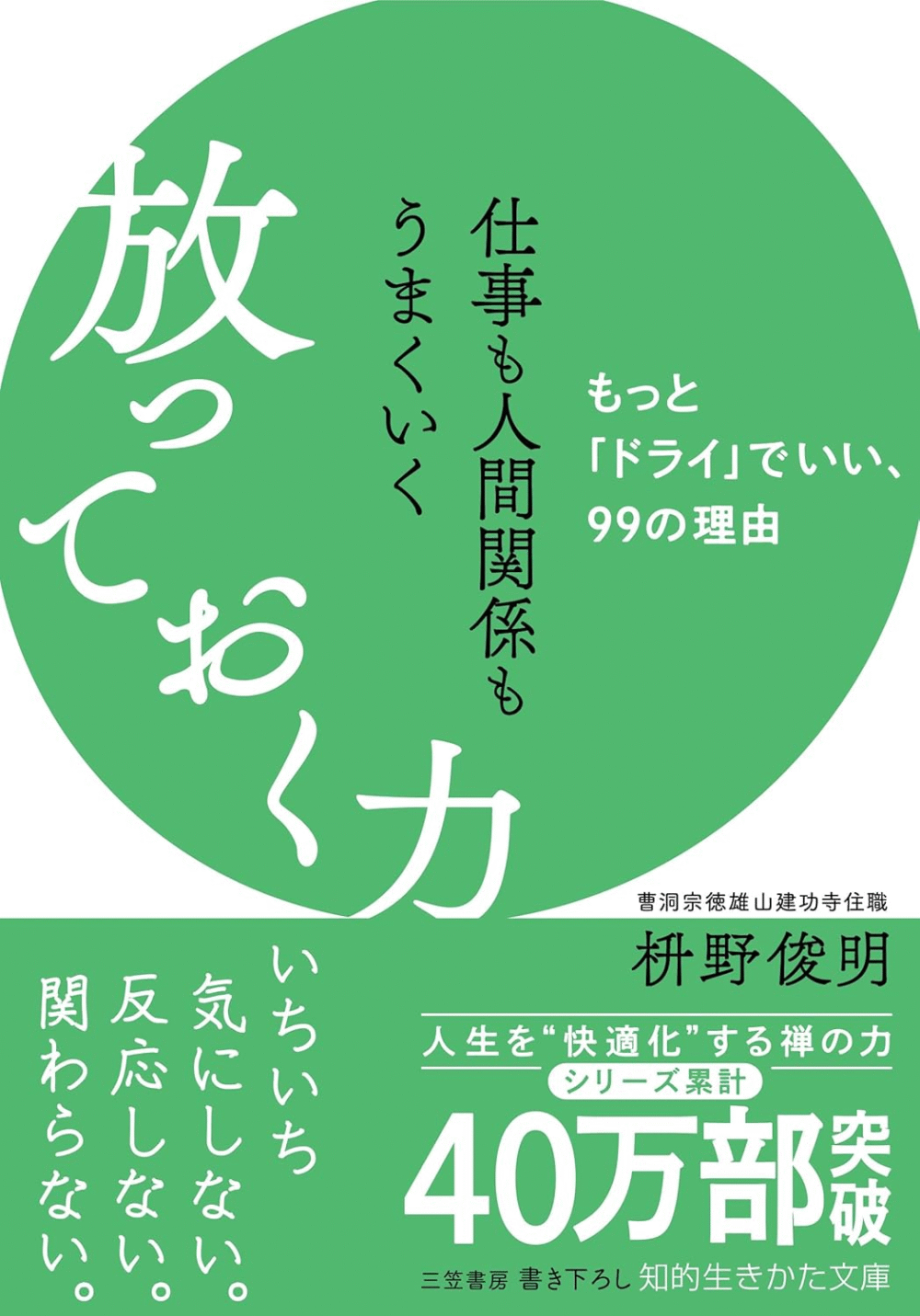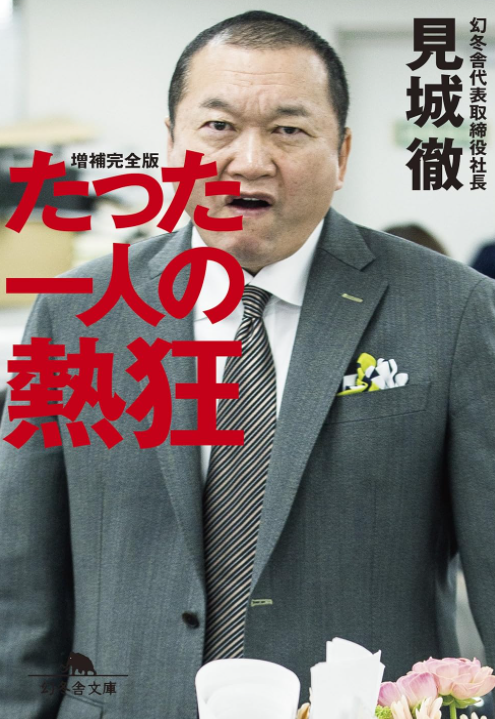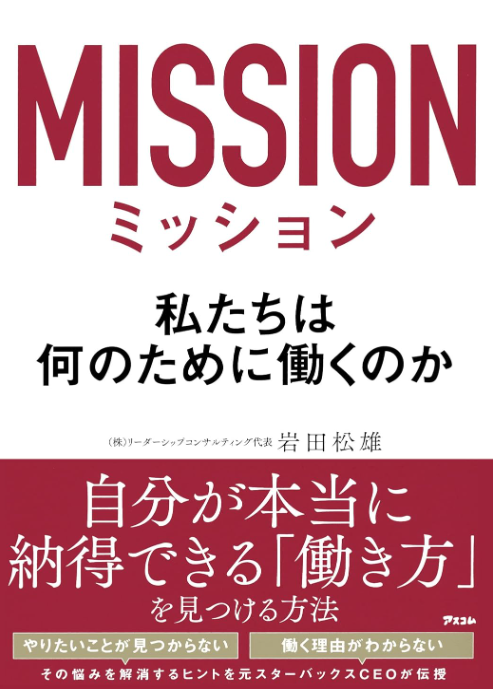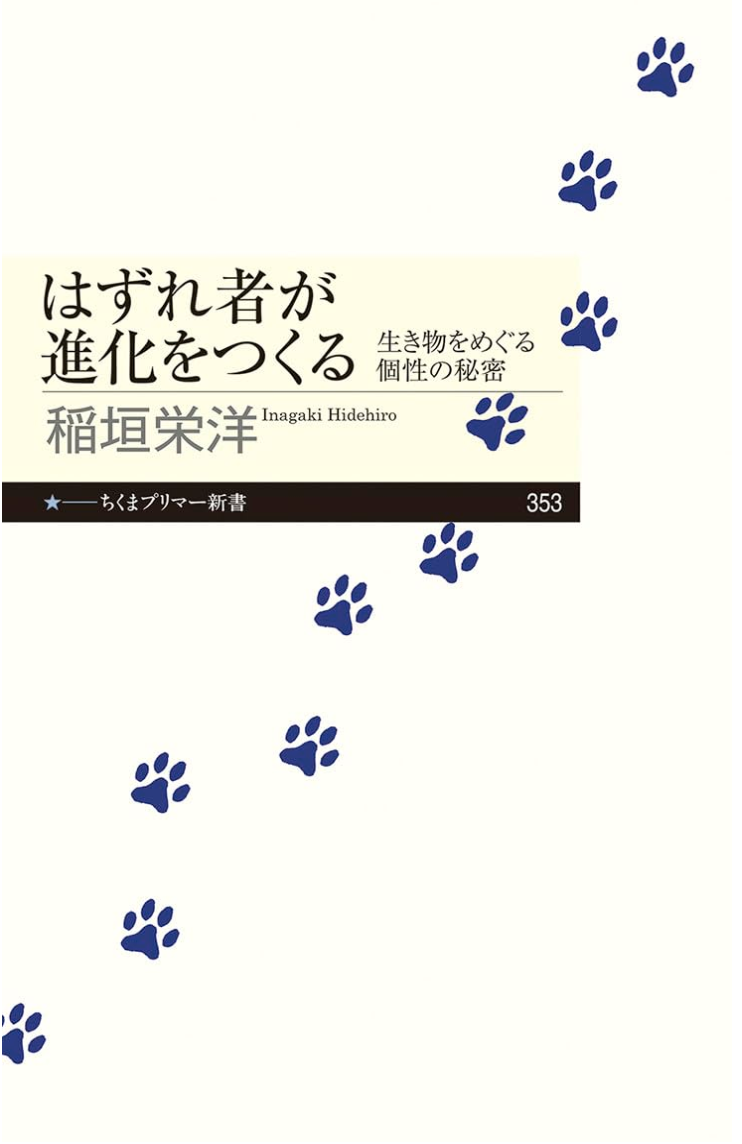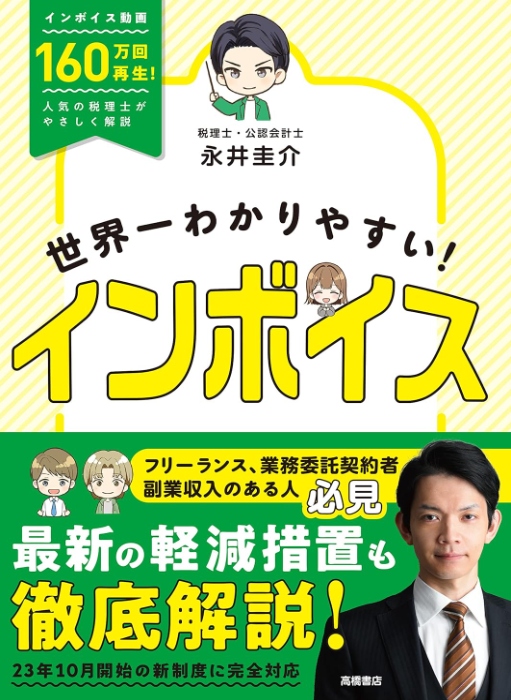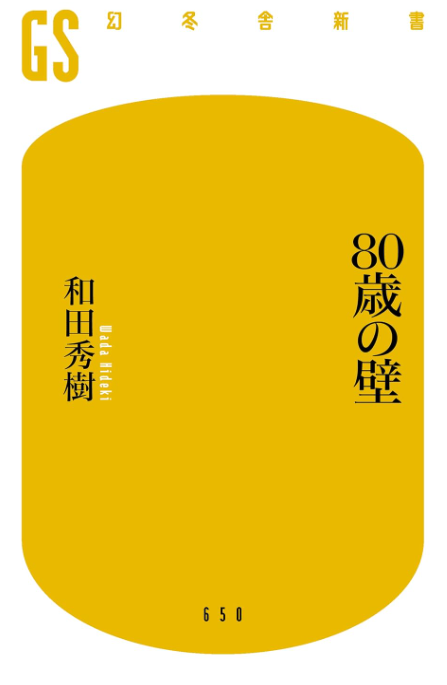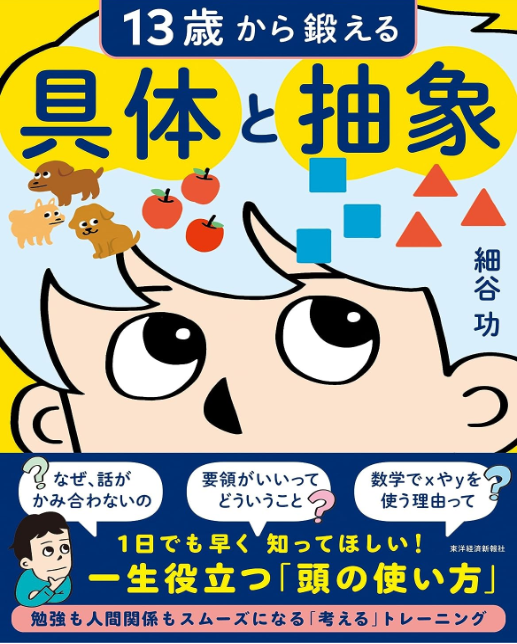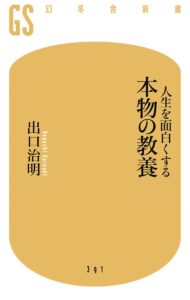【仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法】
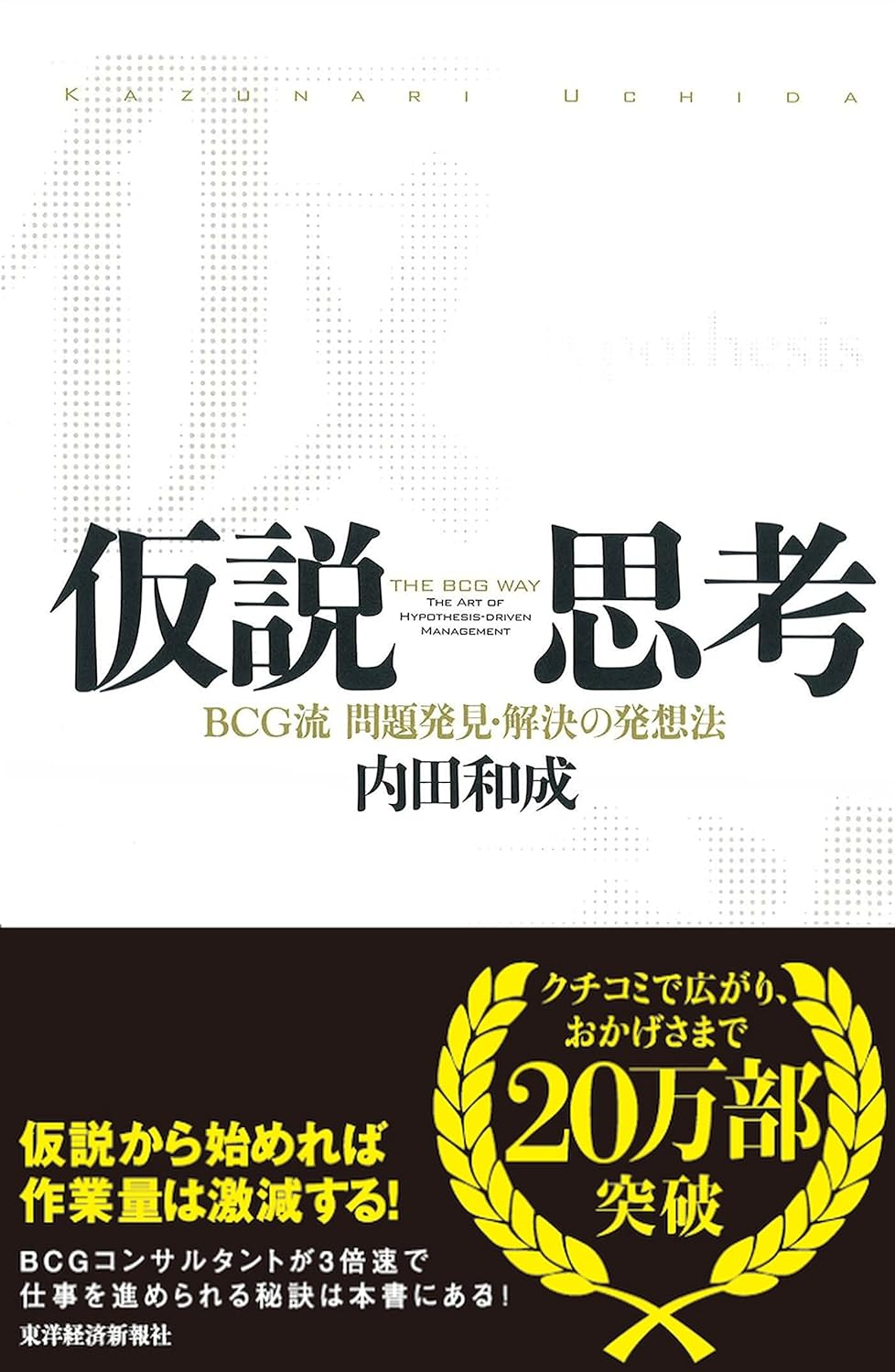
インフォメーション
| 題名 | 仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法 |
| 著者 | 内田和成 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 出版日 | 2006年3月 |
| 価格 | 1,760円(税込) |
仕事の速さ・出来栄えを決めるのは何か? それは「分析力ではなく、仮説である」と著者は説く。ボストン・コンサルティング・グループでの20年の経験から、コンサルタントの必須能力である「仮説思考」を解説。
引用:東洋経済新報社
ポイント
- 仮説思考とは情報が少ない段階から、常に問題の全体像や結論を考える思考スタイル、あるいは習慣とも言うべきもの。本書では、著者が20年間のコンサルティング経験の中で培ってきた「仮説思考」の要諦が解説されている。
- 仕事の速い人は限られた情報をベースに、人より早くかつ正確に問題点を発見でき、かつ解決策につなげることのできる思考法を身につけていると著者はみている。一方で、仕事が遅い人の特徴は、とにかくたくさんの情報を集めたがることだと指摘する。
- 仮説思考を身につけることにより、迅速かつ正確に課題の本質を解明し、解決策を導き出すことができるようになるのだ。
サマリー
BCGで学んだ仮説思考
著者は、ボストンコンサルティンググループ(BCG)の新人時代には「枝葉の男」と称されていたという。
新人コンサルタント時代の著者は、手当たり次第に情報収集を行ない、人一倍に分析作業を行なうものの、有益な分析結果が少ないという状況だった。
さらに、問題の本質に到達するのに、膨大な時間を要し、時間切れになってしまうこともあったようだ。
つまり、コンサルタントとしてのもっとも大事な「幹」ともいうべき、問題解決の全体像が描けなかったというのだ。
そのような著者が変わるきっかけとなったのが、先輩コンサルタントから学んだ「仮説思考」だ。
仮説とは、情報収集の途中や分析作業以前にもつ「仮の答え」のことである。
著者は、仮説思考を以下のように表現している。
仮説思考とは情報が少ない段階から、常に問題の全体像や結論を考える思考スタイル、あるいは習慣とも言うべきもの。
著者は、コンサルタントの仕事の中で「仮説思考」を実践すると、仕事がよりスムーズに、そして正確に進んだ。
もちろん、最初からうまくいくわけではない。
著者は、「仮説思考は実践していくことで身についていくもの」と断言する。
そして、失敗と試行錯誤を積み重ねながら、仮説思考は進化していくと伝えている。
本書では、著者が20年間のコンサルティング経験の中で培ってきた「仮説思考」の要諦が解説されている。
早い段階で仮説をもてばうまくいく
ビジネスパーソンは日々の仕事の中で、問題解決を迫られている。
著者は、多くのビジネスパーソンは、できるだけ多くの情報を集めてから物事の本質を見極め、さらにその問題に答えをだすために、必要な情報を集めていると指摘する。
しかし、その仕事の方法だと「時間切れ」になったり、時間に追われるあまり最後の意思決定を勢いでやらざるを得なくなったりすることにつながる。
つまり、あらゆる情報を網羅的に調べてから答えを出す方法は、時間的にも資源的にも無理があるということだ。
そこで著者が勧めるのが、早い段階で仮説を持つことだ。