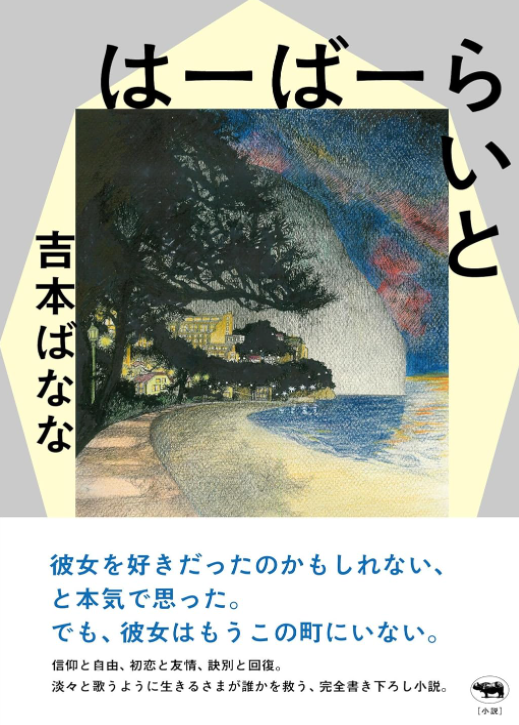【ライオンのおやつ】

インフォメーション
| 題名 | ライオンのおやつ |
| 著者 | 小川糸 |
| 出版社 | ポプラ社 |
| 出版日 | 2019年10月 |
| 価格 | 1,650円(税込) |
登場人物
・海野雫
三十三才。癌ステージⅣ。
・マドンナ
ライオンの家の代表。
・狩野姉妹
ライオンの家の調理担当。姉シマ、妹マイ。
・六花
ライオンの家で飼われている犬。
・田陽地(タヒチ)
葡萄を育てて、ワイン作りをしている。
・海野梢
雫の妹。
あらすじ
ようこそ、ライオンの家へ
担当医から、自分の人生に残された時間というものを告げられた時、雫はなんだか頭がぼんやりして、他人事のようで、うまく飲み込めなかった。
決して治ることのない段階ではあるが、雫はがんばってあらがったりもしたけれど、強い勢力には勝てなかった。
住んでいたアパートを解約し、ライオンの家で人生最後の日々を過ごす。
瀬戸内海にあるレモン島にライオンの家はある。
空気がおいしい。これまではずっと、空気を吸うこと自体が恐ろしかった。
何か悪いウィルスが入ったら、抵抗力のない雫はすぐに深刻な状況におちいってしまう。
だから、深呼吸もろくにできなかった。レモン島でなら、安心して空気を吸える。
ライオンの家に到着し、マドンナが部屋まで案内する。
ホスピスというと、もっと病院っぽいか、もっと庶民的かどちらかを想像していた雫は、拍子抜けした。
まるで隠れ家ホテルにいるような、優雅な気分にさせてくれる空間だった。
次にマドンナが案内してくれたのは、“おやつの間”だった。
毎週、日曜日午後三時から、ここでお茶会が開かれる。
ゲストのみんなに、もう一度食べたい思い出のおやつをリクエストすることができると言う。
朝ごはん
ライオンの家では、三百六十五日、毎朝違うお粥でゲストをお迎えしている。
病院で出されるお粥は、雫は食べられなかった。
冷めていたし、ドロっとして気持ち悪かった。
でも、ライオンの家のお粥はふわふわと湯気が踊っている。
おいしい水のように、儚くて清らかな味だった。
食べれば食べるほど、おなかの底がぬくぬくして、乾いた大地に水が染み込む。
ライオンの家での基本的な暮らしは、食べることと寝ることだけだ。
最初は単調すぎて退屈してしまうのではないかと恐れていたけど、杞憂だった。
彩りがあり、驚きがあり、少しも飽きない。
ここに来て、食べ物のおいしさに雫は開眼した。
魂に直接響くような味だった。
六花とタヒチ
マドンナの提案で、雫と六花は散歩へ行く。
ずっと犬を飼いたいと思っていた雫は、六花と散歩している、
ただそれだけで幸せだった。
病気になって良かったとは、まだ心から言えない。
でもライオンの家に来て、こんなにもたくさんのギフトを恵んでくれたのは事実だ。
六花が畑の中にいたタヒチのもとへ駆けていく。葡萄畑だ。
はるか下に、青い海が輝いていていい眺めだった。
ホスピスの人たちが飲むモルヒネワインを作りたいとマドンナが言い出し、いつの間にかプロジェクトが進み、気がついたらタヒチが島に呼ばれていたという。
三日後に、タヒチから島を案内させてほしいとドライブのお誘いがあった。
雫は、人生最後のデートか、と思った。
もうすぐ雫の人生は終わってしまうから、今更何か期待しているわけではない。
でもタヒチのような好青年とドライブできるなんてラッキーだと思った。
タヒチと六花とのドライブは、風が優しくて、光がまぶしくて、自分が生きていることを実感した。
タヒチと六花に感謝の気持ちを伝えたいのに、うまく言葉にできないからたくさん笑った。
ビーチへ行き、そこで雫はタヒチにお願いする。
「私が死んだらさ、ここに来て、空に向って手を振ってもらいたいの。その時は、六花も一緒に連れてきてほしいんだ。私も、がんばって手を振るように努力するから」
死を直面する
事前に送られてきたライオンの家の案内に、書かれていた。
ゲストが亡くなると、二十四時間、エントランスにろうそくが灯される。
タヒチとのドライブ後にライオンの家に戻ると、ろうそくが灯されていた。
美味しいコーヒーを淹れてくれたマスターの死だった。
雫は、お別れをしにマスターのもとへ行く。
マスターの両手は、お腹の上で美しい形に組まれている。
その手に雫の指を乗せた。
ひんやりとした温もりがあり、常温に戻る途中の保冷剤のようだった。
雫の心に、靄がかかるのを止められなかった。
遅かれ早かれマスターみたいに動かなくなる。
靄はどんどん濃くなり、存在感を増していった。
次の日、泣きながら朝ごはんを食べていると、シマが言った。
「せっかく生きているんだから、おいしいものを笑顔で食べなきゃ」
「生まれるのも死ぬのも、自分では決められないもの。だから、死ぬまで生きるしかないんだよ」
おやつの時間がやって来た。
配られたのはカヌレ。
マスターのリクエストだった。
ここでは、死が日々の営みの中に自然に溶け込んでいる。
だからと言って悲しくないわけではないんだなと、スタッフの表情を見て、雫は感じた。
涙だけが、悲しみを表す手段ではない。
状態の悪化
ライオンの家に来て、初めて雫は眠れなくなった。
マドンナの勧めで、セラピーを受けることになる。
痛みにはふたつあるのだと、マドンナは言う。
ひとつは、体の痛み。
もうひとつは心の痛み。
体の痛みと心の痛み、両方を取り除かなければ幸せな最期は訪れないと。
ホスピスは、体と心、両方の痛みを和らげるお手伝いをしてくれる場所だった。
体の痛みに関しては、モルヒネワインを飲むことでなんとか誤魔化していた。
でもだんだん、モルヒネワインだけでは効かなくなり、夜中に痛みで目が覚めて眠れなくなっていた。
夜間セデーションといって、夜寝ている間だけ睡眠薬を使って深く眠る。
すっきりと起きて、元気な午前中は好きなことをし、午後、音楽セラピーなどを受けて心身の痛みのお掃除をした。
死を受け入れるということ
死を受け入れるなんて、そう簡単にできることではなかった。
雫は、自らの死を受け入れたつもりになっていた。
でも、そうじゃなかった。
そう思うことの方が自分にとっては都合がいいから、受け入れようとしていたのだ。
でも、本当の本当のところでは、まだ死にたくない。
死を受け入れる、ということは、自分が死にたくない、という感情も含めて正直に認めることだ。