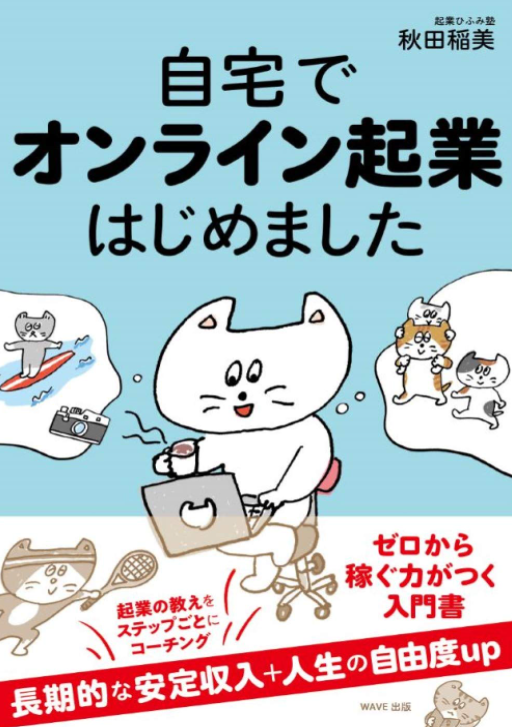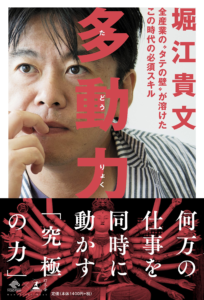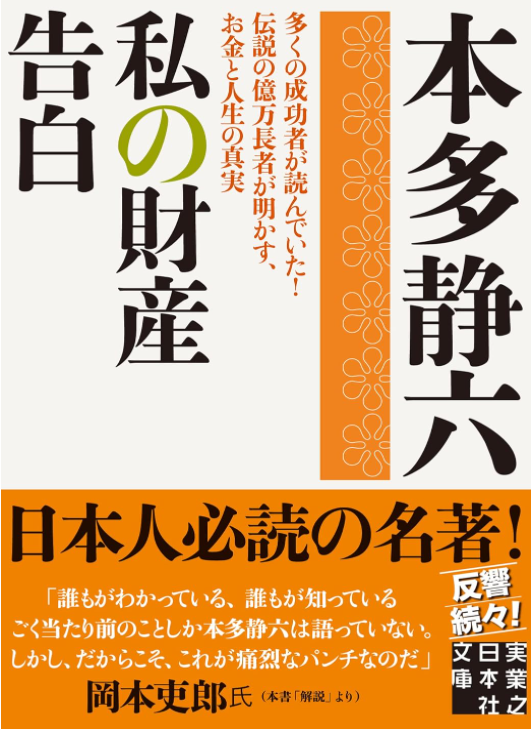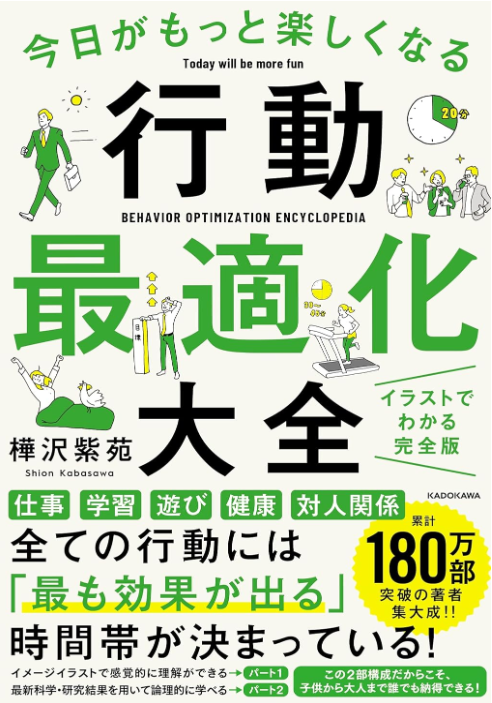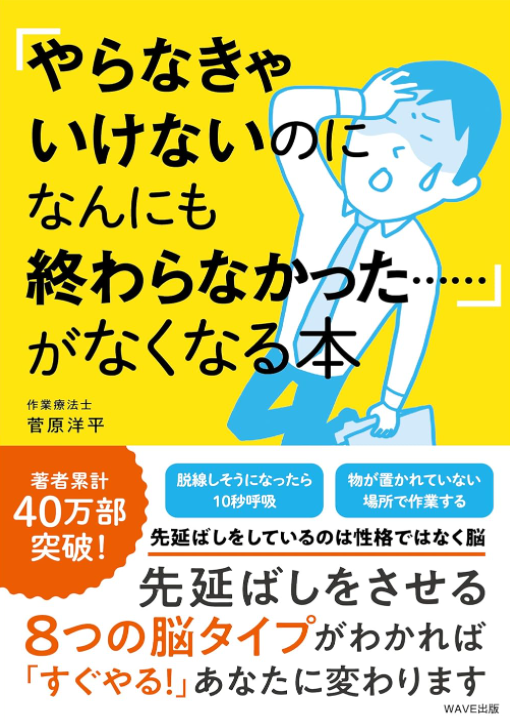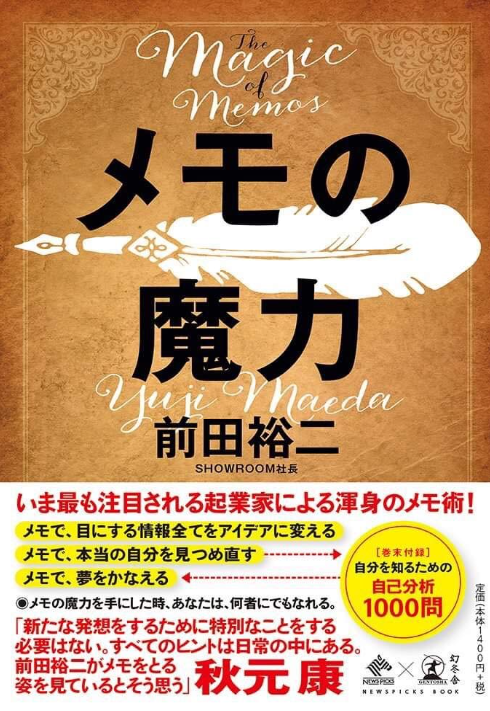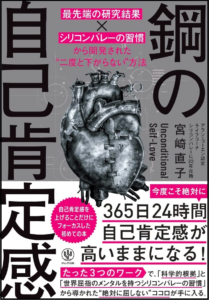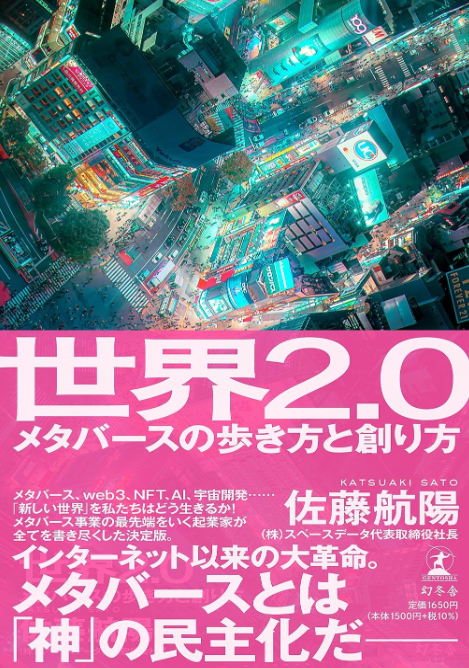【なぜ最近の若者は突然辞めるのか】
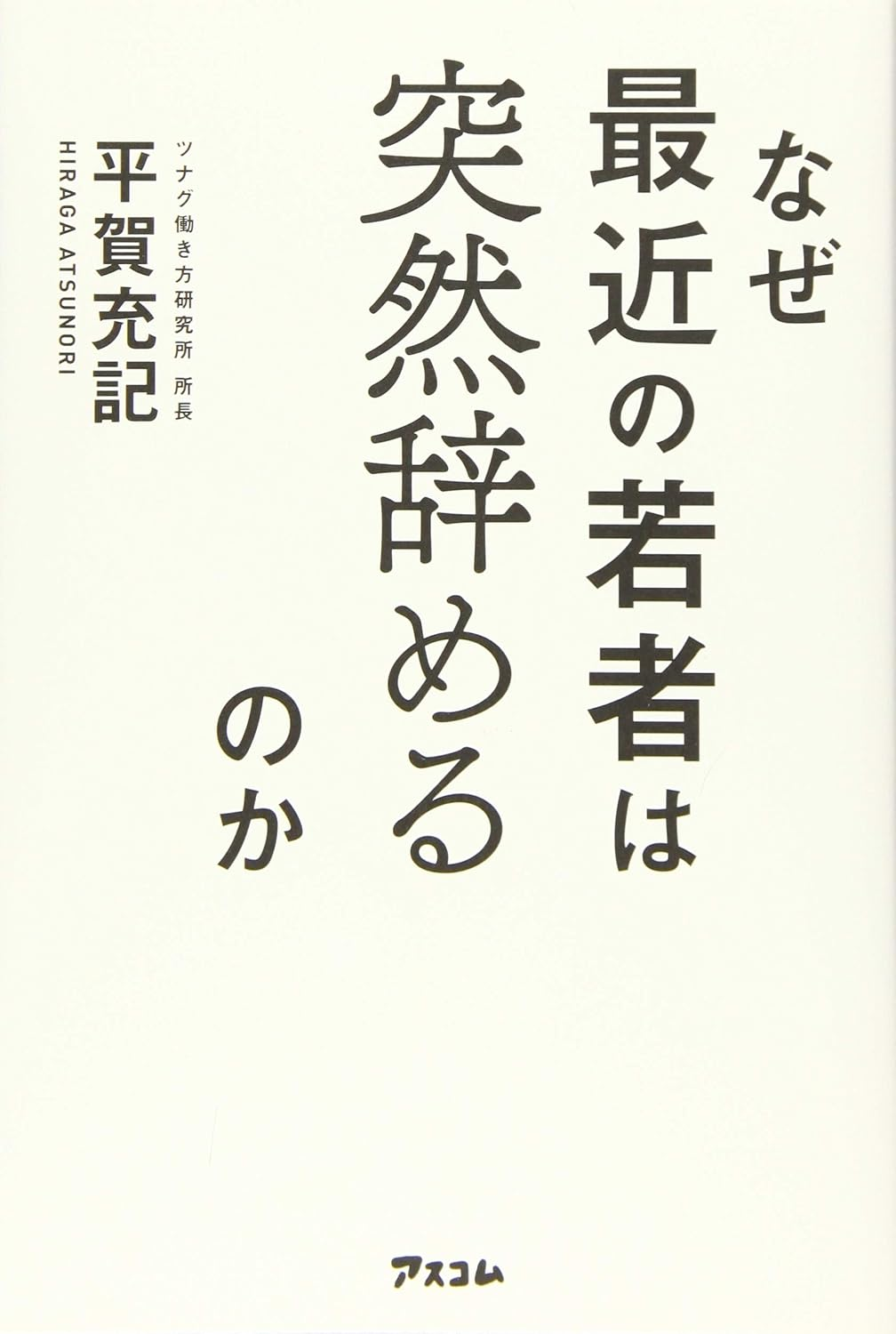
インフォメーション
| 題名 | なぜ最近の若者は突然辞めるのか |
| 著者 | 平賀 充記 |
| 出版社 | アスコム |
| 出版日 | 2019年5月 |
| 価格 | 1,540円(税込) |
なんで急に辞めたり休んだりするのかわかった。
職場の若者に気を使うストレスが減った。
部下が相談してくれるようになった。
…扱いにくい若者に悩むオトナから納得の声が続々!
30年以上、若者の働き方を研究してきた第一人者が教える
職場の若者のトリセツ
ヨコ社会、意味づけ、タイムパフォーマンス重視が当たり前!
「SNS村」で生きる若者に、これまでの職場の常識は通用しません!
・ バリバリ働いて40万円稼ぐより、そこそこ働いて20万円でいい
・ 「コスパ」の悪い飲み会、残業はNO!
・ 大きな売上をゲットするより、「お客さんが喜ぶ」ことが大事!
・ 出世してプレッシャーを背負うよりも身の丈にあったポジションで自分らしく働きたい
・ 目立つエースにはなりたくないけどベンチ要員も嫌
・ どんな暴言よりも「時間を奪われる」ことが最悪のパワハラ!
・ 石の上に三年なんていられない! 修行するより仲間とコラボして結果を出したい
・ 「自分的には普通にアリ」…はっきり白黒つけたくない
そんな若者と、どう向き合えばいいのか?
オトナがわからない若者の心の中を徹底解剖!
<若者との付き合いが楽になるコミュニケーション術が満載>
・ 褒めは質より量! 小さな「いいね!」をたくさん押す
・ ダメだしよりも「合ってるよ」「確かにね」の肯定感が大事
・ 「怒りの境界線」を先に示しておく
・ 自分の苦手なことや弱点はどんどんオープンにする
・ 役職や肩書きで呼び合うのはやめる
Etc
引用:アスコム
ポイント
- 「最近の若者はすぐ辞める」という声はあちこちから聞こえてくるが、「若者がすぐ辞める」ことが職場での一番の悩みではない。辞められることに対してビクビクしている日常、辞めさせないように気をつかいまくる日常、そんな気疲れが、マネジメント層にとってなにより悩ましいのだ。
- 現代の若者は「SNS社会」の住人である。オンラインの世界に住んでリアル世界を眺めている。その「SNS社会」は、暗黙の「掟」が存在する、「村」とでもいうべきもの。ルールを逸脱してしまうと仲間外れになるリスクが発生する。
- 若者は、社会欲求(=どこかに所属していたい)と、承認欲求(=価値を認められたい)が異常に肥大している。「みんなが自分の存在を認めて必要としてくれている」と感じられなければならない。職場のマネジメント層に求められているのは、若者の「居場所を作り出すこと」。
サマリー
若者、取扱注意
マネジメント層を悩ませているもの
「最近の若者はすぐ辞める」という声はあちこちから聞こえてくる。
だが、新卒が3年で3割辞めるのは、30年前からほとんど変わらない傾向である。
今は、「人を大事にする」ことが求められ、マネジメントが難しくなっている。
部下が辞めれば、ちゃんとケアできていたのかと管理者は責められる。
何より、戦力として期待していた人材が急にいなくなれば、自分の仕事がきつくなるし、心理的な負担にもなるだろう。
辞めさせないように、腫れものに触るように若者と相対せざるをえない。
結局のところ、「若者がすぐ辞める」ことが職場での一番の悩みではない。
辞められることに対してビクビクしている日常、辞めさせないように気をつかいまくる日常、そんな気疲れが、マネジメント層にとってなにより悩ましいのだ。
若者はITで武装している
若者はスマホを持ち歩き、24時間常時接続。
わからないことがあればすぐにググる、参考資料はアマゾンでポチる。
自前の知識が豊富かどうかなど意味をなさない。
先人がたどり着いた答えをシェアすることが合理的、これが若者だ。
どれだけ時間と経験を重ねて企画書を作り上げたとしても、そのノウハウはテクノロジーで簡単にシェアできる。
積み上げた知識が100あっても、テクノロジーを使いこなす力が10しかなかったら、若者から見ると「仕事ができない人」と同義である。
単純な知識でない部分でオトナが価値を示さないと、若者はついてこない。
若者は「SNS社会」の住人
これまでのオトナと若者のギャップは、生きる時代の違いだった。
しかし今は、両者は生きる空間まで異なる。
現代の若者は、「SNS社会」とでもいうべき、常時接続のオンライン空間に生活の大きな比重を置いている。
オトナはSNSをツールとして使っているが、考え方や価値観はリアル社会が前提であり、基本的には「オフラインの住人」だ。
だが若者はSNS社会の中で仲間を見つけ、そこを住み家としている。
オンラインの世界に住んで、リアル世界を眺めている状態である。
その「SNS社会」は、暗黙の「掟」が存在する、「村」とでもいうべきもの。
ルールを逸脱してしまうと、仲間外れになるリスクが発生する。
この「SNS村社会」に住む若者たちの特性は、大きく分類すると、「過剰忖度」「相対的自意識」「ヨコ社会」「イミ漬け」「時間価値」である。
オトナは若者とどう向き合うべきか
関わる・近づくコミュニケーション
若者に近づくためのポイントは、コミュニケーションの「質より量」を意識すること。
職場には、「話しかけないでオーラ」が出まくっている若者がいるかもしれない。
しかし、若者はタテの人間関係が苦手なだけで、「居心地のいいフラットな人間関係」自体は強く求めている。
現代の若者は、社会欲求(=どこかに所属していたい)と、承認欲求(=価値を認められたい)が異常に肥大している。
単に雇用関係が結ばれているという安心感だけではダメで、「みんなが自分の存在を認めて必要としてくれている」と感じられなければならない。
職場のマネジメント層に求められているのは、若者の「居場所を作り出すこと」。
簡単な声かけひとつでも、彼らに居場所を感じてもらうことはできる。
ちょっと近づくことから始めてみてはどうだろうか。
共感と安心を育むコミュニケーション
次に必要なのは、本質的な信頼関係を築くことである。
信頼関係を築くには、「秘密の窓」と「盲点の窓」が重要とされている。