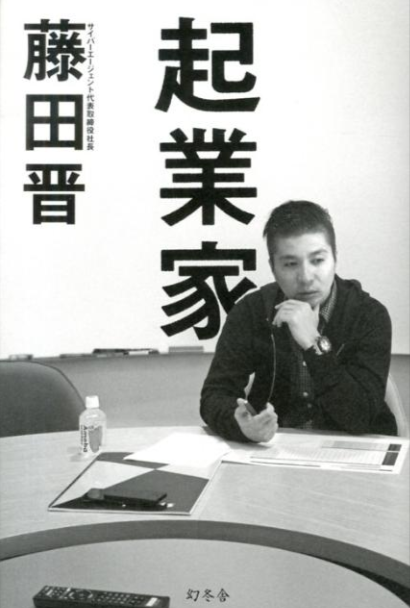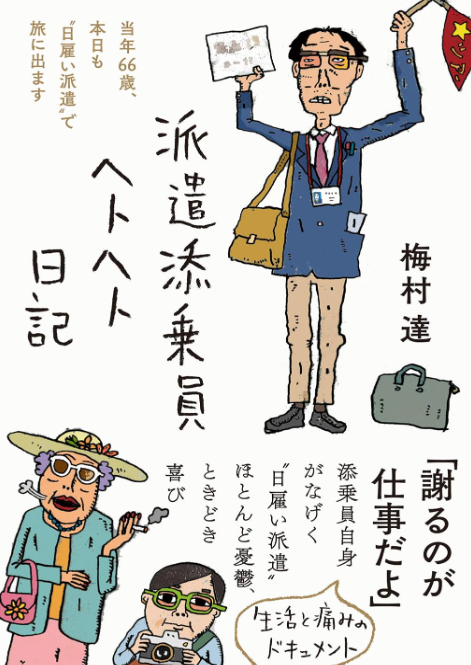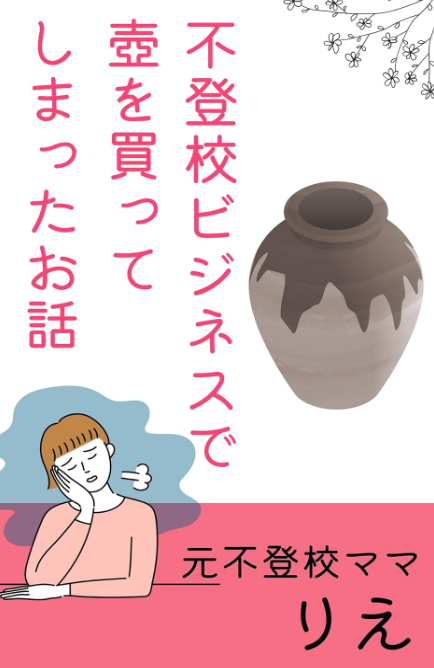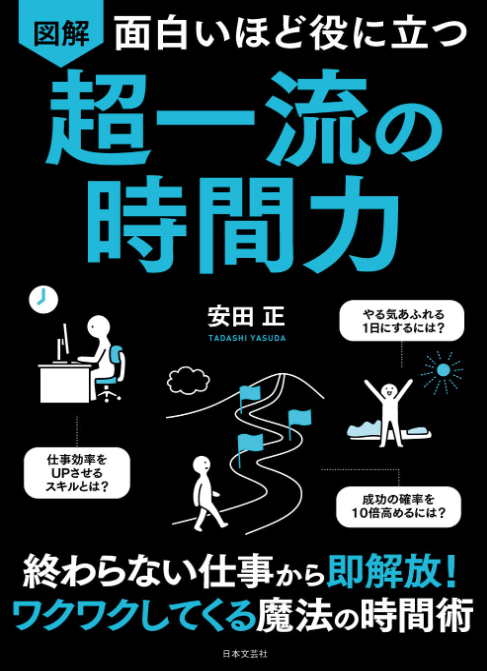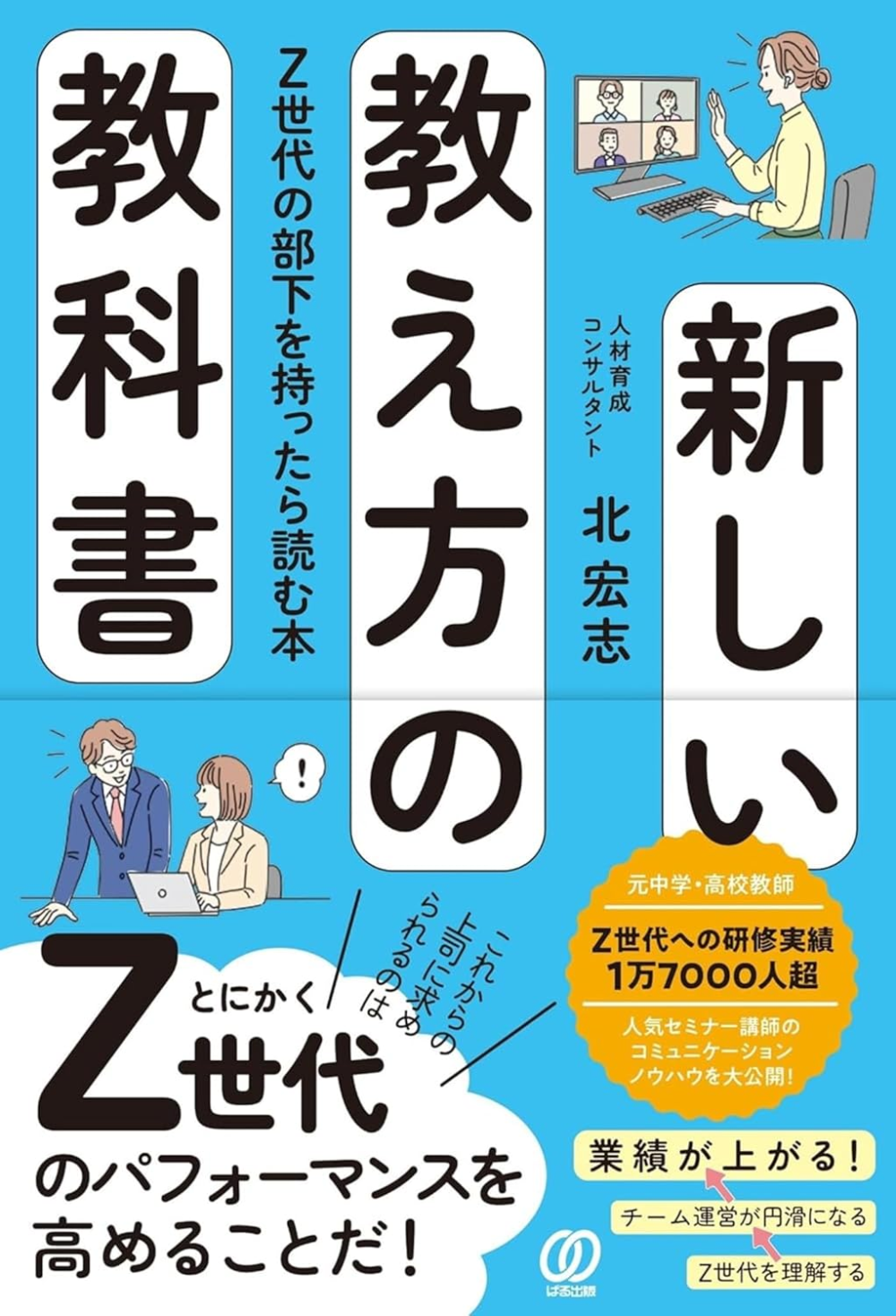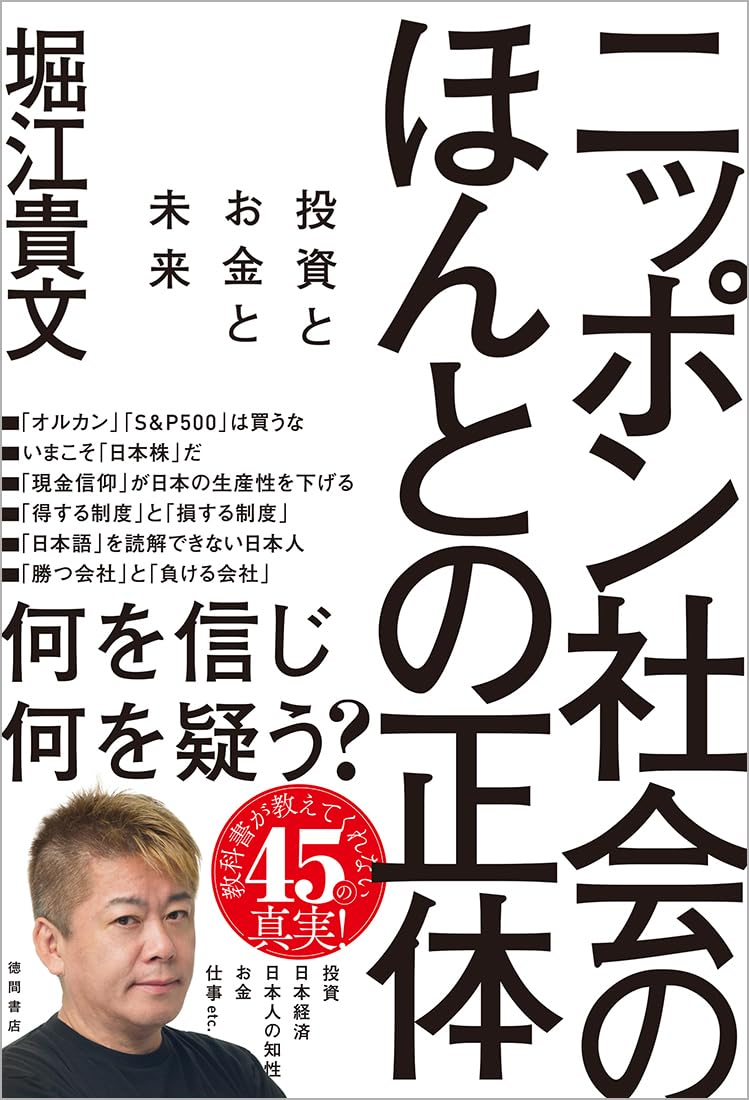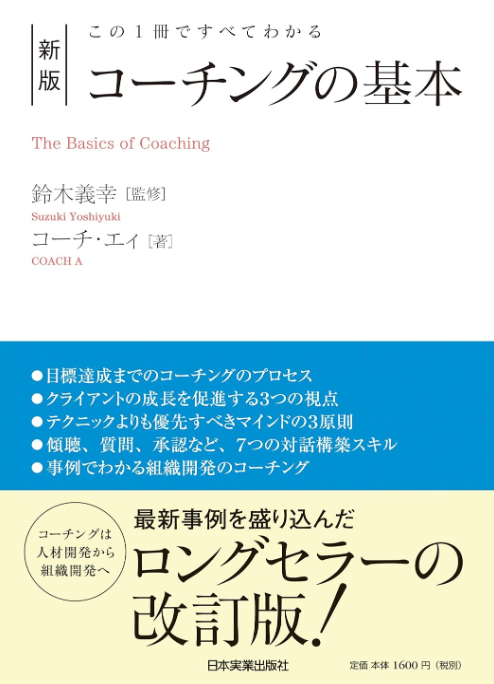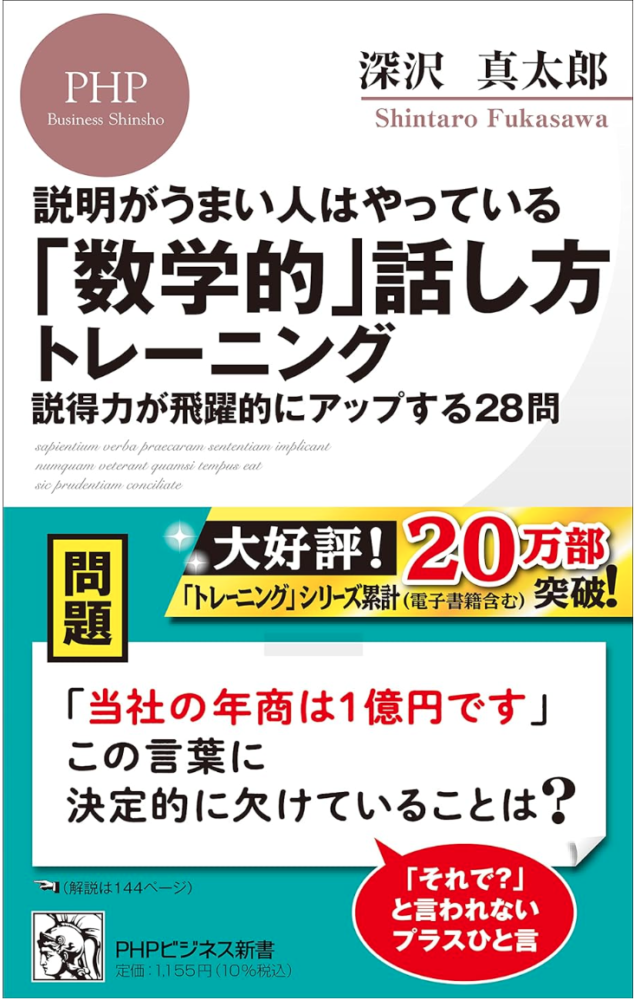【否定しない習慣】

インフォメーション
| 題名 | 否定しない習慣 |
| 著者 | 林 健太郎 |
| 出版社 | フォレスト出版 |
| 出版日 | 2022年12月 |
| 価格 | 1,650円(税込) |
相手のことを「否定しない」という習慣術
「よく人間関係でトラブルになる」
「部下が成長してくれない」
「すぐに子どもを怒ったり責めたりしてしまう」
といったことはありませんか。
部下や上司、同僚や友人、親・子ども……
など人間関係が良好な人ほど幸せ度が高いと言われています。
実際、対人関係が良好でない状態だと、
どれだけ好きな職種についていても、
どれだけお金を持っていたとしても
「幸福感」を感じられないというデータもあります。
そして、そんな対人関係を良くする方法として、
「褒める」「肯定する」といったことが取り上げられます。
部下や子どもを成長させたいと思う人であれば、
ここに「叱る」という選択肢もあるかもしれません。
しかし、「褒める」「肯定する」「叱る」といった方法以上に、
効果的かつ、簡単に人間関係を良くする方法があります。
それが「相手のことを否定しない」ということです。
誰かを意識的に「褒める」といったことをする必要はありません。
いい関係をつくる上で大切なのは、「安心感」です。
この安心感は、「褒められる」「肯定される」といったことでは作られません。
・何を言っても否定されない
・話を向き合って聞いてくれる
・ミスや失敗を責められない
といった「否定されない」ことで生まれてくるのです。
逆を言えば、いつも人間関係でトラブルを抱えたり、
お互いがお互いに信頼できる関係を作れない人は
無意識に「相手の否定をしている可能性」が高いのです。
・相手の話を聞かない、話を奪う
・ミスをしたら失敗を責める
・相手の意見や考えを頭から否定する
・相手の相談に真剣に向き合わない
これらは全部否定です。
あなたがもし、人間関係を良くしたい、
信頼関係をつくるコミュニケーション力を身に着けたい
と思っているのであれば、
「否定しない習慣」を手に入れましょう。
本書では、プロのコーチが使っている「否定しないコミュニケーション技術」と
そのコミュニケーションの習慣化についてまとめた一冊です。
人間関係をよくしたい、誰かといい関係を築きたい、
いい関係をつくるコミュニケーションを身に着けたい
という方にオススメです。
引用:フォレスト出版
ポイント
- 多くの人は、知らないうちに否定をしてしまっている。「悪意」はなく、よかれと思って「相手のために否定する」というメカニズムである。この「よかれと思って」が否定を正当化してしまう。
- 否定をやめるメリットは様々あるが、とくに大きいのは、「心理的安全性」が確保されること。「否定しない」ことで、とてもいい人間関係がつくれる。
- 否定しないためには、「事実だから否定してもいい」という思考はしないこと、「自分は正しい」という思考はしないこと、相手に「過剰な期待」はしないこと。
サマリー
はじめに
仕事や育児において、「褒める」「肯定する」「叱る」がいい方法だと言われる。
しかし著者は、もっとも効果的なのは、相手を「否定しない」ことだとする。
その技術を身につければ、人間関係が劇的に変わるという。
気づかないうちに否定する人の心理
多くの人は、「否定ばかりしないほうがいい」と認識しているが、知らないうちに否定をしてしまっている。
小学生になる自分の子どもが「将来は宇宙飛行士になりたい」と言ってきたら、「そんなの無理」と言ってしまうかもしれない。
「実現するわけがない夢からは、早く目覚めさせたほうがいい」という無意識の「親心」が働くのだ。
ここに「悪意」はなく、子どものために「よかれと思って」言う。
「相手のために否定する」というメカニズムなのだ。
この「よかれと思って」が否定を正当化してしまうから厄介である。
「否定しない」が心理的安全性を生む
否定をやめるメリットは様々ある。
とくに大きいのは、「心理的安全性」が確保されること。
心理的安全性とは、「チームにおいて、どのような発言や指摘をしても、否定や拒絶をされたりする心配がない状態」である。
グーグルの研究結果によれば、「生産性の高いチームや組織には心理的安全性がある」という。
心理的安全性は、ビジネスだけでなく、個人間の一般的なコミュニケーションの場合でも生まれる。
「否定しない」ことで、とてもいい人間関係がつくれるのである。
「否定しないマインド」のつくり方
「事実だから否定してもいい」という思考はしない
部下のことを無自覚で否定している上司は、よく、「事実を伝えているだけ」、「間違っているから指摘しただけ」と言う。
しかしこの思考は、否定を肯定し、正当化することになる。
ここで考えるべきは、「事実かどうか」でもなく、「否定しているか、していないか」でもない。
「言われた相手が否定されたと受け取るかどうか」である。
知らず知らずのうちに相手を否定していないか、まず気づくこと。
そのためには、「相手の態度」を観察する。
ムッとしていたり、うつむいて黙っていたりしたら、相手を否定してしまった可能性が高い。
「自分は正しい」という思考はしない
日常的なコミュニケーションにおいては、どちらかが一方的に間違っているのではなく、どちらにも一理あるという場合がほとんどである。
「正しさ対決」では決着はつかない。
意見の違いを否定するのではなく、意見の違いを理解して、目的を共有すること。
「両方の意見のいい部分を合わせた選択肢をさぐる」という方向へ軌道修正するとよい。
「過剰な期待」はしない
期待が裏切られると、人は相手を否定しがちである。
部下に仕事を任せても、期待に達していないと、相手を責めてしまうこともある。
しかし、部下はわざとパフォーマンスを低くしているわけではない。
ただ、進め方がうまくなくて結果が出ていないだけだ。
「その人なりに精一杯やっている」と思えば、瞬間的に否定することはなくなる。
否定しない技術
イエス・エモーション話法
否定しない技術として「イエス・バット話法」が有名だが、これは否定することには変わりない。
そこでお勧めしたいのは、著者が開発した、相手をより気持ちよくさせる「イエス・エモーション話法」。
肯定の言葉に加えて、ポジティブなプラスの感情を伝える話法である。
こうすることで、相手の承認欲求を満たすことができて、関係がいい方向に向かう。
「仕事、頑張っているんだね。頼もしいと感じたよ」
「髪を切ったんだね、すごく似合っていると思うよ」
そのあとに、自分が言いたい意見を言う。
それは、相手と異なる意見であってもOKだ。
能動的に黙る
「言葉を返す前にブレーキを踏む」ことも、「否定しない」ための大事な技術である。
「ブレーキを踏む」とは、まずは「黙りましょう」ということ。
コミュニケーションのトラブルの多くは、脊髄反射的に言葉を返したりすることから始まる。
SNSで、相手がどう思うか考えず、反射的、直情的に悪口を書き込むのがその象徴だ。