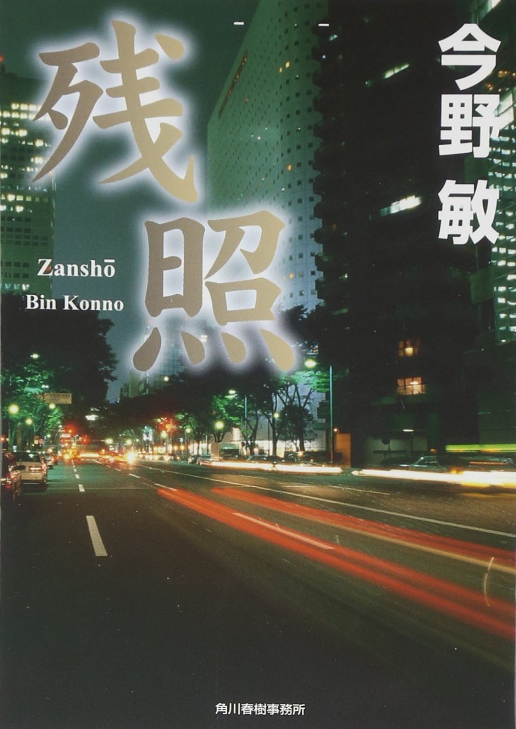【赤い月の香り】

インフォメーション
| 題名 | 赤い月の香り |
| 著者 | 千早茜 |
| 出版社 | 集英社 |
| 出版日 | 2023年4月26日 |
| 価格 | 1,760円(税込) |
登場人物
・朝倉満
朔の元で家政婦、雑務として働く
・小川朔
調香師
・新城
興信所の探偵
・茉莉花
歯科衛生士
あらすじ
※一部、ネタバレを含みます。
※本記事は要約記事ではなく、自身の言葉であらすじ及び感想を書いたものです。
怪しいふたり
短髪の一人の男。
捉えどころのない表情に、どことなく淡い色の髪。
安っぽいカフェで、その男の周りだけ青い夜の気配がただよっているように見えた。
向かいには黒ずくめの男が座っている。
そのテーブルに満は料理を運ぶ。
ふいに、短髪の男が「この職場は君に合っていない」「ストレス臭が充満している」「君からは怒りの匂いもする」と言う。
うちで働くといい、と白い紙片を残して歩き去っていった。
すれ違った瞬間、短髪の男から香りがたった。
香水でも柔軟剤でもない、瑞々しい野菜や果物を切った時のような匂いがした。
何者をも寄せつけない、凛とした孤独を保つ香りだと思った。
これはどこの香水かと、黒ずくめの男に聞いた。
「香水じゃなくて香り」「どこにも売っていない。この世にひとつだ。あいつしか作れない」
朔の嗅覚
店で名刺を渡してきた奇妙な二人組の面接へ行く。
短髪の男は調香師だった。
依頼主が望めばどんな香りでも作る。
面接のあと、そのまま満は寝込んだ。
高熱の中、朔が渡してきた小瓶の蓋を開けて一口飲む。
かすかに薬臭く、甘ったるい匂いがした。
すうすうと熱を奪っていく。
朦朧とした意識の中で懐かしい香りだと思った。
二日目の晩には熱が下がり、「三日後の朝、七時に」という朔の静かな声がよみがえる。
熱が出ることも、三日後には回復することも匂いで朔は全てわかっていたのだ。
朔の香り
満の一日の仕事はシャワーから始まる。
朔から自宅で使って欲しいと、シャンプー、石鹸、化粧水、保湿クリーム、ヘアワックス、歯磨き粉、衣類用洗剤や柔軟剤まで手渡してきた。
その全てが朔の手作りだ。
朔の調香によって作られていた。
自分の許容しない匂いは何一つこの洋館には存在させないという偏狭で強固な意志を感じさせた。
与えられた香りに染まっていくと、満の輪郭が朧になる気がした。
朔が作った香りに包まれた満と、元の満とが乖離していくような錯覚。
まるで幽霊になったみたいな気分になる。
それが嫌なのか、楽なのか満にはわからなかった。
自分であって自分ではない
「虫歯ができている」朝の挨拶もなく、朔は満の顔を見るなりそう言った。
何度、歯を食いしばっても、別にどこも傷まない。
しかし奥歯の詰め物の中で虫歯菌が繁殖していたらしい。
こんなに初期の段階でよく気づいたねえと歯科医は何度も首を傾げた。
治療が終わると歯科衛生士が満の胸の辺りに顔を近付けてきた。
「なんの香水つけてんの?」朔に作られた香りでできている満。
この女性が興味を持っているのは俺であって俺じゃないと満は思う。
そうすると身体を縛っていた警戒心や嫌悪感がすっと消えた。
代わりに、好奇心がわいた。
「今度、持ってこようか」と言い、連絡先を交換する。
盗み
満はそっと貯蔵庫へ行って透明な瓶に手を伸ばす。
スポイトを使って少しずつ手持ちの小瓶に移していく。
そうして、夜は茉莉花を部屋に呼んだ。
茉莉花にもまずシャワーを浴びてもらう。
シャワーを浴びた茉莉花の肌はしっとりと柔らかく、心地好い冷たさがあった。
汗ばむ身体からも髪からも、洋館の静かで瑞々しい香りがただよう。
人の肌の生々しさより、清涼な植物を思わせる香りだ。
この香りがあれば、満は平静さを保てる。
衝動に呑み込まれることはない。
しかし、朔は気付いている。
満が朔の調香したボディケア用品をこっそり盗んで茉莉花に与えていることに。
もしかしたら新城に調べさせたのかもしれない。
しかしこの香りを失ったら、満は茉莉花とはいられない。
母親の存在
「残業をお願いできるかな」と朔が言った。
やっぱりそうか、と満は思う。
今日が最後の仕事だ。
満は謝り、どうしてもこの香りがないと誰かといられないこと、自分が呑み込まれてしまうこと、朔に香りを作ってほしい、と言う。
しかし、朔には分かっていた。
誰かといられないんじゃなくて、自分を落ち着ける香りがないと女性に触れられないことを。
そして、満が嫌悪しているのは母親という存在ということを。