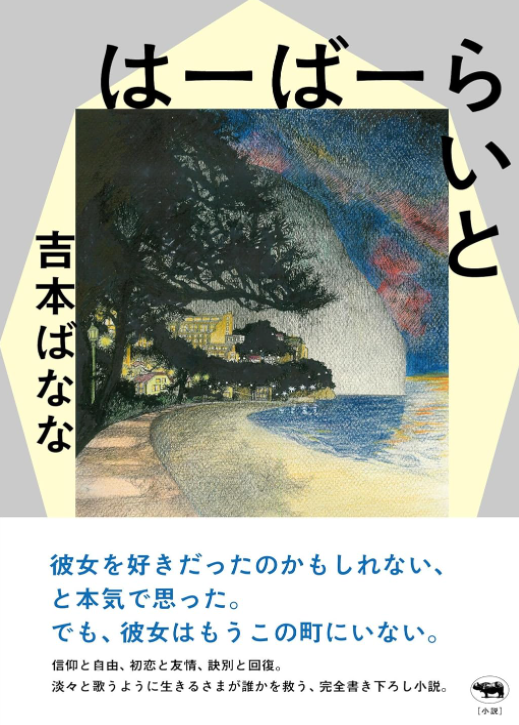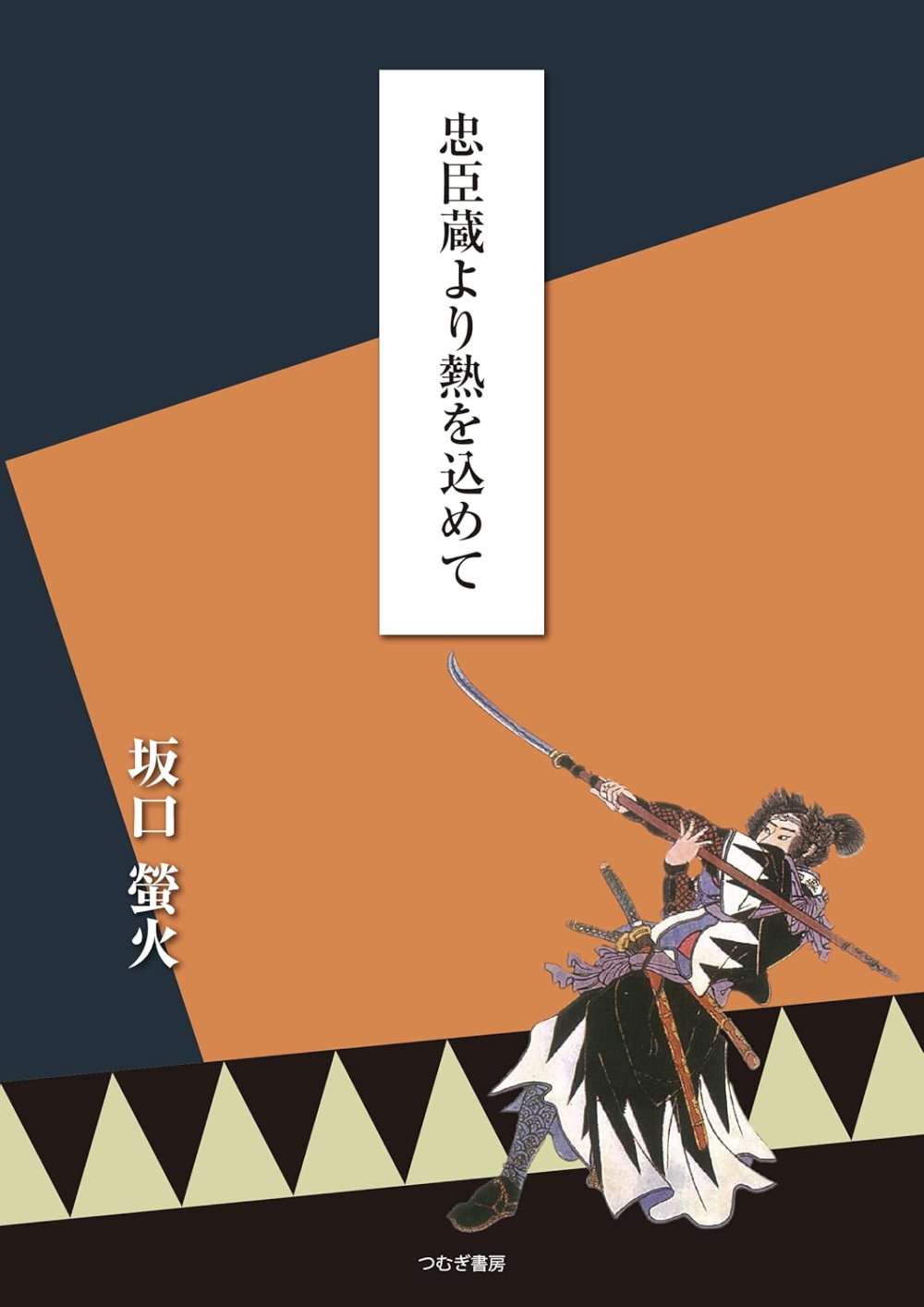【さんかく】

インフォメーション
| 題名 | さんかく |
| 著者 | 千早茜 |
| 出版社 | 祥伝社 |
| 出版日 | 2019年11月1日 |
| 価格 | 1,650円(税込) |
登場人物
・高村
フリーランス。京都の町家で暮らす。
・伊東正和
高村の六つ年下。華の彼氏。
・中野華
伊東の彼女。研究者。
あらすじ
※一部、ネタバレを含みます。
※本記事は要約記事ではなく、自身の言葉であらすじ及び感想を書いたものです。
再会
伊東と高村は一緒に働いていたことがあった。
軽食もできるカフェで、高村はキッチンで、伊東はホールに立っていた。
高村のまかないは人気だった。
他の人は、カフェの余った食材で作るので毎回パスタだったが、高村はまかない用に食材を持ち込んだ。
実家から送られてきたという野菜で具沢山のスープを作ったり、古くなったバケットはコロッケの衣やデザートのパンプディングになった。
どうしてわざわざ食材を持ってきてまで凝ったまかないを作ってくれるのか。
「一日二食だから食事の半分がここなわけで、いいかげんなものを食べたくないの」と高村は仕込みの手を止めずに言った。
伊東は、働くようになってから、その言葉を時々思い出した。
インスタント食品で昼を済ます時、閉店間際の値引きシールの貼られた弁当を籠に放り込む時、この食事は人生の食事の何割を占めるのだろうと考えることがあった。
去年の師走に居酒屋で偶然、隣り合わせになり、伊東から声をかけた。
それから、月に一、二度、飲みに行くようになった。
高村に再会して、あのまかないが懐かしくなった。
久しぶりの高村のご飯
一緒に飲んでいると、伊東が酔い潰れた。
目を覚ませば、細長い日本家屋。
高村の住んでいる町家だった。
伊東の会社に雑談しにくるお婆さんから人参をたくさんもらって、人参しりしりと味噌汁、鮮やかなオレンジ色のあけぼのご飯を作った。
オレンジ色の見た目の鮮やかさに反して、優しい味だった。
ほのかな酸味で口の中がさっぱりして、いくらでも食べられそうだ。
しりしりも甘じょっぱくて箸が進む。
空っぽの胃がオレンジ色で満たされて行く様を思うと、冷えていた手足がだんだんと温まっていった。
伊東はわざと傘を忘れて帰った。
伊東の彼女
動物は食べ物に合わせて体を変えるけれど、ヒトだけは食べ物を加工して自分たちに合わせる。
つくづく特殊な種だと、食べ物を見るたびに華は思う。
けれど、そんな内容を伊東に送ってもしょうがない。
華の言うことはたいてい人を困惑させる。
同じ研究室の人たち以外は。
華と伊東のデートは今まで何度となくドタキャンがあった。
広島に行った時は、「アミメキリンが…」ときびすを返し、温泉旅行の途中で電話が鳴り「コビトカバ?!」と叫んで帰ってしまったこともある。
クリスマスは二人分のコース料理を伊東一人で片付けねばならなかった。
華はいつも必死で謝るが、電話が鳴ると心はもう大学へと飛んでいるように見える。
こうも会えないと、付き合っているのかどうかすら伊東はわからなくなっている。
でも、華は平然としている。
つい湿っぽい感傷に囚われている時、高村からご飯の誘いがきた。
一緒にパクチーと羊の水餃子を食べる。
ふと、伊東が「今のアパートが更新なんですよ」と華に話すつもりだったことを高村に話していた。
「ここ部屋余っているけど」
罪悪感
茄子のピリ辛味噌炒めにピーマンとじゃこのきんぴら。
冷蔵庫にある高村の作り置きおかずは自由に食べてもいいことになっているので、伊東はタッパーに詰めて弁当にしている。
昼の外食をやめて高村のおかずとおにぎりを持っていくようにしてから体が軽い。
会社の人に結婚したのかと疑われ、「同居人です」と答えた。
間違ってはいないが、うっすら罪悪感めいた気分になるのが落ち着かない。
伊東はまだ華に引っ越しのことを言っていなかった。
バレる
いつも来てもらってばっかりだから伊東の住む大阪まで行ってしまおう、と思い立った華。
伊東がきてくれるのは嬉しいけど、解剖の後だったりすると大変。
風呂で髪まで洗って臭いを落として、部屋に散乱したものをクローゼットに押し込んで、いま帰ったところという顔で出迎えなければいけない。
嬉しいけど、焦る。
「いま家だよね」とメッセージを送ると、伊東から着信があった。
「あのね、華、いま、そっち、いないんだ」
伊東の外泊が増えた。
深夜にでていくこともある。
夕飯も高村が誘わなくては家で食べなくなった。
携帯を肌身離さず持っている。きっと異性関係のことだ、と高村は気付いていた。
「実は最近ちょっとやばいんです」「彼女にバレちゃって」と伊東は言った。
高村は思わず口が半開きになった。
彼女がいて、隠していたわけ?
高村は「いや、知らないから」とさえぎる。
巻き込まれるのは迷惑。
そこまでは言わなかったが、背を向けたので伝わっただろう。
どっち?!
どうして京都に引っ越したことを秘密にしていたの、と華は言った。
「実は先輩の家でさ」と組み立てたストーリーをたんたんと話す。
先輩と一緒に住んでいた人が突然出ていってしまい、一軒家だし家賃で困っていたから伊東が住むことになった。
忙しくて知らせるのが遅くなった。
せっかくだから会って話そうと思っていた。
同じ京都なら華にも会いやすくなる。
本当は華と住みたかったんだけど、と付け加えるのを伊東は忘れなかった。
その日から、華は帰宅すると伊東に連絡をするようになった。
伊東は華の家に向かうとき、町家に残してきた高村のことがよぎる。
高村が作った料理の配膳を手伝い、湯気のたつ食事を二人でとり、そこから、伊東だけ他の家へとそそくさと出ていくのが、悪いことをしているように感じてしまう。
高村からは朝帰りをしても、詮索されることも嫌みを言われることもない。
朝帰りは辛く、華の帰宅が遅いから睡眠時間も削られる。
華に付き合って深夜にコンビニ弁当やインスタント食品を食べてしまうから体重も増えた。
伊東にとっての家はどっちだろう、と思った。
心は華にある。
けれど生活はあの町家にある。
穏やかで居心地の好い暮らしがある。
感情は?生活に宿るのか、心に宿るのか。