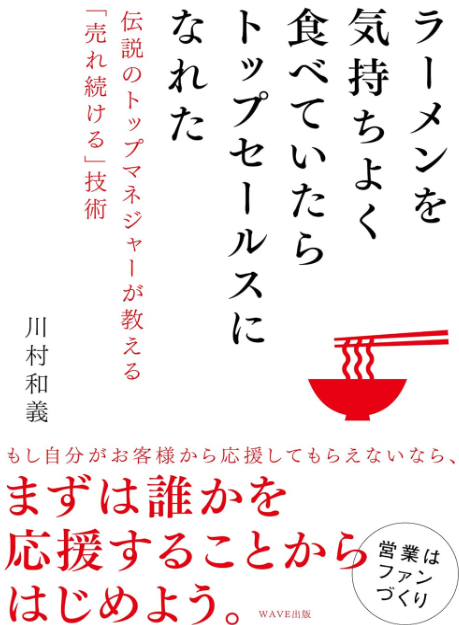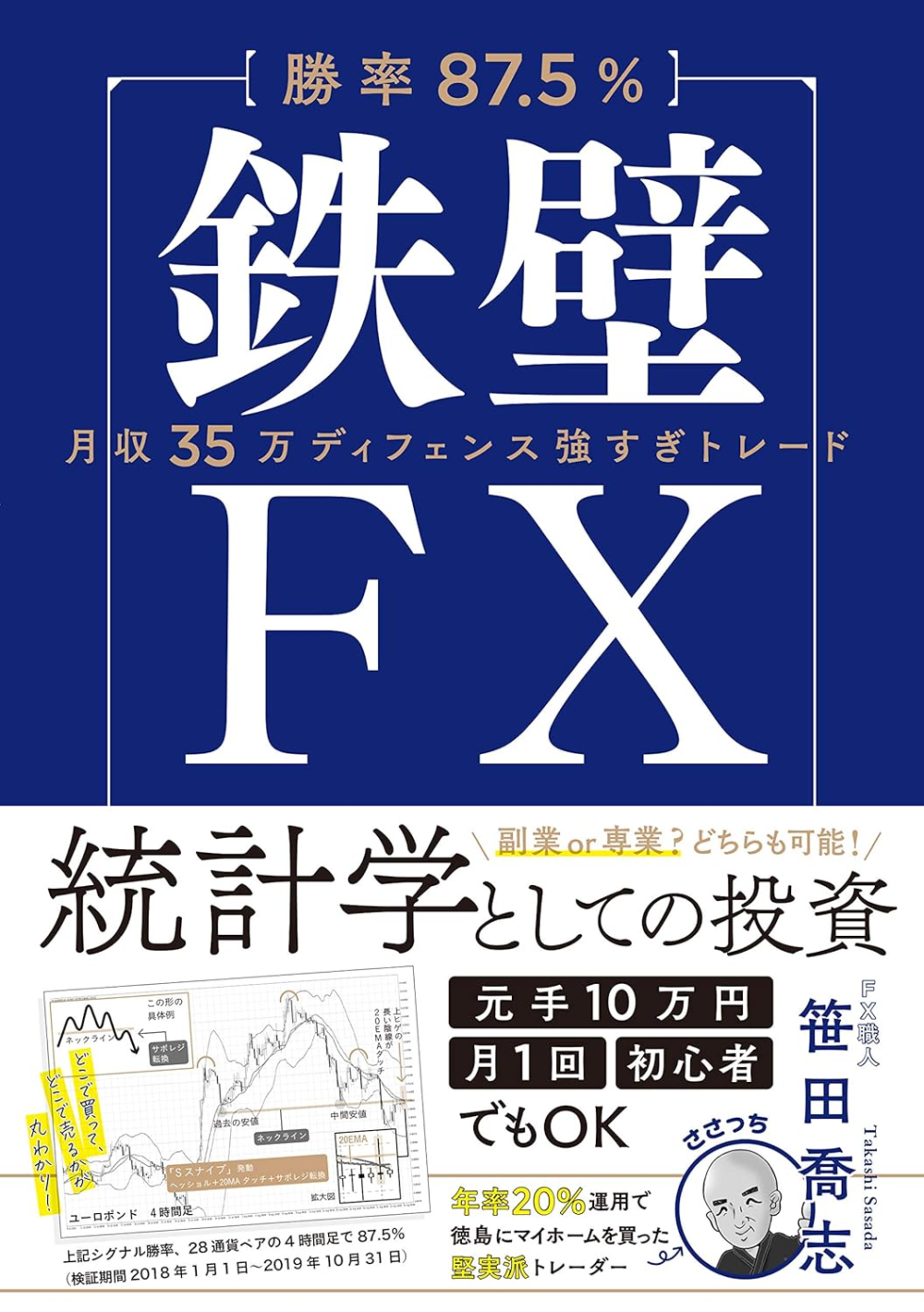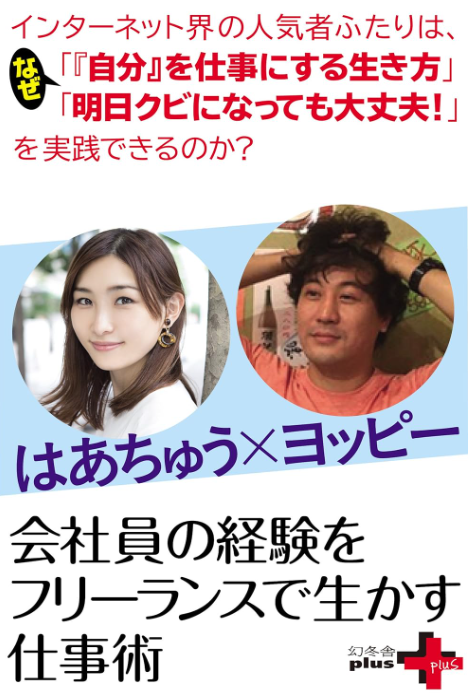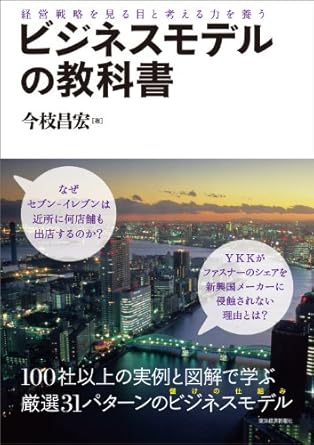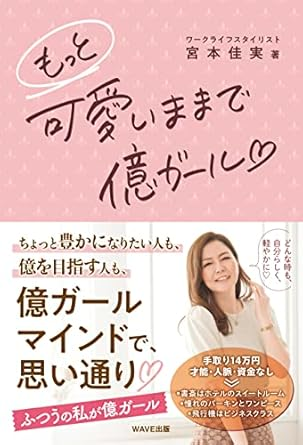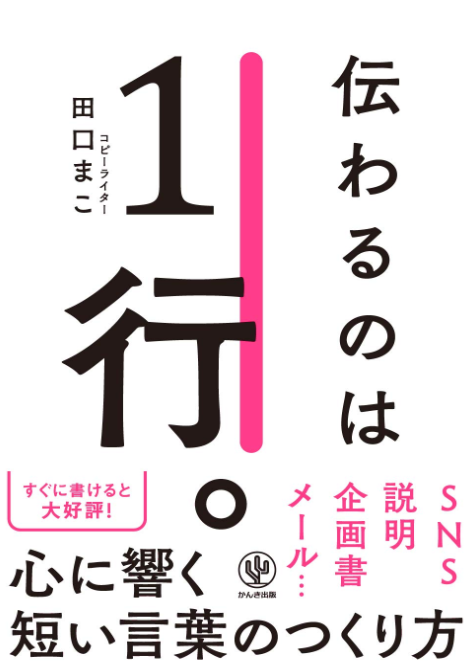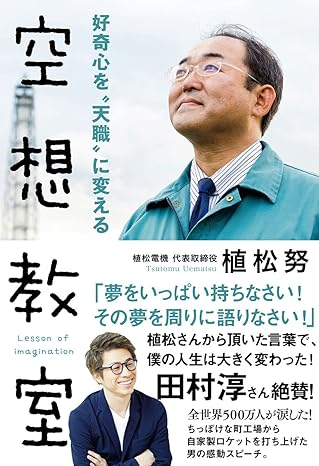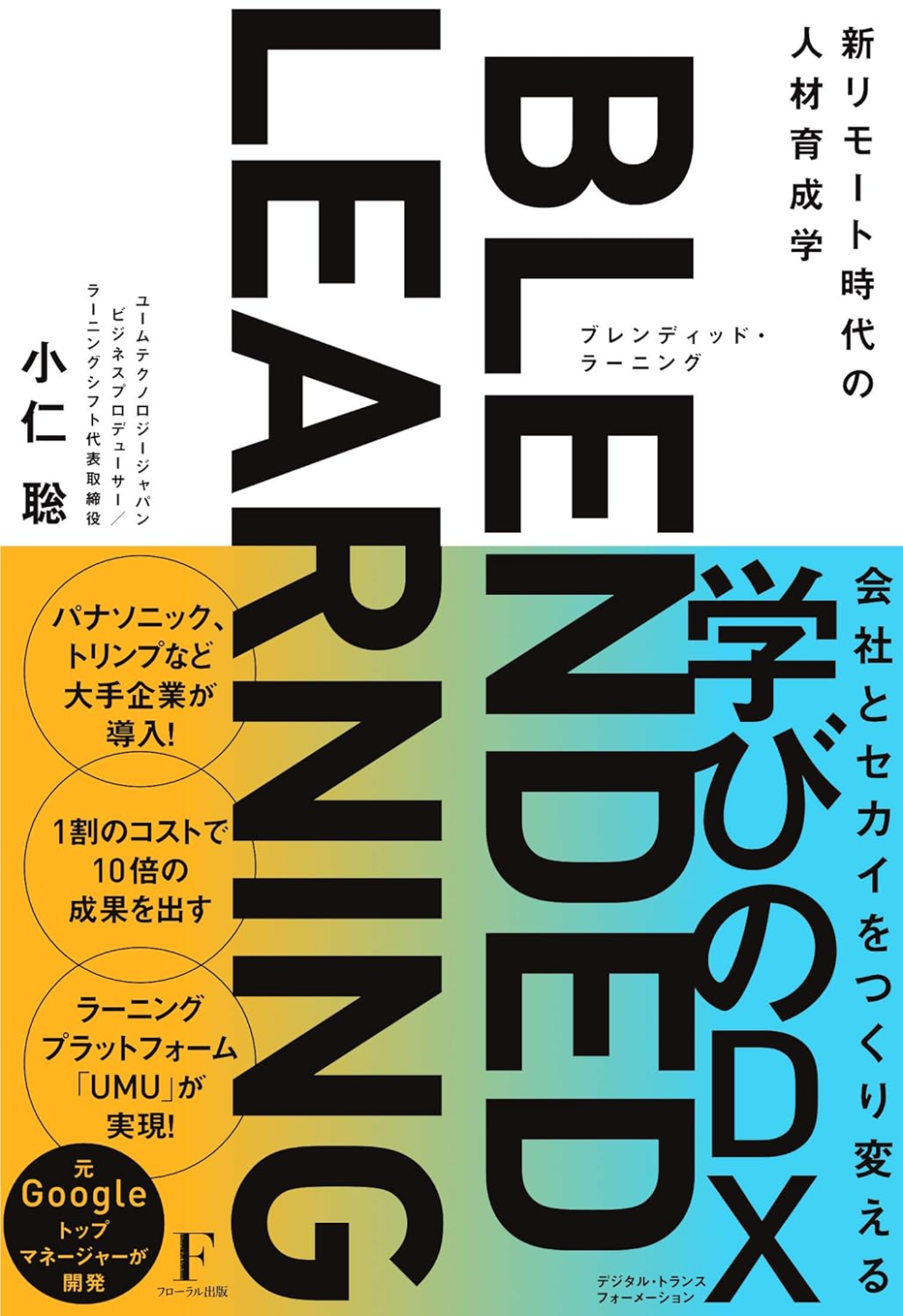【不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック】
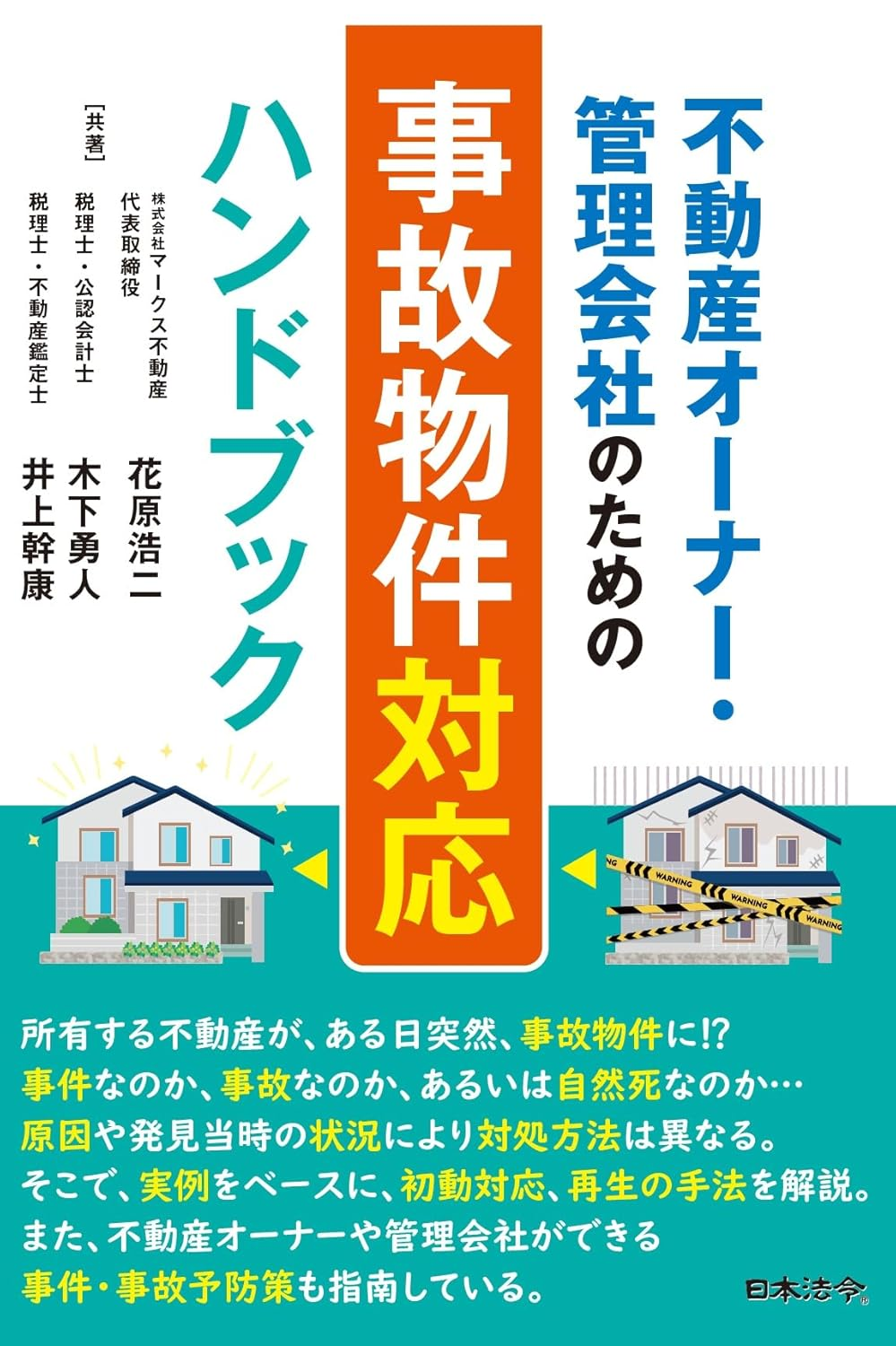
インフォメーション
| 題名 | 不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック |
| 著者 | 花原浩二 木下勇人 井上幹康 共著 |
| 出版社 | 日本法令 |
| 出版日 | 2024年2月 |
| 価格 | 3,190円(税込) |
所有する不動産が、ある日突然、事故物件に!?
超高齢化や生涯未婚率の上昇などに伴い、単身世帯数が増え、また、世界情勢の不安や物価の上昇、疾病や失業といった環境下で、孤独死や自殺、殺人事件は増加傾向にあります。
そのような状況で、不動産オーナーが所有する不動産が、人の死の絡んだ不動産(心理的瑕疵物件)、いわゆる「事故物件」となってしまったら、どうすればよいのか…。
本書は、行き場のない「事故物件」を引き受け、成仏させて新たな不動産に再生するサービスを展開する筆者が、不動産オーナーができる事件・事故の予防策や、有事の際の初動対応から手に負えない場合の最終手段まで、過去の実例を参考に解説。
国土交通省より策定された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を踏まえて解説することにより、今まであいまいな判断で取り扱っていた事故物件への対応をクリアにしています。
また、事故物件が与える不動産評価や税務への影響についても解説されており、困った時の不動産オーナー必携の書!
引用:日本法令
ポイント
- 本書は、事故物件の現状を理解し、適切な処理と正しい取引を行い、事故物件に抵抗のない人に届けていくために書かれた。
- 令和3年、国土交通省が『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を発表した。もし、ガイドラインを知らずに、それを破ってしまうことは、多大なリスクが伴う。
- 事故物件が必要な不動産として世の中に送り出されるためには、多くの課題を超えなければならないが、著者には人生をかけてなし得たいことがある。それは、遺族の痛めた心の負担を軽くし、少しでも胸を張って過ごしてもらえる世界を創り、「事故物件を誇れる選択肢へ」ということだ。
サマリー
事故物件とは
「事故物件」と聞くと、怖いとか気味が悪いというようなマイナスのイメージを持つ方が多いだろう。
実は「事故物件」という言葉は、不動産取引における俗称で法律で定められているものではない。
本書では、令和3年に国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を受け、住居用不動産取引において告知が必要とされる事象が発生した不動産を「事故物件」と定義している。
そして、「事故物件」に関わる可能性がある不動産オーナーや管理会社が、どのように対応するべきかを詳細に伝えている内容だ。
著者はハウスメーカーでの17年の勤務を活かし、より人の役に立つ仕事を求め、空家問題の解決をするために不動産業として起業した。
その中で、孤独死が発生した、いわゆる「事故物件」の相談を受けたという。
著者はその時の心情を語っている。
「事故物件のネガティブな印象によって苦しめられている遺族の姿を目の当たりにし、事故物件の概念が打ち砕かれました。事故物件の扱いに困っている遺族…そのような方々を救いたいという気持ちから、ついに成仏不動産サービスを開始しました。」
日本は、超高齢化が進み、生涯未婚率も上昇する中で、単身世帯は増えている。
また、社会情勢の変化から孤独死や自殺、殺人事件の発生が予想される中で、事故物件の問題は身近に起こってもおかしくないのだ。
本書は、事故物件の現状を理解し、適切な処理と正しい取引を行い、事故物件に抵抗のない人に届けていくために書かれた。
著者は、万一事故物件を扱うことになった場合でも、慌てず恐れず正しく対応し、”負動産”を”富動産”として世の中に送り出すことを願っている。
『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』の制定
前述した通り、令和3年、国土交通省が『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』(以下、「ガイドライン」)を発表した。
著者は「ガイドライン」の内容を、以下のように端的に表現している。
・売買契約・賃貸契約ともに、特殊清掃を行わない自然死や不慮の死などの場合は告知不要
・賃貸契約の場合、自殺や他殺、特殊清掃が行われた自然死や不慮の死等の場合でも3年程度経過したら告知不要
・売買契約・賃貸契約ともに、隣接する住戸や通常使用しない集合住宅の共用部分は告知の対象外
このガイドラインは、「事故物件」を取り扱う際に、トラブル未然防止の観点で、宅地建物取引業者が果たさなくてはならい義務の基準をまとめた重要な情報だ。
また、不動産オーナーや不動産業者にとって、トラブル回避・不動産の流通促進・高齢者への貸し出しリスクの軽減など多くのメリットがある。
しかし、不動産オーナーや不動産業者をはじめ、不動産を検討する一般の顧客にも、このガイドラインの周知が進んでいないのが現状だ。
本書では、ガイドラインの内容を抜粋し、著者の詳しい解説が添えられているので、実践に役立つよう構成されている。
もし、ガイドラインを知らずに、それを破ってしまうことは、多大なリスクが伴う。
宅建業法の違反に問われたり、民事の損害賠償事件に発展する可能性もあるのだ。
まずは、ガイドラインの内容を遵守し、判断に迷うケースは、宅建協会の相談部署や弁護士などの専門家に相談することで、リスクを減らすことができる。
有事の対応
実際に、事故物件に関わることになった場合、不動産オーナーや不動産業者はどのような対応が必要になるのだろうか。
本書には、孤独死・事故死・自殺・殺人などの事例と、それぞれの対応について紹介している。
ここでは、事例のひとつである、埼玉県の賃貸アパートで起きた孤独死について紹介する。
この事例では、まず、近隣住民から不動産管理会社に通報があった。
死亡から発見までの期間は約2週間で、布団の中で横を向いた形で亡くなり、電気毛布を使用していたため、布団の内部は腐敗が進んでいる状況だった。
このようなケースにおいて、不動産管理会社と貸主はどのように対応すべきか、著者はそのポイントを以下のように伝えている。
<不動産会社の対応>
・近隣住民より連絡を受けた際、現場の状況を正確に把握する
・至急保証人と連絡を取り、連絡がつかなければ、現地を確認しすぐに消防、警察へ連絡する
・親族の了承のもと、特殊清掃や遺品整理、原状回復の見積もりの提示、合意解約の署名などの手続きを進める
・貸主には逐一報告、相談をしながら、貸主の依頼のうえで対応する
<貸主の対応>